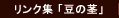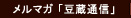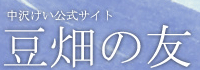 |
||||
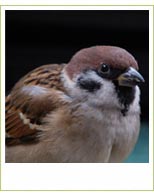 |
| タイトル一覧 |
| 最新の10件 |
| 伊藤比呂美Twitter |
| Twitter三匹の子豚リスト |
| ログ検索 |
| 年譜 |
| 著作リストへ |
| 管理者用 |
|
文庫版「女の絶望」 2011年03月05日(土) 光文社文庫から「女の絶望」が文庫になりました。タイトルが不気味だし、フェイクな江戸弁がしつこいのは重々承知の上ですが、内容は、女として生きてきたあたしが女たちを代弁して言いたかったことを網羅した集大成。と言い切りたい。「あたし」じゃなくて「あたしたち」が書きたかった。なぜフェイク江戸弁かというと、その直前に「とげ抜き」やってて、あの口調が抜けなかったから苦し紛れに。それから「とげ抜き」の文体やふつうのエッセイ文体じゃ「「女」(複数の、多数の、何代ものおびただしいさまざまな女たち)の悩みをかきたくても、「あたしのこと」として読まれちゃうから。人生相談の形式にしたのもその理由。それから、何年もの間、筆記された落語にはまっていたから。でもやってみたら、落語って男の口調で、あたしみたいな女は遊女屋のおかみくらいだということも気がついておかしかった。解説は男代表ってことで、金原瑞人さんにお願いした。金原さん、ほんとにありがとうございます。 どよーーん→おおっとーーーー 2011年03月04日(金) どよーんとしていたら、Y坂さんから電話がきてとてもありがたかった。合気道にいったら(あたしじゃなくトメ)合気道を再開したMみさんたちに再会した。それにもなんだかほっとした。つれあいのエゴと戦い、数独やネットと戦い、トメや犬や植物の世話をする、ここの生活はときどき危うい。ひきつづきThe Eagleにはなんとなく納得できず、最後のジェイミー・ベルのにこやかな笑いも(見たら楽しいんだけど)馬も馬具も砦も寒さも先住民も。ヘイドリアンの壁の向こう側の暗闇と草波を見たかったのだが、期待したほど見られなかったのだと思う。あたしは、草さえ写しておいてくれればいいのだが。とにかくいろいろ調べているが、ローマ式の鞍はあぶみがなくてもしっかりといろんなことができるそうだ。騎馬の文化についてしらべたくともネットじゃ隔靴掻痒。うちに何冊も本があるから(昔買った)早く帰らなくちゃ。ってろくでもない理由で帰るものだ。→しかし数時間後。なんとっっ書類が文字化け。今までに遭遇したことのないへんてこな障害だ。バックアップはたんねんにとってあったが、どれもダメだ。今現在、ひそかにかきためておる「日系人の現在」(仮題)のなかのいくつかの詩だ、なくなったのは。うーーーーーーいろいろやってみてるがどうにも修復できない。てんのかみさまが、よくないからすてなさい、といってたのかも、と思うが、だからしょうがない、あきらめようとも思いはするが、そういうことは、てんのかみさまじゃなくてあたしに決めさせてもらいたい。まったく。てんのかみさまごときが口出すんじゃない、ひとの仕事に、とぷんぷん怒っておる。つまり、低調もへったくれもなくなってとたんにしゃきっとした。 映画とハドリアヌスの壁 2011年03月03日(木) おとといは「わたしを離さないで」をDVDでみた。それで摂食障害についてずっと考えていた。きのうは思い立って「ひとりで映画を深夜見に行く」というとっても勇敢な決断をして(前にも一度、つれあいとけんかしたときにやった)10時半からのThe Eagleをみにいった。ハドリアヌスの壁の向こう側というのをどんな風に描くのかを見たかった(ジェイミー・ベルがどんなふうに育ったかについても知りたかった)けど、なんだかぜんぜん満足いかない。ハドリアヌスの壁、こないだ(もう数年前になる)イギリスいったときにも見たかったが予定があわなかった。でもあちこちでローマの町跡をみた。そういえばトリーアでも見た。そして今は「テルマエロマエ」でその頃のローマ人がどんなお風呂に入っていたか熟知しておる。その上、「アーサー王伝説の起源」を読んで、その上「ヒストリエ」も読んで、想像がふくらんでおる。「The Eagle」で描かれた先住民の社会も、踊りも、風俗も、ほんとかなーと疑いの目で見てしまう。いってもせんないことだが、やはり英語しゃべるのである。ローマ人が。先住民たちの言語はいったい何だったのだろう。映画制作の人たちはど素人のあたしなんかが想像するのよりずっとよく練り調べてあるだろうと思うんだが。監督はドキュメンタリー出身なので、ドキュメンタリータッチを期待したが、2世紀のビクト人の生活はドキュメンタリーになるわけなかったのである。映画館はあたしのほかに若い男が一人。うら寂しいとはこのことだ(前につれあいとけんかしたときに見に行った「クレイジーハート」はあたしの他に二人)。こっちの文化全般かうちの文化か知らぬが、カップルがべつべつに映画いくなんてとんでもないってな雰囲気がある。ばかばかしい。映画はひとりで深夜見るもんだ。レイトショーは安くていいし、肴はあぶったいかでいいのである。熊本じゃいつもそうやって深夜ひとりでたのしくみにいっておるのだ。 「詩人の聲」 2011年03月02日(水) ものすごくものすごく楽しくてたまらない「詩人の聲」シリーズです。天童さんの「声を撃ち込めーー」という声にノセられてもう10回目。ってか35回くらいやってるような気がしていたがまだ10回目か。道は遠い。 学園ライブ 2011年03月02日(水) きのうは忙しかった。銀行から銀行へお金をあれこれと出し入れし(月初めにつき)飛行機のきっぷを何枚も買い、買い間違えたやつをキャンセルし、ホテルを取り、ホテルを検索し、こんどやる熊本文学隊のイベントをいろんなところに宣伝し、こんどの日本行きの予定を決め、本を注文し、facebookやtwitterに書き込み……。で、文学隊のつぎのイベントはこういう内容。どうぞよろしく。 オスカーと数独と「女ぎらい」のミソジニー 2011年03月01日(火) げ。もう3月。しかしきのうはいいことが3つ。まずクリスちゃんがオスカー♡ テレビというものがうちにあり、どうせカリフォルニアにいるんだからそれをつけて、生をみればよかったと後で気がついたが、ふだんテレビをつける習慣がないので後の祭りだった。でもネットでいっぱい見た。髭が長すぎる。これならばロシア正教ものかなんかやってほしい♡ それから難問をS子にメールして、ますにナンバーをつけて(それで同一の場所にいなくとも問題について話し合うことが可能になったのである)電話で教えてもらいつつ解くことができた。これは今まで遭遇したことのないような難問で、人生をはかなんでいたのであった。それから「ミソジニー」を知った。法然のことを考えつつ本棚を漁っていてふとU野さんの「女ぎらい」を手に取り(仏教における女人往生のことを考えていたのである)読み始めたらとまらなくなっていろんなことを考えた。思わずU野さんにちょーおもしろいっすとメールしたら、今くそ忙しいのにあんたの解説かいてるんじゃい、と、まあ表現は歪曲してあるが意味をとればそういうメールが返ってきて、そうなのだった、すっかり忘れていたのだが、「とげ抜き」が文庫になるので解説をちゃっかりU野さんに頼んでいたのだった。もうすぐ発売。←宣伝。しかし「ミソジニー」の概念はおもしろかった。いままでに考えてきたことやざる頭につきつなげられずにきたことや興味を持たずにきたことがしゅるるるるとつながって図式化された感じである。うちの娘たちの生きざまを肯定できた感じである。 テリトリー論 2011年02月28日(月) 姻戚のいた数日間、なんとなく不機嫌度があがってくすぶったみたいになっている自分に嫌気がさして、いろいろと検証してみたのだが、つまりそれは(前々からわかっていたように)自分のテリトリーに踏み込まれていることに対する反感にすぎないのだな。もっと流動的にものをとらえて、テリトリーがなんだ、いいじゃないか、貸し与えれば、いずれ返してくれるんだし、人に貸して減るもんじゃないし、と思えればいいのだが、なかなかそう思えないのは不徳の致すところである。貪も瞋も癡も、つまり各種の嫉妬も、みんなポイントはそこだ、と思ってるけどなかなか行動にはうつせないていたらく。テリトリーとは、つまり「あたしはあたしよ」ということなのであり、それについては名人と思っていたあたしだが、実はまだまだなのであった。ちなみに名曲スーダラ節でも、「わかっちゃいるけどやめられねー」の箇所はつらくて聞く気になれないが、「ほれスイスイスーダララッタ」の箇所は気が楽になって好きである。タケやニコを見ていると、自分のテリトリーによそものが踏み込むやいなや、何も躊躇もなく、がおがおがおがおと食ってかかっておる。潔い。むしろああいうものにわたしはなりたいのかも。 少佐とチケットと数寄和の朗読 2011年02月26日(土) おとといはついしめきりに追われ、H田に誘われ、twitterでエーベルバッハ少佐のフォローをしてしまってすごく楽しい会話をした(少佐と)。H田は今日も愛憎のたっぷりこもったやりとりをしておる。あたしはしめきりも終わったし、姻戚どもが来訪により(ったって籍入れてないのになー)それどころじゃないのであった。雨が降りそうで降らない。やることがいっぱいあって、どれから手をつけていいかわかんない。とりあえずこんどの日本行きのチケットを買った。3月は高いので泣いた(いつも泣いておる)。「詩人の聲」シリーズの天童大人監督から「こんどいつ帰る、比呂美!?」と檄文のようなメールがきたので、はいっ監督、19日ですっと返信したら、「じゃー数寄和だな」ということで、西荻数寄和に19日で予定を組んでくれた。いつもぎりぎりなのにありがとう、監督。この頃しょっちゅうやってるから、お客に飽きられるんじゃ?と監督にいったら、「だいじょうぶだっっ」とまた檄文みたいなメールが返ってきた。実は朗読、おもしろすぎてやめられないのである。しょっちゅうやってるから、毎回ちがう趣向を凝らす。前回の数寄和はエッセイ特集だった。その前の三宿スターポエッツは「ラニーニャ」特集だった。こんどは何を……と考えるだけで楽しいのである。一生朗読してられるような気がする。書くのとどっちが楽しいかと聞かれると、うー、そりゃまず書く方だけど。 ごらんあれが 2011年02月24日(木) 青森から帰ってきてずっと「津軽海峡冬景色」を歌っているのは、青森で「竜飛岬」という道路標識をみたからだ。なんとipodに入っておる。なぜかというと、数年前の暮れに、母に聞かせようと演歌をいろいろあつめたからだ。その年の紅白に出た石川さゆりは、中腰になってからだを揺らしながら「天城ごえ」を歌い上げ、あたしは迫力に驚きつつその歌のエロさにへきえきしたものだ(とうぜんそれもipodに入れた)。天城ごえはまだエロすぎて歌えないが、津軽海峡冬景色なら歌える(人のいないところで)。「わずかに、かすみ、みえる、だけ」というところが気に入らない。「帰ります」の「ます」も気に入らないが、なおしようがない。(詩人の業)「ごらんあれが」はすごく好き。「上野発の」もすごく好き。閉じた音が。しかしビールと同じように、そこで飲むとうまいが、環境や気候がかわったところで飲むとおいしくない。熊本で歌うのはまだマシだった(歌いたいがために、福岡へは車で行った)が、カリフォルニアで歌うとあんまりからからに晴れあがりすぎていて、おもしろくない。遅くなりましたが、青森県立美術館のみなさん、とくにI倉さん、青森近代文学館のみなさん、ほんとうにありがとうございました。そして福岡の箱崎水族館喫茶室、F枝さん、いつもながら、ほんとにありがとうございました。朗読に来てくださったみなさん、ほんとにほんとにありがとうございました。 カリフォルニア 2011年02月23日(水) ちょー忙しかった。あとでちゃんと書く(決意)。twitterはついついちょこちょこ書いてるのに、こっちは書いてなかった。スミマセン。例によって時差ボケでいつ起きてるのか寝てるのかわからない状態。いま、Dリンがこっちに帰ってきてるので明日の朝会う。ということは時差ボケに溺れてもいられないということだ。 ページ移動 / [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151]
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||