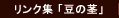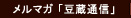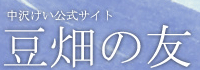 |
||||
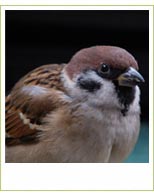 |
| タイトル一覧 |
| 最新の10件 |
| 伊藤比呂美Twitter |
| Twitter三匹の子豚リスト |
| ログ検索 |
| 年譜 |
| 著作リストへ |
| 管理者用 |
|
ブロークバックマウンテン 2008年05月20日(火) 時差ボケで早くおきるので、映画を見ている。おとといはキングコングを見た。今朝はブロークバックマウンテンだった。これは映画館で見て、たいへん感動したが、みんな訛ってるし、ぼそぼそいってるし、何にもことばがわからなかったので、無声映画みたいだったのである。きょうのには字幕がついていた。するとそこに会話があるのであった。それがまたイイのであった。朝っぱらから号泣した。いきたいなあ、ブロークバックマウンテン。 雨っ 2008年05月19日(月) 熊本ではめずらしくないのだろうが、カリフォルニア帰りとしては興奮してしまうのであった。バラが随所にいたるところ。うちの庭にさえ赤い木立のがさんざん花をつけている。ゼラニウムのピンクの色が、カリフォルニアのゼラニウムのピンクとちがう。朝から電話につぐ電話で忙しい。これが日本の生活というものだな。くせでつい「ハロー」と出ちゃうけど、相手はみんなべらべら日本語をしゃべる。すてき。「日本に帰ってきていいのは、どこにでもふつうに漫画がころがってることだ」と「とめはねっ」の縁くんのお父さんがいってたが、ほんとうに、心の底から、それには同感。 文学隊 2008年05月19日(月) ちょうどみんなが佐木隆三講演会にあつまったので、そのあとはじめて役員たちが顔をつきあわせて謀議をした。いいかげんな組織なので、まだ重要な役員たち、幹部たちが、何人も洩れていたのは、いうまでもない(さきに連絡してきちんと招集かけておけばよかったと後悔している)。マジで子ども期の「ひみつけっしゃ」や「ひみつきち」遊びを思い出してたいへんおもしろかった。みんな「遊び」とわかっていてもものすごく真剣であった。 熊本 2008年05月16日(金) ぼろぼろ。 ごあんない 2008年05月13日(火) 6月8日(日)17:00から一時間。 かくのを忘れていた 2008年05月12日(月) 何をやっていたんだろう。 頭 2008年05月09日(金) きのうはDンとGルといっしょに、ソーカ大学まで、Gルの展覧会を見に行った。このごろGルは人の頭に凝っていて、大きいのや小さいのや、人の頭のかたちをしたものが、上に下に、ここにあそこに、ギャラリーいっぱいにうち並んでいた。「首実検」とか「おあん物語」とか「小塚原」とか「山形のみいら」とか「市中引き回しの上打ち首獄門」とか「熊本市現代美術館の生き人形展」とか、さんざん思い出したが、Gルに語ったのはそのごく一部であった。 次郎物語 2008年05月08日(木) きのうは一日、必死で「次郎物語」を読んでしまった。もういっこもういっことやめられなくなって、第五部まで。青空文庫に入ってるのである。青空文庫は、やはりこういう境遇なので愛用させていただいている。ふりがながカッコつきでついてるのがうっとうしく、Wordにうつして、縦書きにして(でないと、読んだ気がしない昔の人間なのさ)カッコつきのふりがなを取ったり、旧かなを新かなに直したり(子どもたちに読ませたいとき‥‥うちのや日本人学校のや)しているうちに、本で読んでるより熟読できる。 雨 2008年05月07日(水) この時期に雨というのはそうとうめずらしい。これでピンクの花がもっと咲くかもしれない。隣の荒れ地にピンクの花が、今年はじめて咲いたのが先々週の金曜日。いまはあっちにもこっちにも点々とある。これが咲くと春もおわりだ。雨の多かった年はピンクの花がよく咲いた。少なかった年は咲かなかった。どんな花かというと、ホンモノの花というよりは子どもが絵に描いたような花、いかにも「花」でございというような花。サクラ形の五片の花びらに、色はどピンク、まん中はほんのり白く、めしべとおしべは黄色っぽい。茎は10センチほどで、葉はあるかなきか。まるで春先のクロッカスのように、地面からにゅうと咲く。晩春の荒れ地に散り咲く。 Hとフクシャ 2008年05月06日(火) Hの夢をみた。これで3回目だ。 ページ移動 / [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151]
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||