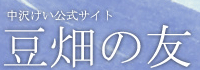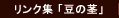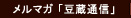|
|
 |
 |
| |
|
| |
渋谷で占い師に捕まえられて
2005年08月24日(水)
渋谷で占い師のおばさん?に突然捕まえれました。なんでもカイカソウ(開花相か?)てのが出てて、すごくいい運勢がきているんですって?ほんまかいな?で、なぜかこのおばさんは迫力があって、ずっと離してくれないんです。
迫力があるって言っても、ほっそりとした少女くさいおばさんなんてすがね。いきなり人ごみの中から手が出てきて「ああ、顔にカイカソウが出ています。手相を見せて下さい」といわれたときには、もう掌を掴まれてました。で、まじまじと掌を見ながら、「ほら、この線が」と指差し「今、お幾つですか?」と聞く、その人の手首には水晶のブレスレッドがありました。
ああ、5時までにはどうしても行かなくちゃいけないところがあるのに、なぜか、おばさんは私の手相に夢中で、こっちの言うことなどぜんぜん聞いていないのです。そんなに珍しい手相だったのかしら?
月夜二題
2005年08月22日(月)
8月20日は旧暦の7月の十五夜でした。大潮です。金沢八景でお月見をしてきました。翌日21日は十六夜の月を三浦海岸で見てきました。
夏は海水の温度があがって膨張していますから、大潮の時の潮の満ち引きも大きくなります。金沢八景と数えられる八つの景色のうちのひとつに「瀬戸の秋月」があります。中秋の名月の晩には、瀬戸から見える野島の真上に月が上がるのですが、今月はまだやや東側に月が昇りました。ちょうど潮が満ちてまんまんとたたえられた平潟湾の上に昇った月を見てきました。周囲はマンションになっても、水の上には明るい月明りが落ちていました。
翌日は三浦海岸の月。赤い月が昇り、中天を目指しはじめると、海岸の潮をどんどんと引いてゆきます。海の写った月の光は、やがて潮が引いた海岸の濡れた砂浜も照らし始めます。黒い砂が金色に光るのです。デジカメでもこれは写せません。月は空高く登るほど、少しずつ白くなって行きました。
東洋ではこのうえなく美しいとする満月ですが、西洋ではこれを見ると狼になっちゃったりするですから、人間のものの感じ方って奇妙です。昔の人はほかに見るものがなかったから、お月様なんかをしげしげ見ていたという人もありますが、人間が作ったどんな仕掛けよりもきれいな月でした。
桜と紅葉のある土地
2005年08月20日(土)
去年から土地を探していました。外房に桜の樹と紅葉の樹のある土地を見つけました。裏は小さな崖で、雑木林になっています。椿、マテバシイなどが生えていて、どうもたぬきが通り道らしい獣道もありました。表は一面に広がる水田です。ほんのりと黄色く色づいていました。耕地整理と農地改良が済んでいるので、整然と四角い田んぼがならんでいます。
広い田んぼの端っこに蹲っているような感じの土地です。ここに小さな家を建てようと思っています。房総の民家をもとにした間取りの家を考えています。
博多のはさみ
2005年08月19日(金)

家の中で写真をとるときにはライティングにもっと気を使わなくちゃと思っています。ピンボケですが、「楽隊のうさぎ」の取材の時に見つけた博多のはさみです。飴切りばさみというのだと聞きました。ほんとうに飴を切るはさみはもっと大きなものだそうです。切れ味がよくってほかのはさみだと詰まらないくらいです。もう6年も使っているのにぜんぜん切れ味は衰えません。
名誉という火傷
2005年08月18日(木)
名誉という言葉だけで、とたんに蔑んだような態度をとる人々がいます。「名誉なんてどうでもいい」と言います。60代以上の年齢の人が多いような気がしています。よほど「名誉」というものに手痛い火傷を負わされた経験があるような、苛烈な対応を見せるときもあります。敗戦というものは、人のこころに「名誉」に対する拒絶反応を植えつけたのかもしれません。
もうひとつ付け加えれば国民皆兵の国の敗戦は、名誉というものを、何か触れてはならない奇妙なものに変えたのではないでしょうか。
郵政民営化がこれほどこじれて感情的な反応を引き起こすのも、靖国問題が激しい感情を呼び起こすのも、その根底には名誉に対する考え方感じ方が横たっていると思います。しかし、この60年間の間、名誉というもにについて、ちゃんと論じてきたことがなかったというのは言いすぎでしょうか?拒絶反応に近いような様相で語られる名誉か、もしくは時代の変化には無頓着な旧来型の名誉かのいづれにしかないところに、不幸があるのではないのでしょうか。
執念と怨念
2005年08月17日(水)
まだ公示されてない衆議院選挙ですが、自民党の候補者選びのためにかなり報道されています。郵政民営化に反対した候補のたつ選挙区へ賛成の候補を対抗馬として立てることをメディアは「刺客」と呼んでいます。
最初に「刺客」という言葉が飛び出したのは小林興起候補の選挙区に小池ゆり子環境大臣が立ったときでした。これが我が家の隣の選挙区。と言っても我が家の選挙区の端っこなので、自分の選挙区の候補はあまり姿を現さないのです。隣の選挙区の候補の方がよく回ってくるのは毎度のこと。メディアは対立候補をみんな「刺客」と呼んでいますが、表現に工夫をして欲しいものです。
小泉首相の郵政民営化への執念を感じさせる候補者選びですが、一方の反対した議員の言動には、とくに亀井静香候補は、怨念を感じる言動が目立ちます。この選挙は執念と怨念の戦いというところでしょうか。世論調査などでは首相側のやりすぎの首をかしげている人もかなりいるようです。対立候補を立てるのは、いきさつから言って仕方がないところがあるのでしょうが、森前首相に干からびたチーズを出して、あとでフランス高級チーズだとバラすなんてのは、いささか、執念をとおり越した妄念なのではないでしょうか。
選挙は次の衆議院選挙だけで終わるわけではありません。首相の執念は郵政民営化法案の成立とともに、あるいは首相がその地位を降りることによって消えるでしょうけれども、怨念のほうは、これは形を変えて残って行くことでしょう。消えたと思ってもまた現れるのが幽霊の怖いところですが、怨念という人間の感情もそれと同じようなところがあります。
まくわうり見つけた
2005年08月16日(火)

知り合いと、甘いメロンじゃなくて昔のまくわうりが食べたいねと話してました。今頃、ソウルへ行くと黄色いまくわうりを沢山売ってます。川水とか氷水で冷やして食べると、ほんのりした甘みがおいしいのです。さっぱりと軽い甘みです。
まくわうり見つけました。ソウルで見かける小ぶりな物ではなくてどちらかと言うとキンショウメロンに近いのですが、それでもまくわうりの味がします。見つけた場所は京都に錦市場を西の方角へ抜けたあたりの小さな八百屋さん。同じ八百屋さんで九条ねぎも買いました。九条ねぎのほうは写真にとらないうちに食べてしまいました。
そうそうねぎを買って歩いていたら、いろんな人に道を聞かれました。新幹線でねぎを買いにくる人はいないから、道を知ってそうに思われたみたいです。
終戦記念日
2005年08月15日(月)
私の母は小学校四年生で終戦を迎えました。神奈川県の秦野に学童疎開をしていたそうです。5月の横浜大空襲のあと山形への疎開が決まっていたのですが、ソビエトが参戦したために見合わせになったと言ってました。もし山形へ移動したあとに終戦だったら、しばらくは、交通事情が悪くて家には戻れなかっただろうと話していました。
学童疎開の引率をしたのは20歳そこそこの若い先生で、あとから考えてみると、あんなに若かったのによく大勢の子どもを預かることができたものだと感心したそうです。終戦の日は、整列してラジオを聴いていたそうです。で、6年生は泣き出したので、なにをそんなにめそめそしているんだろうと思ったという話でした。
ラジオの音が悪いのと言葉が難しいので終戦の勅諭を本土決戦玉砕の放送と勘違いしていたそうです。
田んぼの中を歩いていた教頭先生がアメリカ軍の機銃掃射で殺された話とか、横浜大空襲のあと、ひそかに横浜まで歩いて戻り、家族の安否を確かめた話をしていました。母の家族も家も無事だったのですが、同級生の中には、家も家族も無くなっていた子がいたそうです。
畑のにんじんがおいしかったのと、白い絵の具を食べると甘かったと、食べ物を送ってもらうのは禁止されたいたので、代わりに歯磨き粉を送ってもらって舐めていたのと、そういう食べ物の話が多かったのを覚えています。「戦争はひもじい」という話をしたのは母ばかりではありませんでした。いつのまにか「戦争はひもじい」という話は聞かなくなりました。私が子どもの時でも、テレビドラマの戦争の場面では、かならず、誰かが瓶にお米を入れて棒で突いていました。脱穀をしているのです。そういう脱穀の場面がテレビ・ドラマから消えて久しくなりました。
戦後の話になりますが、中学校の時に同級生がアメリカ兵相手のパンパンをしていた話とか、聞いてはいてもなんとなく当事者ではない人間には書きづらい話もたくさん聞いています。戦争を語り継ぐと言っても、語られただけで、消えて行ってしまう話もたくさんあるのだなと思います。それに風化という言葉がしきりに使われた時期がありますが、風化しなければ見詰めることができない真実もあるように思われるのですが。
仕事をしないで
2005年08月14日(日)
仕事をしないでテレビを見ているなんて、叱られそうですが、この一週間で、郵政民営化は結局、郵政の、とりわけ金融、保険部門の解体、縮小であり、ひいては公共投資中心の金融システムから、民間投資中心の金融システムへの転換の糸口だということが公然と議論されるようになってきました。
明日は終戦記念日ですが、靖国問題がクローズアップされていて、昨晩と今夜とNHKスペシャルを見ていました。これも戦死者の名誉と戦没者の追悼という二つの事柄を整理する必要があることがはっきりしてきたという点で、これまで公然と語られなかったことが、議論の俎上に乗ってきたとようです。
議論というのは、けんかではなくて言葉を生み出し、知恵を生み出し、ひいては感じ方というものを作って行くものだという眼で眺めているとこの数日はかなりおもしろい展開をしています。まるで淀んでいた川が流れ出すように、淵から瀬に流れが差し掛かるように、言葉が生まれて行く瞬間を眺めている感じです。
物語というのは、こうした議論の生み出した感受性の向こう側に存在しているものなのでしょう。
ボイス・レコーダー
2005年08月13日(土)
昨晩、TBSで放送された「ボイス・レコーダー」に引きこまれてとうとう最後まで見てしまいました。日航ジャンボ機墜落事故から二十年です。
最初は再現ドラマという手法に違和感がありました。例えば機長がフライトに出るシーンは現在の羽田で撮影されていますが、二十年前は勿論、ビッグ・ウィングではありません。しかし、だんだん、二十年という歳月の表現の仕方に興味を持ちました。
日航機の事故の時、その第一報を聞いたときの自分の動作をよく覚えています。千葉の館山の家の台所にいました。台所の勝手口の扉を開けたときに、日航機が行方不明になっている第一報のニュースがテレビから流れてきました。なぜ、そんな動作を覚えているのか自分でも解りません。
その歳の一月に母がなくなって、新盆なので、子どもたちと連れて、館山の家に戻ったばかりでした。人のいない家は荒れやすくて、数日を過ごすための準備にはけっこう手間がかかるものです。締め切った家の扉を空けてすぐのニュースでした。
ところで二十年という歳月ですが、例えば戦争中に集団疎開をしていた私の母にとって終戦から20年と言えば昭和40年がそれにあたります。私は幼稚園の年長組でした。八月になると、集団疎開を撮影した映像などが紹介されると、母は食い入るように画面を見てました。昨晩のTBSの番組を見ながら、そうか、二十年というのはこんな感触なんだなあと、自分の身体で、改めて歳月の質量を測っていました。
20年前と言えばテレビのワイド・ショーが盛んになってゆく時期で、日航機事故もそのきっかけのひとつになったのです。「ボイス・レコーダー」はそのワイド・ショーが生み出した再現ドラマとか、現場からの中継映像などの技巧と、ドキメンタリーの手法を慎重に組み合わせながら作られた番組でした。テレビ局がこの二十年間になにをしてきたかを製作技法で語っているように見えたのも興味深いです。
↑前のページ / ↓次のページ
|
| |
|
|
|
|
| |
|
| |
|