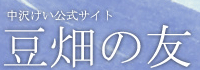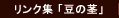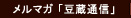|
|
 |
 |
| |
|
| |
終わって初めて解ること
2005年10月21日(金)
フランス自然主義を矮小化して受容した日本の自然主義ですが、これが私小説を生み出します。私小説にはいろいろな議論があるのですが、結局のところ、近代的な文章で語られる叙情を生み出すという役割を大きく果たしたのではないでしょうか?
鴎外は「ウィタセクスアリス」を書いた翌年に「青年」を書いています。このニ作品を読むと、鴎外は自然主義が科学主義的態度で社会を観察して書くという自然主義の方法を理解していたようです。で、その限界にも気付いていて、「青年」以降は歴史小説を書くようになります。
ところが、フランス自然主義文学を矮小化して捉えた日本の近代文学は告白と描写を組み合わせることによって、近代的叙情を切り開いて行きます。これは日本の発明でした。たぶんそういいきってかまわないと思います。言語改良運動は、どうしたって旧来の叙情を殺してしまうものですが、観察という方法論は告白と言う主観表現を呼び込むことによって、叙情の再構築を可能にしたと言えるでしょう。
近代文学は終わったというのは90年代に入ってからの文芸評論家の意見でした。気短な批評家は文学さえ終わってしまったかのような極論さえ唱えましたが、終わって初めて理解できることというものがあると思います。今、鴎外の「青年」を読むと、近代文学の終焉の時の諸相が早くも鴎外が予想するところになっているのに驚かされます。が、その鴎外の自然主義が私小説を生み、それが近代の散文的叙情を構築するという展開は予想できなかったようです。韻文あるいは韻は踏んでいたくても詩的な叙情についてはこれとは別な展開があったようですが、そのあたりは詳しくないので、今度、詩人の城戸朱理さんにあったら聞いてみたいと思います。
そうそう城戸朱理さんのブログを見つけました。骨董市の買い物日記がおもしろいです。
ゾラ・バルザック・フローベール
2005年10月20日(木)
文芸評論家の秋山駿さんが「歳をとると中学生頃までに読んだものをくりかえし読むようになるんだ」とお話してたことがあります。秋山さんはドストエフスキーでした。ドストエフスキーは大事に思っている読者が大勢いるようで、うちの娘の「ガンバッテ」読んでいました。私の場合はドストエフスキーはやや苦手で、ロシア文学ならチェーホフでした。
若いときってよくもわるくも「本気」で読んでしまうのですね。その「本気」が歳をとってからくりかえし読む原動力になると言うことがこの頃わかってきました。
で、鴎外の「青年」を読んでいると、やはり自分が馴染んだのはゾラであり、バルザックであり、フローベールだったんだなあと思いました。そんなに研究したというわけではありません。大人の本が読めるようになったばかりの頃に、なじみを感じて読んだのがそういうフランスの自然主義作家の作品だったのです。それが日本文学にも影響を与えて私小説を生んで行く道筋が、目に見えるような感じがこの頃してきました。高い丘の上に上って歩いてきた道を眺めているような気分です。
森鴎外の「青年」
2005年10月19日(水)
森鴎外の「青年」を読んでいます。以前、読んだ時にはこの小説が日本の自然主義批判だとはまった気付ませんでした。が、読み返してみると、この小説が書かれた当時のフランスの様子なども視野に入れた自然主義批判なのです。フランスではフローベールもバルザックもゾラも登場してしまって自然主義はいささかの行き詰まりを見せているのに、日本では盛んに自然主義を唱えているという状況の中で話はすすんで行きます。そういう視点で読み返すとおもしろことがたくさんあります。
日本の自然主義は「観察して写生する」つまり描写という方法を文学に根付かせました。そこから私小説も生まれてくるのです。私小説は近代の叙情を生み出す上で大きな役割を果たすことになったというのが、私の考えです。鴎外はこうした発展は予想してなかった様子なのも「青年」の読みどころです。私小説が生み出した叙情が形式を備えるのは1950年代なのではないかという仮説をたててます。そして、その叙情の形が大きく崩れて行くのが1980年代だとするという仮説を立ててみています。こうした仮説を考えるうえで、鴎外の「青年」には示唆的なものがたくさんあります。
外堀土手の枳殻の実
2005年10月18日(火)

法政大学の前にある外堀の土手はいつ歩いても気持ちが良い道です。この土手にはいろいろな樹が茂っています。枳殻の木も何本も生えています。そのなかで毎年黄色い実をつけるのは飯田橋寄りの一叢です。たぶん日当たりの関係なのではないかと思うのですが、この一叢だけはたわわな実りがあるのに、ほかの繁みはとげとげの枳殻の木で、ほとんど実はついていません。
枳殻の実がたくさん生っていたでしょうと言っても気がついている人はほとんどいません。あら、そう?っていう返事が帰ってくるだけです。誰も見ていなくても枳殻は毎年ちゃんと実をつけています。
先生こんにちは
2005年10月17日(月)

盛岡に行く前に、法政大学の前の外堀の土手の上でちょっと休息中の勝又先生に出会いました。カメラを取り出すと「おや、また、なんでそんなものを持っているの。ああ旅行なの」と、おっしゃっている間にパチリ。こういう場所で出会うと文芸評論家の勝又浩氏というよりも「先生、こんにちは」と言いたくなります。「旅行」と言われても、盛岡に行って帰って合計18時間の移動なので「なんだかなあ」という感じでした。
こんなお天気の良い秋の日は、新幹線や飛行機で飛び回ったり、空調のあるビルの中で会議や講義をするよりも、土手の上でおしゃべりをしているほうが人生にとって有意義な気がするので、困ったものです。
最低気温9度・盛岡
2005年10月16日(日)
13日夜、新幹線で盛岡に行きました。翌日、盛岡市内で講演をして、その日に夕方には法政大学で講義をしているというとんぼ返りの日程でした。
盛岡の最低気温は9度。最高気温32度の那覇から比べるとその差は23度。こんな温度差に堪えられるかしら?とやや不安だったのですが、今のところ風邪も引いていないようです。なんだか「ばかは風邪をひかない」という声が聞こえてくるようですが。
盛岡でも山では紅葉が始まっているということですが、平地はまだ赤く色づいている樹木は数えるほどしかありませんでした。今年は全国的に紅葉の時期が遅いようです。
ズームのおけいこ
2005年10月15日(土)

近づいてくるゆいレールの車両はズームで撮影しました。3倍ズーム機能がついているカメラを持っているのですが、これまでどうやってズームを使ったらいいのか解らなかったのです。どうも機械のマニュアルが苦手で、使いながら、少しずつ必要なところを読んで行くというやり方で慣れて行くしかないような付き合い方をしています。今日の赤い花は、ゆいレールのしたの往来に咲いていた花です。
沖縄はまだ真夏でした。
ゆいレール
2005年10月14日(金)

沖縄には戦前、軽便鉄道があったそうです。戦後は鉄道はまったくなく、自動車社会でした。その沖縄に那覇空港から首里までモノレールが走りました。ゆいレールと呼んでいます。空港から県庁前を通り、牧志から新都心のおもろまちを抜け、終点は首里です。おととしから
開業しています。これに乗れば空港から首里まで那覇周辺の主要な観光地を歩くことができます。なかなか便利で快適。写真は県庁前駅から空港方面を撮影しました。こうしてみると沖縄も変わったなあと感じます。
気温32度に戸惑う。
2005年10月13日(木)
昨日、一昨日の那覇の最高気温は32度でした。一応出かけるまえに、ネットで最高気温と最低気温は調べていたのですが、なんだかぴんときません。那覇に到着したとたんにストッキングに革靴を履いていることが愚かしいと気付きました。それに帽子もサングラスも持参していませんでした。
ううん。数字で理解しているということと、実際は「ああ、帽子をかぶらなっくちゃ」とか「サングラスがほしいなあ」と思うのはなにか、違います。もともとあまり用心深いほうではないので、いつもこの違いに面食らって、なんて学習効果がないんだと我ながら呆れています。でも空港にいる人っておおかれ少なかれ、どこかちぐはぐなかっこうをしていますね。用心が足りないのは私ばかりではないかって、なんとなく、安心。
沖縄からただいま。
2005年10月12日(水)
沖縄の那覇を21時に出発する飛行機で東京に帰ってきました。で、羽田到着は11時30分。キャビン・アテンダントの女性が飛行機の扉をいかにも重そうに開けて、扉の向こう側にいた地上整備員の人に「こんばんは」ときれいな声で言っていたのが印象的でした。そばらく「こんばんは」って挨拶を聞いていなかったような気がしました。
那覇は最高気温32度。那覇祭りの大綱引きが終わったばかりだそうです。最低気温のほうもまだ26度ありました。夜は幾らか涼しくなったと、沖縄タイムスの友利さんは言ってましたが、東京から飛行機で飛んだ感覚からすると、まだ真夏です。ああ、帽子とサングラスを持ってくるんだったなあと後悔することしきりでした。
カタアメ(方雨もしくは片雨でしょうか?)という言葉を教えてもらいました。空のかなたは晴れているのに、一部分だけ降る雨のことをカタアメというのだそうです。那覇ではここのところ、毎日、カタアメが降っているとのことでした。
↑前のページ / ↓次のページ
|
| |
|
|
|
|
| |
|
| |
|