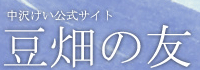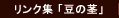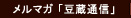|
|
 |
 |
| |
|
| |
文学フリマお手伝いお礼
2005年11月21日(月)
文学フリマでお手伝いいただいた梅沢先生、大西さん名古屋君、豆蔵さん、未兎さん、どうもありがとうございました。おかげさまでたくさん本を買ってもらうことができました。お礼申し上げます。
(連絡事項)法政大学のゼミ生の皆さん。ゼミ誌は人気で完売しました。
秋葉原の文学フリマ
2005年11月21日(月)
土曜日に恒例の日大院生の諸君とフィールドワークに行ってきました。夏休みに挙行の予定だったのですが、台風の接近で延期になってました。今回は日が短くなっているので皇居周辺を街並みの変化に注意しながら歩きました。
で、聖橋の上から秋葉原を眺めてみると、煌々とした巨大ビルが三っつも見えました。明るいビルで、すっきりとした色合いの光です。電気街のネオンサインで色とりどりに輝いていた昔とは違います。神田明神の境内からも秋葉原の巨大ビルを眺めることができました。
以前、文学フリマの事務局長の望月君に秋葉原を案内してもらったことがありました。やはり日大のフィールドワークでしたが、考えてみるとあれが古い秋葉原の見納めでした。戦後の街。秋葉原はそう行ってもいいと思います。津島佑子さんの話だと昭和20年代はまだ野原だったということです。東京の東側にはところどころに火伏せのための野原があったのです。そこに電気屋さんができてあれよあれよというまに大きな電気街に育ったのは昭和30年代だったとのことでした。
秋葉原の再開発は渋谷のビットバレーよりも実際的な要求に沿っているように見えます。で、日曜日にその秋葉原の中小企業振興会館で行われた文学フリマに行ってきました。出店者です。一言で言って想像以上の賑わいでした。なにしろ、開場前の行列が凄かった。詳しくはトピックスで。豆蔵さんがフリマの様子を写真にとってくれているはずです。
文学フリマ
2005年11月19日(土)
11月20日に秋葉原で行われる文学フリマに出店します。販売するのはこれまでの文学者キャラバンの資料集(全部がそろっているわけではありませんが、かなりの種類があります。)私のゼミの雑誌。「法政文芸 創刊号」「私小説研究」「現代文学研究」などの研究誌です。
詳しくは文学フリマのホームページをご覧下さい。
汁なしワンタン麺
2005年11月19日(土)

台湾はおいしいという宣伝文句をよく耳にしますが、ほんとうにおいしかったです。一番、おいしくなかったのは(まずかったわけではないのですが)大きな料理屋さんで食べた宴会料理。あとで聞いたら、そのお料理がいちばん高価だったそうです。写真は汁なしのワンタン麺。お皿のふちに載っているのがワンタンです。で、このおそばがとてもおいしかったのです。ワンタンも茹でただけでしたが、しっかりした味で、具もいっぱい入っていて、こういう食べ方もいいなあと思いました。
お堀の夕焼け小焼け
2005年11月18日(金)
しばらくは寒い日が続くようです。なんだか、寒い日がすきです。ずっと暑いよりも寒いほうがほっとします。ちょっとくたびれています。10月11月とあっちこっち駆けずり回ってましたから。
娘が自動車を運転して出かけました。夏休みに免許をとってから初めてのお出かけ!ううん。なぜかおしめをした赤ちゃんがハンドルを握ってにっこり笑っている姿が浮かんでしまいます。
夜は帝国ホテルでパーティの予定でしたが、ハンドルを握っているベビーの映像がしきりに瞼に浮かんで、パーティには出かけずに家に帰ってきてしまいました。ああ、道路って恐ろしいところだったのね。昔の赤ちゃんがみんなで運転しているなんて。そんな感じのする一日でした。
市谷から飯田橋へかけてのお堀端から眺める新宿方面の夕焼けは、この季節がいちばん冴え冴えとしています。気の早いデパートや商店街がそろそろクリスマスデコレーションになり始めました。
ベランダのブーゲンビリア
2005年11月16日(水)

台北の植物は沖縄とよく似ています。隣り合った島だから当たり前といえば当たり前なのですが、台北のほうがずっと元気良く育っています。台北の裏町のベランダでブーゲンビリアがたくさん花をつけていました。写真はありませんが、台東の街ではジャスミンの花の香りが漂うとおりがありました。お茶の匂いではなくて生のジャスミンの香りです。
寒い朝
2005年11月15日(火)
今朝の東京は気温12度です。北海道や東北では雪が降っているそうです。12月くらいの気温ということで寒い朝です。朝方、地震がありました。20センチから50センチの津波が東北から関東沿岸に到達しています。紀宮さんの結婚式です。
地震とは関係ないと言えばそうなんですが、この宮様が御降嫁になろうとすると、日本列島がくらくらと揺れるような気がします。ひょっとすると女性天皇と内親王による宮家の創設が検討されていますから、御降嫁になるのは紀宮さまが最後ということになるのかもしれません。旧弊な女官なら「海山がお嘆きになっている」なんて言うのでしょうか?偶然の符合なのですけど。
茅野裕城子さんの台湾みやげ
2005年11月13日(日)

写真は台湾の少数民族タオ族の船の模型と台湾のセブンイレブンで買物をするたびにくれたデズニーランドのフィギュアです。茅野裕城子さんがおうちでお留守番をしていた小学生のお子さんへの台湾土産の写真を送ってくれました。
茅野さんのお子さんは、白雪姫が皆に二列に並んで乗船を待つようにしている場面を作ったところをパチリと撮影して送ってくれました。白雪姫がほかのみんなに指示を出しているところがとってもかわいいです。台湾にはたくさんのセブンイレブンや全家便利店(ファミリーマート)があり、キャラバンのメンバーは毎晩、何かしら買物に行っていました。
木枯らし一番が吹きました
2005年11月12日(土)
東京に木枯らし一番が吹きました。例年よりも一日早い冬の到来だそうです。東京はすっかり晩秋の気配です。
(連絡事項)東呉大学院生の皆さんへ
うちの娘と豆蔵さんがのまネコの小さいのをゲットしてきました。さすが豆蔵さん。一発のゲットだったそうです。東呉大学の院生の皆さんにお送りするノマねこがこれでできました。明日、荷造りをして明後日もしくは火曜日には郵便でお届けするようにします。
銀の波
2005年11月11日(金)
台北から台東までは列車で行きました。華蓮から先は単線の旅です。台湾の東側は中央山脈がすとんと海に落ちるような地形をしています。列車は華蓮まで、海岸沿いを走ります。きめの細かい砂で埋め尽くされた海岸が無防備に太平洋に開いていました。
華蓮あたりから太平洋と中央山脈の間に走っている襞のような山地に入ります。3000メートル級の山々が並ぶ中央山脈の山の稜線が弧を描いて、石ころだらけの川原が広がる谷に落ちています。川は枯れ川か、もしくは石だらけの川原の中に細い流れがあるかでした。日本の川で言うと大井川に似ていました。ひとたび雨が降れば、山の斜面を駆け下りた水が川幅いっぱいにごうごうと流れる様子が目に浮かぶような川原でした。
そうした川にも穏やかな背もある様子で葦がいっぱい茂っていました。銀色に輝く穂が一面に広がっていました。葦の穂はさわさわと、高い山から下りてくる穏やかな風にそよぎながら、日差しをいっぱいに浴びていました。銀色の波でした。枯れ川の中にたつさざなみでした。
台北から台東まで行きは4時間半、帰途は6時間の列車の旅でしたが、その景色が変化に富んでいたので飽きることなく凄くことができました。台湾でも新幹線の試運転に成功したそうです。東シナ海側の台中から高雄にかけては平野部ですからもうすぐ新幹線も走るでしょうけれども、太平洋側はまだしばらくのんびりとした列車の旅ができそうです。
(連絡事項)東呉大学院生のみなさんへ、うちの娘が今日、のまネコの捕獲にでかけて行きました。しかし、もうのまネコはいないかもしれません。流行のはやり廃りが早いのでUFOキャッチャーのぬいぐるみもどんどん変わって行くそうです。期待しないで待ってください。
↑前のページ / ↓次のページ
|
| |
|
|
|
|
| |
|
| |
|