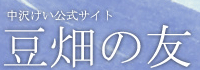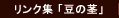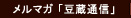|
|
 |
 |
| |
|
| |
超漢字 串刺辞書
2005年12月17日(土)
東京国際フォーラムで開かれていたトロン・ショーに行ってきました。年々歳々に賑やかになってます。参加する企業も増えて、今年は国際フォーラムの地下全体を使った展示になってました。
「超漢字」の串刺し辞書が完成したので、それを見せてもらいました。単語を検索する場合、複数の辞書を同時に検索することが出来るというものです。日本語の国語辞典ばかりではなくて、英和、仏和、伊和など外国語の辞書を検索することも可能になってました。
言葉の意味というのは、A=Bというようなものではありません。Aという言葉はAという意味の集合で、その集合のある部分がBという意味の集合と一致しているのです。そのには自然とずれが出来ています。串刺し辞書を活用すると、そうした意味の範囲の広がりや言葉がずれが自然とわかります。辞書に串刺しにすることによって「類義語辞典」のような役割も果たすようになってました。
会場には作家の吉目木晴彦さん、歌人の大谷さんもいらっしゃっていて、串刺し辞書について、楽しくお話させてもらいました。
すっかり冬景色
2005年12月15日(木)
寒くなりました。コートを引っ張り出して着ています。暖かいとほっとします。
昨日は昼に家を出るまで、国会中継を見ていました。で、帰りにタクシーの運転手さんと話したのですが、姉歯元建築士はそんなに嘘はついていないだろうという感じですし、木村建設の社長は実務はそれほど知らなかったのだろうという感想のお客さんが結構いましたよという話でした。
出勤した大学でのほかの先生のこの件で雑談をしたのですが、60代50代の全共闘世代がおとなしい40代をこき使った感じがするという感想でした。ところがその40代は気弱で真面目なおかげで、あれもこれもばれたというところでしょうか?「なんだかなあ」とため息。
それにしてもこの事件、よく解らないのはなぜ構造計算書を偽造したのかという点です。建築工事の手抜きはよくある話で、地震のたびに手抜き工事が問題になるのは今に始まったことではなくて、古くは江戸時代、いやもっと先まで遡るかもしれません。で、手抜き工事をすればいいものを、ちゃんと構造計算書を作ったところが奇妙です。なんでわざわざこんなめんどくさいことをしたのでしょうか?今朝の新聞を読んでもその謎は解けませんでした。
それにしても冬景色です。大企業のボーナス支給額は過去最高なんていう文字も新聞のすみっこで踊ってました。
つくもさんの念力
2005年12月14日(水)
言われるまで気付かなかったんですが、つくもさん(リンク参照)とお目にかかったり、つくもさんが我が家に起こしになったりするとなぜかウィンドウズの調子がへんになっちゃうんです。30秒で電源が落ちるウィルスに感染するとか、作業中に画面がまっくらになるけれども、ポインターは生きていて、手探り(あてづっぽうか?)でクリックするとなんかと使えたりといろいろ怪奇現象がおきるのです。これってつくもさんの念力なのかしら?
で、先日のサーバーが飛んじゃった時ですが、あれはつくもさんの結婚式に私もお呼ばれしてました。で、結婚式に出席した人の中にもこのHPを見ていてくれる人がいて「今朝からアクセスできなくなってますよ」って教えてくれました。ううん。こうなるとサーヤの結婚には地震や津波がくるのと同じくらいの不思議です。これも念力の一種かしら?つくもさん自身に指摘されるまで気がつかなかったんですけど。こういう念力もあるのかなあって、びっくりしてます。
生ハムと洋ナシのサラダ
2005年12月13日(火)
洋ナシの季節はそろそろ終わりですが、洋ナシと生ハムのサラダのレシピを覚えました。ころころに切った洋ナシにルコラ、それにパルメルザンチーズを薄くそいだものをかさねてバルサミコ酢をかけます。これだけ。とってもおいしい組み合わせです。覚えたての組み合わせです。
生ハムといえば果物との相性がいいのですが、なんでも以前の日本の法律ではハムは加熱しなければいけないという規定があって市販できなかったそうです。でもホテルや高級レストランの前菜には生ハムがありました。あれはきっと縛られる法律が違ったのでしょう。で、前菜といえば生ハムのメロン添えというのが定番という時代がありました。
イタリヤ産の生ハムを売っている店をデパートで見つけた時はすごく嬉しかったのですが、お値段のほうも目の玉が飛び出るくらい高価でした。これは今でもあまり変わりがありません。そんなに高い生ハムを買わなくても日本産のまあまあの値段のものが今は出回るようになりました。
生ハムと洋ナシあるいは桃という組み合わせは今までも楽しんでいたのですが、+ルコラ+パルメルザンチーズ+バルサミコでこんなに見た目に美しく、複雑で良い香りのするお料理になるということを発見しました。クリスマスには温野菜のサラダにするか?生ハムと洋ナシのサラダにするか?考えています。
「シュラクサイの誘惑」と「ガープの世界」
2005年12月12日(月)
ここ数日、小説を読むようなおもしろさでマーク・リラの「シュラクサイの誘惑」(日本経済評論社刊)を読んでいました。「ハイデガー、アーレント、ベンヤミン、フーコー、デリダら現代思想のスターたちの失敗から解き明かすユニークな政治哲学入門」と本の帯にはあります。哲学だけを論述の対象にするのではなく、それらの哲学者の実際の政治的行動もあわせて論じているので小説を読むようなおもしろさがあって、二十世紀後半の思想の流れを現実の歴史の流れに沿って読み直すことができます。
で、話は変わって、ジョン・アーヴィングのこと。若い友人とアーヴィングを読み直したらおもしろいだろうねという話をました。日本の文芸評論家がフーコーだとかデリダだとか、いわいゆるポスト・モダンの哲学に夢中になっている間に、日本の小説家に影響は与えたのはジョン・アーヴィングでした。若い友人によるとちょっと考えただけでも、保坂和志の小説にもアーヴィングの名前を発見することができますし、小川洋子や角田光代の小説もアーヴィングからインスピレーションを得たのではないかというディテールを見出すことができるということでした。その考えに私も賛成。
確かにアーヴィングは30年前に日本で紹介され始めた時に魅力的な作家でした。そして、フーコーやデリダをいじっていた文芸評論家からはこれまた見事にまったく無視されました。にもかかわらず、アーヴィングが提出するイメージというのは、ポスト・モダンの哲学の痛烈な批評になっています。通常の批評は「物語」を「批評」するのですが、ポスト・モダンの哲学のそばにアーヴィングを置いてみると「物語」が「批評」を批評しているという転倒が起こります。これはおもしろい転倒です。批評は直感的なリアリティを要求されませんが、物語(小説と言ってもいいのですが)はリアリティを要求されるためにこうした転倒は起きるのでしょう。
10月に大阪で小川洋子さんと一緒のシンポジウムに出席した時、小川さんが「偉大な日常の発見」と発言していたのが印象に残っていますが、こうした表現は非現実的な批評家の言辞に悩まされた来た作家には直感的に理解できてしまうものであって、同時に「物語」が「批評」を批評するという転倒の中から生まれてきたものなんだなと感じました。おもしろい発見をしました。
冬の海の家
2005年12月11日(日)
広い空と大きな海とどこまでも続く砂浜の九十九里海岸までドライブしてきました。何時も何か用事があるのですが、今度はほんとうにドライブ。
アクア・ラインから木更津に抜けて、紅葉がまだ終わってなかったので、房総半島を横切るようにして、鹿野山と清澄山の西側を抜けて天津小湊に出ました。紅葉もまだこ残っていましたし、途中でたくさんの柿の実が実っているのでも出会えましたが、山道があんまりぐるぐると回っているので、運転していて目が回ってしまいました。これはちょっと心配。
それから太平洋沿いに九十九里浜の大網白里まで北上。ここで西の空へ陽が落ちて行きました。東の空も沈む陽の照り返しで、雲が紫がかったピンク色に染まっていました。引き潮で黒く濡れた波打ち際を千鳥が一羽、千鳥足なんて冗談でしょうという言いたげにまっすぐに走っていました。海の色に乳白色とブルーが混じった感じ。冬の海も時折、こんなパステルカラーに染まるのだなと関心したくなる色でした。
こんな季節に海岸にならんだ海の家が営業しているとは思えなかったのですが、幾つかの店の中には人の影がありました。で、覗いてみると「いわしの丸干しとハマグリとイカを鉄板で焼くだけ」というメニュー。
「それだけならあります」
浅黒い肌につやのない髪。いかもに海辺の人らしい風貌のおばさんは、その風貌に似つかわしくないやさしい声で日暮れに飛び込んできたお客の相手をしてくれました。「飲み物は自動販売機を利用してください」という店内はがらんとしてましたが、それでも、カップルが一組、熱心に話し込んでいました。
昨日、高速道路を走りながら聞いたラジオでは「明日は都心でも雪がちらつくかもしれません。お出かけするなら今日のうちに」なんて言ってましたが、ほんとうに小雪が舞い始めました。池袋で開かれた伊藤比呂美さんの朗読会を終わって地下鉄を降りたら、空から白い粒々がぽつぽつと舞い降りてきました。
研究室にサンタが
2005年12月09日(金)
講義を終えて研究室に戻ってみるとサンタが来てました。のまネコがちょこんと机の前の椅子に座っているではありませんか。しかも黒い瓶に「米」と書いてあるやつを持って。ふかふかののまネコです。サンタさんありがとう。
豆蔵さんとうちの娘が捕獲してきたちびのまネコは台北の東呉大学日本語系の皆さんに可愛がってもらっているようです。
耐震構造偽装問題
2005年12月08日(木)
鈴木隆之さんのホームページを覗いてみるとロサンゼルスでもネットで日本の耐震構造偽造問題のニュースを把握しているとのことでした。最初は「さもありなん」と思っていたそうですが、しだいに驚きを増していると書いていました。
鈴木さんによると建築は経験が重視される仕事だそうです。その経験重視の現場が耐震構造偽装の設計図のままに建物を建ててしまったことに驚いている様子です。
これまで内閣が吹っ飛ぶような事件はいろいろありましたが、この耐震構造偽装問題はロッキード事件以上に国民生活密接に関連した問題ですから、予算委員会が開かれる来年1月2月の国会が大荒れになりそうな気がします。この事件とはまったく無関係ですが、こうした時期には内閣を揺さぶるような細かいニュースがぽろぽろ出てくるものです。すでにその兆候が現れているようなニュースを私はいくつか見つけました。
いずれにしても働いている人が投げやりな気持ちになるような世の中はいい世の中とは言えませんね。
武道館で
2005年12月07日(水)
武道館の小田和正のコンサートに行ってきました。ゲスト?飛び入り?で矢野顕子とゆずが顔を出したのが楽しかったです。とくに矢野顕子は「すごい」って聞いていたけれども、レコードやCDだといまいちわからなかったのですが、ライブだと声の表情の微妙な感じがすごくおもしく、これが「すごい」って言われるゆえんだなって思いました。
それにしても、武道館というと大学の入学式や卒業式で出かけることが多いので、客席は「おばさん」ばかりっていうのはなんだか保護者会にいるような気分でした。圧倒的に50代40代の女性の観客が多く、ま、私の「おばさん」のひとりなんだけど、なんというか、へんな気分でした。この気分をいったい何と言ったらいいのだろうかしら?
スープのだま
2005年12月05日(月)
朝のうち、ぼんやり曇っていた東京にしっとりとした冷たい雨が降りました。寒くなりました。子どもの頃、こういう寒い日にはよくコーン・スープを作ってもらいました。
小麦粉をバターでいためてホワイト・ルーを作り、コーンの缶詰(クリーム状)と牛乳で作るスープです。小麦粉をバターでいためる作業が難しくて、なかなか滑らかなホワイト・ルーになりません。ところどころに小麦粉のかたまりが出来てしまうのです。それで、出来上がったスープにも小麦粉の粒が入っていました。これを「だま」といいました。
「だま」はコーン・スープに混じっていると、コーンの粒とよく見間違えることがありました。コーンの粒だと思って食べてみると、ねちゃと柔らかくはじけて、時には粉っぽい味がすることもありました。お料理としては失敗なのですが、でも、私はこの「だま」が好きでした。いや、今でも暖かいスープの中の「だま」が好きです。買ってきたコーン・スープや、お店で食べるコーン・スープには入っていない「だま」は家で食べるスープの味の大切な一部分です。
もし、お店で食べるスープに「だま」があったら、なんだかすごく損をしたような気がするのに違いないのです。でも、家の味はそんな失敗もいいものになります。寒い日にほっとするのは「だま」の入ったコーン・スープです。
↑前のページ / ↓次のページ
|
| |
|
|
|
|
| |
|
| |
|