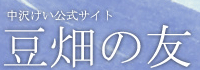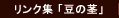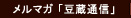|
|
 |
 |
| |
|
| |
冬景色
2006年01月23日(月)

雪の日にベランダから撮影しました。なんだか深い山の中にいるような景色です。
ばりばりばり。
2006年01月22日(日)
明るい日差しとばりばりという音で目が覚めました。昨日の雪が凍ったところを、自動車が走る音がばりばりばりっと響いています。今日はどこもかそこも路面は凍っているのでしょう。
雪の降った次の日というのは驚くほど明るく、そして冷たいものです。自動車が凍った路面を走る音は、その明るい空気にひび割れを作って行くような感じがします。今日は明るい東京湾を眺めに行こうと思います。
雪です。
2006年01月21日(土)
夜明け前から雪が振り出しました。うっすらと積もっているところです。まだまだ降りそうです。
83年から84年にかけての大雪の時は1月から3月までに東京で30日も雪が降ったそうです。3日に一度雪が降ったことになります。ロッキード事件の判決が出た頃で「新潟三区のたたり」なんて冗談もありました。
この歳の冬は母と過ごした最後の冬でした。83年の7月に脳梗塞の発作を起こし、後遺症で右半身麻痺が残った母はそれから85年の1月まで入院生活をしていました。83年の大晦日には病院から家のほうに戻ってお正月を家で暮らすことになっていました。小雪が舞ったのは大晦日の深夜でした。
それから年が明けて、ほんとうに雪の日がよく続きました。母の入院先の病院は所沢のお茶畑に残った雑木林の中にありました。後に産廃銀座なんて呼び名もつくようになりましたが、その頃も雑木林の中やお茶畑の中にはたくさんの産廃処理場がありました。病院の隣も産廃処理場で、しばしば形容しがたい異臭が漂っていることもありました。病院へ続く雑木林の中の道路はまだ舗装されていませんでしたから、雪が降るとタクシーも入ってこられないのです。もちろんバスもありませんから、雪が降ると、タクシーが来てうれる場所まで、0歳の娘をおんぶして(これがぽかぽかあったかくってカイロの代用になった)、1歳のお兄ちゃんには歩いてもらいました。
その母に聞いた話ですが、終戦の翌年もよく雪が降ったと言ってました。お正月から積もるような雪が降ったという話でした。それから昭和38年の38豪雪。とすると20年おきくらいに大雪の年があるようです。
耐震構造偽装問題が吹っ飛んで
2006年01月20日(金)
ライブドア事件のおかげで、耐震構造偽装事件がすっかり吹っ飛んだかたちになっています。テレビも新聞もライブドア事件を追いかけるのて手一杯で、耐震構造偽装問題は二の次というかたちになってしまいました。
テレビは「文脈」がないとジョン・アービングが「第四の手」で書いていましたが、こうした大事件がかさなると新聞もまた「文脈」を失ってしまいます。「文脈」というのは感情の継続的変遷と考えてもいようなところがあって、それは「愛情」を根底で支えているものだとアービングは考えているようです。
大量の情報にさらされながら「文脈」を維持するのは容易ならざることでしょう。その意味ではネットもさらに「文脈」の破壊を加速させる材料になってゆくでしょう。メディア不信というのは、メディアがどのような情報を流しているのかという情報の質の問題以前にメディアの存在そのものを疎ましく感じる感情が働いていると思えてきました。昔から新聞なんて読まなければ世の中は平和だと考える感じ方は存在していましたが、そういう拒絶的な感情のほうも、メディアの発展と同時進行でおおきく膨らんできているに違いありません。
今日から通常国会。大事件続きで、大荒れになるのかそれとも、あまりに案件が多すぎて焦点がぼけてしまうのか、あるいはメディアそのものにうんざりした人々の感情の影響で奇妙にしらけた国会になるのか、その雰囲気は予想がつきません。「文脈」を失った情報によって感情が「断片化」された結果が奇妙な騒ぎを生みそうな予感がします。民主主義というのは大衆的な情報の提供が前提で成り立っている政治システムですが、それがあまりに過剰なためにまったく機能しなくなってしまうという可能性もはらんでいます。
霜が降る前に植えたビオラ
2006年01月19日(木)

花屋さんに「霜が降る前に植えるが根ががっちり成長するよ」と教えてもらったビオラです。写真は10月に植えたばかりのところで、今は鉢一杯に成長しています。今年は寒いので、鉢の中は根っこがびっしりと張っていることでしょう。冬を越した株のほうが晩春まで花を咲かせ続けるのだそうです。ビオラの株のしたにはムスカリとチューリップの球根を植えておきました。どんなふうに花が咲くのかたのしみです。
今朝の新聞にはライブドアショックの文字と一緒に東京証券取引所の取引停止という大きな文字が躍っています。ライブドアへの強制捜査にはいささかならぬ大きな疑問を持っています。昨日あたりは粉飾決算の疑いが出てきていますが、もし、粉飾決算だとしれば、そもそも株式上場が認められたことが大問題だといわなければなりません。ライブドアの問題というよりも証券取引所の信用問題です。
ライブドアつぶしが思わぬ大波紋を呼んでいるというところが実態なのではないでしょうか?粉飾決算も風説の流布もはっきりしない嫌疑のまま、ライブドアのような大衆的支持を集めた会社を突然に強制捜査をすることそのものが、そもそも当局の認識不足をあらわにしているように思えます。耐震構造偽造問題を隠すためではないかと考えたいたので、もし、そうだとすれば、これはあまりにも代償が大きすぎると言えるのではないでしょうか?
耐震構造偽造問題で年明けの国会は大揺れになりそうだと予想していましたが、類推が正しいとすれば、国会よりも外に飛び火したかたちで、その火事はかなり大きく燃え広がるのではないでしょうか?こうした大衆的支持を集めている会社に粉飾決算の疑念があれば、捜査側は株式市場全体の信用を失わせないために、もっと周到な準備をするべきだということは現時点で言えることです。ライブドアへの嫌疑が真実であれば、なおさら、そうした市場への周到な配慮が必要でしょうし。もしその嫌疑が真実でなければ、これは当局は大きく責任を問われるべき市場の混乱をもたらしたと言わざるおえないでしょう。
証券取引所も国会も地検も、この冬をどうやって越えるのでしょうか?私はここのところの一連の動きは「国」のコントロールが機能不全を起こしていることの現われに見えています。さて、これから、どんなものの根が張るのが、またその張った根がどんな花を咲かせるのか?こちらは楽しみというよりも、いささかホラー小説じみた感じの期待?というか怖いもの見たさみたいな感じがあって、嫌な感じ。
こう見えて、
2006年01月18日(水)
こう見えて、ほんとうはかなり忙しい。忙しいけれども忙しいと言わないのはもの書きの「武士は喰わねど高楊枝」だとは思いつつ、テレビをばっちり見てしまうと、ついつい、「くそっ」とあまりお上品じゃないスラングも飛び出してしまいます。
見てたのはもちろんヒューザー社長の国会の証人喚問。で、証言拒否ばかりでつまらなかったかというとそうでもなかったのです。
テレビの報じるこの人の経歴は戦後に日本の歴史そのものというか、いわゆる中間層とか中流というものはどういうものだっかなと考えさせられるところがあって、表情を見ているとディケンズの小説を読んでいるように想像力を刺激させられるものがありました。で「くそっ」て思ったのは、そのあたりの自分の感じたことをうまく言葉にできない、つまり言語化できないってことに対する腹立ちです。
百聞は一見にしかずですが、その一見を言葉にするためには、すごくたくさんの時間が必要で「高楊枝」の見栄だけではどうにもなりません。
焦げ臭い、うそ臭い、うさん臭い
2006年01月17日(火)
ライブドアが家宅捜索を受けたというニュースのあとヤフーの掲示板を覗いたところ、明日、国会で行われる証人喚問隠しだという指摘で賑わっていました。やっぱりそう思う人が多いのだなあというのが私の感想。
NHKが勇み足ぎみの速報をして、わざわざ夕方のニュースに間に合わせるような時間に家宅捜査に入るなんてだけでも、うそ臭い。それに容疑もそれほど騒ぐようなことかと思える程度の容疑だし、なにか意図が働いているようできな臭い。ライブドアはスケープ・ゴートにされたんだという点では掲示板の意見は一致しても、誰がホリエモンをスケープ・ゴートにしたのかということになると諸説紛々です。
ふつう、こうしたメディアの注目を分散させるような動きというのは「政府」もしくは「与党」が仕組んだということになるのですが、今回の場合は「政府」の中の誰か、もしくは「与党」の中の誰か?が問題になっています。つまり「政府・与党」の中の暗闘がこうしたかたちで表に出てきているのではないかといううさん臭いを感じさせる騒ぎになっています。
NHKが勇み足な報道をするなど、微妙な手際の悪さも感じさせるところがあって、映像の向こう側でいったい何が起きているのだろう?とかんぐりが働いてしまいます。が、明日の証人喚問は、ライブドアの強制捜査以上の関心を集めることは間違いないでしょう。なんと言っても自分の住んでいる家や隣の家が問題なのですから。
消防自動車
2006年01月16日(月)
暖国育ちの私はカマクラの中でお餅を焼いたり蝋燭を灯すことができるので不思議でなりませんでした。雪がむろのようになってしまうという点では雪中の火事もまた同じ理由で、ひとつの場所だけが燃え盛るのだそうです。
以前、山形を旅行していたとき、周囲は新緑に包まれようとしているのに、そこだけ黒々とした冬が残っているような火事場の跡を見たことがあります。建ったまま真っ黒になっている柱や斜めに傾いた梁などの家の残骸でした。雪の中の火事は現代の消防自動車の威力を持ってしてもなかなか消しとめられないものだそうです。
うちの近くの地下鉄の駅のそばに消防署があります。消防車は2台。1歳になるかならないかくらいお坊やがお母さんといっしょに消防自動車を一生懸命見ている姿をときどき見かけます。よほど消防自動車がすきなのでしょう。昨日、その消防車の前を通った時も坊やは消防自動車をお母さんと一緒に飽かず眺めていました。
すると消防署の奥から、制服を着たおじさんが出てきました。歳格好から見て、消防署では少し偉い人のようです。
おじさんは坊やに「消防自動車に乗せてあげよう」といいました。が、坊やは突然そう言われて、怖くなったのか、一歩、二歩とあとづさりして、しまいには背中をお母さんにぴったりくっつけてしまいました。
「じゃあ、お母さんと一緒だったら乗る?」
そう改めて聞かれると、笑顔を満面に広げて「うん」とうなづきました。制服のおじさんは消防自動車の扉を開けて
「はい、お客様を二人ご案内」と言いました。
坊やはお母さんに抱っこされてにこにこと消防自動車に乗り込みました。もしかすると、あの坊やは大きくなったら消防士になろうと決心したかもしれません。
新聞は北越雪譜だらけ
2006年01月15日(日)
金曜日に雑談をしていて「ここのところ、新聞のコラムや短信欄は北越雪譜だらけ」という話になりました。確かに私も北越雪譜からの引用のコラムをいくつか見ました。天麩羅のくだりを引用しているのはありませんでしたが、そんなことは自慢にならないし、みんなおんなじことを考えるのだなあと、ややしょぼん。
雪の中で怖いものは「洪水」「火事」そして天麩羅の次に出てくる「狼」なのだそうです。「雪中洪水」の章には、リアルな挿絵もあります。この挿絵をリアルだと感じるようになったのは、数年前に青森で、じっさいの雪の溶ける様子を見てからでした。真冬のさなかの晴れた日の雪解け水の凄まじさは、想像以上のものがありました。青森空港は山の上にあるのですが、その空港へ向かう坂道を雪解け水がざあざあと流れているのです。毎日毎日雪模様の空が続いていたのが、やっと晴れて青い空が見えたと思ったら、こんどは白い雪がきらきら光る冷たい水になってざあざあと流れ出すのです。
北越雪譜が恐ろしいものとしている「洪水」「火事」「狼」のうち、なくなったものは「狼」だけです。
天麩羅の話
2006年01月12日(木)
鈴木牧之の「北越雪譜」に中に天婦羅の話があります。大阪から江戸へ駆け落ちしてきた利助という男が、牧之の江戸京橋の家の裏に住んでいました。この男はなかなか気が利く者で、江戸では大阪では流行っている魚のつけあげを食べさせる店がないことに目をつけました。魚のつけあげ辻(道端)で売れば儲かるのではないかと山東京伝に相談したところ、ためしに調理してみろと言うことになり、なるほどこれは旨いと、商売を始めることになりました。すこで、これを売るに当たって何か良い名前はないかと利助が言うので、山東京伝が考えたのが「天麩羅」だそうです。
出奔して天竺あたりまでふらふらしてみようかという男が売るから「天麩羅」であり、麩には麦という字が含まれていて、さらに羅は薄い衣という意味なので、小麦の薄い衣をつけて揚げる食い物にはぴったりだということで、この文字を提灯に書き付けたのはまだ若かった自分だと牧之は書いています。利助は天麩羅をひとつ四文で売っておおいに商売繁盛そうです。
「北越雪譜」を雪国の生活を描いた随筆ですが、時々、こうした思い出話が混じったりして、そこがきままに書く随筆らしいところです。昨夜、天麩羅を食べたので思い出しました。ちなみに「てんぷらの話」に次の章は「雪中の狼」という章になっています。
↑前のページ / ↓次のページ
|
| |
|
|
|
|
| |
|
| |
|