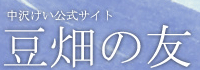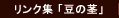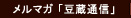アンチ左翼とアンチリベラル
2004年10月03日(日)
フィリップ・ロスの「ヒューマン・スティン」を読むと、アメリカがアンチリベラルの心情にとらわれているのがよく解りました。日本のアンチ左翼とパラレルな現象でしょう。
理想主義に極端で急進的な情熱が加わったあとにはこうした冷淡な現実主義がもてはやされるのでしょう。理想だけ残して、急進と極端を止めるというバランスはなかなか取れないのでしょうか?
ところで、捕鯨が国際問題化するたびにアメリカは「白鯨」をどうやって生徒や学生に読ませているのだろうと不思議に思っていました。どうやら、古典教育というものをかなり捨ててしまったようです。今では「白鯨」のタイトルさえ知らない中学生がいるという教師の嘆きが「ヒューマン・スティン」の中に出てきました。
日本も欧州もアメリカの教育学の影響を受けて古典文学教育を縮小しました。過去の価値観からの決別という意味もその縮小には含まれていたのですが、これをやると価値観そのものが失われてしまうという現象が起きることは勘定されていなかったようです。
さらに言葉の意味を重層的に奥行き深く取るという訓練もできませんし、意味を保証する審美眼も育たないということも考えなくてはなりません。
どうりでアメリカ大統領選で幾らケリーががんばってもブッシュ優勢を復すことができないわけです。
アンチ・リベラルの聴衆の耳にはケリーの言い分は七面臭い奇麗事を言っているようにし響いていないらしい様子です。
フラソワーズ・サガンと森村桂
2004年09月28日(火)
今朝の新聞に森村桂さんの訃報が載っていました。自殺?らしいのですが。
庄司薫とか森村桂とか、あるいは鈴木いずみとか、そういう作家の仕事の延長線上に村上春樹や山田詠美、吉本ばなながいるような気がします。そういう文学史を組み立ててみるのもおもしろいでしょう。
数日前の新聞にはフラソワーズ・サガンの訃報がありました。最初に来日した時に「週刊女性セブン」で対談をしました。すごい皺の深い顔に驚いたのを覚えています。深い皺の刻まれた皮膚は、濃密なと言いたいくらい細かい毛の覆われていました。産毛のようなその毛はライテングの具合でぼんやりと金色に輝いて見えるときもありました。幾らか赤みがかった白い肌が金色の毛で覆われ、そして深く皺が刻まれていたのです。そのときのサガンは50歳くらいだった勘定になります。皺は深いけれども柔らかく、表情の変化とともにゆるやかな曲線を描いて風紋のように変化するのでした。通訳の入る対話をそっちのけにして、よほどまじまじと皺を見詰めていたみたいで、今でも目にくっきりと浮かびます。
対談をした時のことを新潮社「波」に書いたのですが、今まで書いたエッセイの中でも一番書きにくいエッセイでした。なぜって顔の皺ばかり目の前に浮かぶのだけれども、そのことは書かなかったから。豆しぼりの手拭をねじってスカーフのかわりに首に巻いていました。フランス人だからサマになるけれど、日本人だったら笑っちゃうようなファッションでした。
フラソワーズ・サガンとかコレットなどのフランスの女性の小説家がいなかったら、私は小説を書こうと思わなかったかもしれません。小説に対するいちばん甘い願望はフランスの女性作家によって触発されたのかもしれません。
久しぶりにフィリップ・ロスの小説「ヒューマンスティン」を読んでいます。アメリカの田舎町の大学が舞台なので、懐かしいような本の名前や哲学者の名前が出てきます。とくにフランス人の女性の教授の周辺には、懐かしい名前がごろごろしています。
私の少し上の作家、例えば中上健次などはフォークナーを読んでいましたし、その上になるとヘミングウェイを読んでいました。フィリップ・ロスやそれに南米のガルシア・マルケスが日本に紹介されたのは、私が大学に入る頃でした。
ただ懐かしいのではなく、何か歴史の流れの中で見晴らしの良い場所に出てきているなあという感じがしています。
それにしても今年はいやに「自殺」の文字が目につきます。今日はお月見。旧暦8月15日の十五夜です。
スクープ(特ダネ)はスクープ(幽霊)?
2004年09月23日(木)
北朝鮮北部で大爆発があったというのは、発電所を作るための発破作業だったということで落ち着いたようです。まったく疑問がないわけではないのですが、そういうことになったので、空騒ぎでした。
北京発の情報と思ったのは私個人の思い込みでした。どこでそんな思い込みができたのか、記録を残しているわけではないでの見当がつきません。これも思い込みは怖いのひとつでしょう。
今朝のネットでは読売が北朝鮮がノドンミサイルの発射準備に入ったと報じています。自衛隊が発射に備えて配備され、日本政府もそういう情報があることを認めてみます。これもスクープはスクープで終わってくれると良いのですが・・・。何か今までと違うことが北朝鮮国内で起きているのでしょうか?いまのところ(23日午前)このニュースは読売しか報じていません。
ひがんばながかれても
2004年09月22日(水)
ひがんばなが枯れても暑い日が続いています。光が丘公園を散歩してきました。萩が花盛り。お彼岸ですね。
昨晩(21日)のジャイアンツ戦の観客が少なかったのや、テレビの野球中継の視聴率が低かったことなどから野球人気の凋落傾向を指摘する記事をネットでいくつか見かけました。実際はパ・リーグの球場には大勢のファンが詰め掛けていたわけですし、注目を集めている対戦カードは巨人・横浜戦ではなかったうえに、多少、巨人に対する反発によるボイコットも含まれていた現象で、必ずしも野球人気の凋落を表してはいないでしょう。
こういう記事はよく世論操作だと言われます。しかし、実際は世論操作でも何でもなくて、たんに記者の現実を把握する力が衰弱している場合もあります。だから「良い」と言うのではなくて、意図的な世論操作よりもよどほタチが悪い場合も多々あるように思えます。
巨人一極集中という強固な固定観念を持って、昨日の巨人戦の視聴率や、球場への入場者数などを見れば前述のような記事も、書いている記者は「ほんとうのこと」を書いていると思い込んでいることもありえます。他の球場への入場者数を調べたり、注目される対戦カードの様子などを見れば考え方や見方が修正されそうなものですが、一度、思い込むとそれがそうは見えないのです。
「そんなばかな」と思われる人もいるかもしれませんが、記事を書く直接の当事者に聞いてみると意外なほどよくあることなのです。現実を見て、情報を把握し、言葉で現実のスケッチをするという作業は、けっこう書き手に負担をかけるもので、かなりエネルギーが必要です。そのエネルギーが枯渇すると、観察に基づく感想を文字にするということができなくなってしまいます。
プロ野球観戦の楽しみ
2004年09月21日(火)
昔、日本ハムに落合がいた頃、誰もいない後楽園で日本ハムの試合を見ていました。観客が少なくてもホームランを打つ落合選手が好きでした。一度だけ試合後にインタビューをしたことがあります。
プロ野球ではありませんが、明治が東大に負けてしまいました。昨日は祝日ですが、明治大学は月曜日の振り替え授業。月曜日は祝日が多いので、振り替えで授業をしないと時間が足りなくなってしまいます。出講して、野球部の学生さんの立ち話をしたのですが、一場が抜けたのはかなり痛いようでした。ここはひとつ気を取り直してがんばって欲しいと思います。いや、外野席の観客としてはそんなことしかいえないのですが、久しぶりに神宮へ行こうかなという気になりました。春は優勝したのですから。
落合はいまや中日監督、ついでに優勝もかかっているし、日本ハムのほうは新庄選手がとんでもない大活躍。新庄はアメリカに行っていい意味でのショーマンシップを持ってきてくれました。
プロ野球はおじいさんやおばあさんと孫がそれぞれの楽しみ方で楽しむのことができるエンターティメントだなあと、スト明けの試合を見て、そういう感想を持ちました。60歳から野球を始めたいという人は少ないでしょうけれども、60歳になったら毎日でも野球を見たいという人も、孫と野球をみたいという人も
大勢いることでしょう。
プロ野球のストライキの議論を聞いていると野球を衰退産業と見ているとようですが、そもそもそれがおかしいのではないでしょうか。産業の中には役割を終えて縮小に向かう産業も実際あります。かつての石炭産業がそうでした。銀行は大型公共投資への融資からほかの産業への融資にビジネスモデルをかえることをここ10年要求されてきました。そうした衰退産業の整理の発想の延長でパ・リーグの経営が取りざたされているように見えます。それで、良質な観客という大事な財産まで失うようなばかげたことをしているのではないでしょうか?
日本の政府は海外からの観光客の誘致ということを言い始めています。観光は名所旧跡景勝を訪ねるだけでなくて、スポーツ観戦も含まれます。パ・リーグもほんもののパシフィック(環太平洋)リーグといえるような築き上げることができれば、いっそう、おじいさん、おばあさんと孫が一緒に楽しめるでしょう。
確かに野球は国民的スポーツではなくなってしまいました。しかし、だからといってもう観客動員はできないかと言えば、そうではありません。観客は国境の向こうにいるということに目を向けてもいいのではないでしょうか?物を輸出することも大事ですが、人に来てもらうという仕事もあります。ネットでホテルの予約もできれば試合のチケットも購入できるのですから、それは不可能ではありません。
プロ野球の経営責任(番外)
2004年09月20日(月)
ゆうべからずうっと考えていたんだけど以下のような罵倒しか浮かびませんでした。
プロ野球球団の経営責任を無視して、教団側がストライキをした選手会に損害賠償を求めるならば、それはたとえて言えば以下のようになります。
打率0でかつ、たびたびエラーをかさねた選手が試合中に負傷したことを理由に年俸の上積みを要求するようなものです。ばか。
法律のほうがもしそんなに経営者側に有利にできているならば、法律のほうを変えればよろしい。頭の悪いやつにもすっきりと解る法律を作ったらよえろしい。いや番外でした。
プロ野球球団の経営責任
2004年09月20日(月)
こだわってしまいますが、プロ野球のストライキでなんだかヘンだなと思っていたのは、球団の経営責任について誰も何も言わないことです。そもそもパリーグが赤字で規模を縮小しようとしたことからこのストライキが始まっています。
で、もし球団経営が赤字であるとすれば、その責任は選手にあるのではなくて経営者にあるのです。選手は毎年の契約更新の時に試合の成績を問われています。それは選手の仕事が野球をすることだからです。経営者は球団の財政を黒字にするか、もしくはとんとんに採算がとれるようにするか、最低でも赤字の幅を小さくするのが仕事です。もし、それがうまく行かなければ、シーズン中の成績が悪かった選手と同じように責任を問われるべきです。
経営者はその仕事がうまくいかなかったからこそ縮小を考えたのです。確かに縮小もひとつの方法ではあります。が、その時、経営者は経営責任を問われるべきです。その経営者側が、まだストライキが決行される前から経営者側は損害賠償を求めると言っていました。損害賠償を求めると言うのでは経営者側はまったくの被害者になってしまい、そもそもの経営責任を放棄したにも等しいことになります。
リーグの縮小は経営事項であって、労働基準法で正当なストライキの権利を認められた雇用問題ではないからというのが、損害賠償を求める根拠になっています。それは、選手に対しての経営責任を負っている球団の経営の失敗はまったく無視した考えかたと言わなければなりません。こんな理屈が通るなら、プロ野球だけの問題ではなくなってしまいます。うまく言えませんが、資本主義の社会の根幹を揺るがすようなルール無視をそこに感じます。もし、縮小よりも他に方法がないとしても、それを納得させるだけの説明と情報の開示が必要になります。そうした経営者側の責任を果たさずに、交渉の最中に損害賠償という言葉が出てくるのは誠実な対応とは言えません。
損害賠償という言葉が出てくるのは、球団経営者は金を出す側、選手は金を出してもらう側という発想に縛られているという感じがするのです。しかしほんとうにプロ野球にお金を出しているのは、観客です。もしそれがスポンサーによる提供であったとしても、観客はスポンサーの商品を買うとか、電車に乗るという形でお金を出しているのです。そこで、経営者は球団の黒字経営をする努力をするのがお金を出してくれた人に対する仕事であり、選手はおもしろい試合を見せるのが仕事なのです。
ストライキをした選手はファンサービスをし、ファンにストライキへの理解を求めました。しかし、球団経営者側はテレビや新聞が伝える限り、ストライキという結果を招いてしまったことを詫びる態度は示していません。あの読売新聞でさえ、球団経営者側がそうした態度を示したことを報道していないのですから、たぶん、そんな態度は示していないのでしょう。ストライキは本来、経営者の責任を問うものなのです。そのような視点が欠落した報道が多いので、なんだかもやもやしていたのです。
昨日のサンデープロジェクトで野村克也氏が「今まで何もしてこなかった漬けが回った」と言っていましたが、それは経営責任のことを具体的には指し示しているのだと思います。
法律上の解釈以前に経営の失敗を無視して選手会側に損害賠償を求めるようなことを球団がするとすればこんなモラルハザードな話はほかにないと思います。
プロ野球ストライキ
2004年09月19日(日)
特別な野球ファンでもないくせに、プロ野球のストライキには自分でもおかしいと思うくらい興味を持っています。そして古田がんばれという心境になっています。
昨日、パック・イン・ジャーナルでストライキについて話ましたが、それで、この問題に興味を持った理由が少しわかるような気がしました。
プロ野球は新聞やテレビという20世紀のマスコミとともに歩んできたプロスポーツです。ネット時代に入って新聞やテレビは、これからの行き方に悩んでいます。それとプロ野球のリーグ再編問題がダブって見えているのです。
話の方向が少し変わりますが、ネット時代に入って、よく良質のコンテンツが求められているという話を聞きます。スポーツは音楽と並んで言葉の壁が低い分野です。ですからオリンピックなども成り立つわけです。スポーツというコンテンツはグローバルな性質を持つネットには向いている分野です。
野球に限って考えれば日本のプロ野球はすでに70年の歴史を持ったいるわけで、これをネット時代の良質なコンテンツにする工夫をすれば、日本の重要な産業のひとつに育てることもできるでしょう。現在の経営者側の言い分はパ・リーグの赤字をどう解消するかという発想ですが、そこにネット時代のコンテンツを育てるという発想はみじんもありません。現在の観客をよろこばせようとするサービス精神さえ感じられないのですから当然ですが。
スポーツ選手はお金をかければ数年で優秀な選手を育てることはできます。かつての共産圏がオリンピックで金メダルをたくさん獲ったことでもそれは証明されています。しかし、しんにスポーツを愛する良い観客はそう簡単には育てられないのです。良質な観客は質の高い試合を生み出し、名場面を作る証言者になって行きます。ですから、良質な観客がいるということが、ネットの良質なコンテンツを生み出す条件になってくるのです。単純に勝ったからうれしい、負けたから悔しいでは、それほどの詳細情報を必要とはしません。試合の多様な楽しみ方を知っている観客こそが詳細情報を欲しいと思うのです。
試合の見方を知っていてマナーを守り、愉快な観戦をする観客を育てるのはむずかしいなあと思ったのは先日の中国でのサッカーのアジアカップの時もそうでした。観客は意図的に育てるわけには行かないのです。自然に育ってくるのをしんぼう強く待つしかないのです。
そういう優れた観客を持っているのは、日本が70年かかって築き上げてきた財産でしょう。日本のように経済成長をしてしまった国が、次に育成すべき産業はソフト産業だと言われています。プロスポーツはまさにソフト産業であって、そこを大事にして欲しいのです。何事にも一日の長(ちょう)というものがありますが、近代工業社会の高度成長をすでに経験してしまった日本の一日の長の一端は、プロスポーツの優れた観客がいるというてんにあると思います。
選手会の思いはプロ野球を衰退させたくないというところにあります。それを情緒的感情的だという批判もあるのは承知しています。しかし、芸術やソフト産業それに興行の世界は情緒や感情にうったえて、利益を上げているわけです。ですから、私の目には選手会のほうが経営感覚があるように見えるのです。もちろん、選手には経営の技術はないかもしれません。経営の技術で選手を支えるのが興行の世界の経営者なのではないでしょうか。
唸ってしまいました。
2004年09月16日(木)
今朝の新聞はどこも佐世保の小学生の同級生殺害事件の保護処分決定について報じています。私は東京新聞のコメントを出したこともあってこの事件に興味を持っていました。
加害児童の特徴について家裁は三つの特徴を指摘したと朝日新聞1面は報じています。
1、対人的なことに注意が向きづらい
2、物事を断片的に捉える
3、抽象的なものを言語化することが不器用
うなってしまったのは、大学生に文学作品を読ませた時の特徴が全部出ている点です。ですから被害者の父親の御手洗さんが、一線を越える子とそうでない子の境はどこにあるのかと戸惑うのも当然だと言えます。これに加えて愉快な感情は表現できても、怒りや寂しさ悲しさなどの不愉快感情が表現できないということも付け加えられているのですが、これも、大学生に文学作品を読ませたときの特徴のひとつです。
事柄の重い軽いを別にすれば、現代の大学生に文学作品を読ませた時の特徴が出ている指摘が家裁から出されたということは、それだけ今までの精神障害を発見しようとするだけの鑑定よりも、より実際に近い結果を裁判所も出してきたと言えるでしょう。
文学作品はなにか人生の問題を解決するためのものではなくて、喜怒哀楽すべてを鑑賞に耐えるものとして表現しようという意図を持って製作されています。
作者がその意図をどれだけ明快に持っているかどうかはまた別問題ですが。ともかく鑑賞に堪えるものとして表現しようとする努力だけはどんな作品にも施されています。
鑑賞するだけで、あとはどうなるのだ言うような人には文学作品を鑑賞する資質がないということになります。逆に鑑賞に堪えないというのは作品に対する最大の侮辱になるわけです。学文学作品を鑑賞する資質に欠けているのに、「鑑賞に堪えない」という批評用語だけを覚えて振り回されると、これはもう手に負えないのです。
こちらは、殺人事件ではなくてせいぜい学校の評価をどうつけるかというようなことですから、まあ、「ああ困った」と唸っているより仕方がないし、教師が唸っているうちにどんどん鑑賞の能力を磨いてしまうので大学生です。でも時々、頭がおかしくなりそうという気分になることも事実です。
プロ野球中継
2004年09月15日(水)
プロ野球のリーグ再編問題がいろいろと言われていますが、ある時期から夕暮れの飲み屋や食堂で野球中継の音を聞かなくなりました。いったいいつ頃からでしょう?
今のダイエーの王監督が巨人軍を引退する時にニュースは西荻の「ダンテ」という喫茶店で、誰かが読んでいたタブロイド誌で知りました。「ダンテ」の向かいに「初音」というラーメン屋さんがあって、そこではラジオの野球中継が流れていました。「ダンテ」を出て「初音」に行くとお客さんたちが王選手の話をしていたのをよく覚えています。
よく覚えていると言えば、長島選手が巨人軍を引退する時のことも記憶に鮮明です。まだ中学生でしたが、中間テストが終わって、写生会に出かけていました。館山港で船舶を写生しながら、ずっとラジオで野球の試合を聞いていました。「巨人軍は不滅です」という挨拶を長島がしたのはこのときでした。お天気の良い秋の日でした。
水道橋の会社に勤めて、明治大学の2部に通っていた頃には、後楽園スタジアムはドームではなかったので、球場のライトが点等すると、「あ、これは一限に間に合わないなあ」と思ったものでした。野球ファンではないのですが、そんなふうにあっちこっちに野球をその中継が記憶の背景として残っています。まるで昔の写真の背景に写りこんでいる景色のように。
↑前のページ / ↓次のページ
|