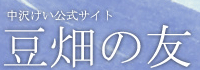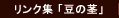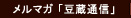�U��c��g�t
2004�N12��10���i���j
�@�����u�����̎����قƂ�Ǘt�𗎂Ƃ������ƂɁA�g�t�������U��c���Ă��܂����B����Ȃɍg�t�̖��������̂��Ɗ��S����قǁA�����炱����ɍg�t�̖�����܂��B
�@�����u�����͌��̓O�����g�n�C�c�ƌ����Ă��܂����B�A�����J�R�̏��Z�Z��ł��B�O�����g�͂����������O�̏��R�������ƕ����Ă��܂��B�������痧���n�y��s�@�Œʋ��Ă����l������̂������ł��B���Z�Z��ɂȂ�ȑO�͔�s��ɂȂ�\��ł����B��s�ꂪ�������Ȃ������ɏI��ɂȂ��Ă��܂����̂ł��B
�@�O�����g�n�C�c�ƌĂ�Ă����������炩�o���Ă��܂��B�����ČR����͕Ԋ҂ɂȂ��Ă��܂������A�����Ƃ��Đ��������O�ŁA���͓͂S��Ԃň͂��Ă��܂����B���̌����u�����̎��̓O�����g�n�C�c�̍��̎������̂܂ܗ��p���Ă���Ƃ���ƁA�V�����A�������łł��Ă��܂��B
�@�܂�ŃT�o���i�̂悤�Ȃƌ`�e�����قǁA�����u�����̎��͕��ς��ș��������Ă��܂����B�A�����J�l�͎��̎�ނɊW�Ȃ����̍����ə��肷�邱�Ƃ��D�ނ悤�ł��B����̃A�����J�R��n������Ȃӂ��ș��������Ă��܂��B���A���ł͂قƂ�ǂ̖����{���Ȏp�ɖ߂��Ă��܂��B�����Ɂu�O�c����v�Ɩ��O�����Ă���ł̖����͍��ł����Ɏ}���L���A��������Ƃ����p��ۂ��Ă��܂��B
�@�g�t�͂����炭�A�����Ƃ��Đ�������Ă���A�����ł��B�ǂ̖��Ⴍ�āA�X�ɗt�̂��邤���͂ق��̎���̍����ɉB��Ă����܂��B���ƂP�O�N����������̎Ⴂ�g�t�̖����h�Ȏp�ɂȂ��āA�H�̐X�ő��݂��悭�咣����悤�ɂȂ邱�Ƃł��傤�B
�����Ƃق��Ƃ���
2004�N12��08���i���j
�@�����̂������̂������Ȃ̂ŁA�����H�ɂȂ�Ȃ����ȂƐ؎��Ɋ���Ă����̂ł����A�H�ɂȂ�Ȃ������ɓ~�ɂȂ��Ă��܂����g�����w���ȓV�C�B�P�Q���ɋC�����Q�T�x������Ȃ�āA���܂Ōo���������Ƃ�����܂���B����������̉��x���͂Q�O�x������Ȃ�č������݂̋C��B�����������Ƃ���B
�@�Ȃ����߂����₷���Ƃ��������͂��܂���B������������Ƃق��Ƃ��܂��B�Ƃ͌����A����������قǂ̊����ł͂���܂���ł����B
�@�P�P�������ɂȂ�Ɩ[���ł������~�����������āA�炢���e�̗t���Ԃ��F�Â��̂ł����A���N�͂�����Ȃ��B�[���ł��M�C�ł��쐅����Q��傫���c��܂��Ă��܂̂��Ԑ���ɂȂ肻���ȗl�q�ł����B���N�̓~�͂��̂ւ�ȋC��̂܂܁A�������ɂȂ��Ă��܂��̂ł��傤���H�V�C�}�߂Ă���ƁA������A�ˑR�A���̂����������Ȃ肻���ȗl�q�ł��B����ȋC�ƕa�C�����Ă���l�͐h�����낤�Ȃ��Ǝv���܂��B
�~�̉ԉƂ������[�Ă�
2004�N12��07���i�j
�@�M�C�ɍs���Ă��܂����B���N�P��̏H�R�x������͂މ�ł��B�H�R����̊җ�̂��j�����ŏ��������Ƃ������̉�������P�S��ڂɂȂ�܂����B
�@���j���i�T���j�����̒�C���̂��߂ɉ��c�s���̗�Ԃ��^�x�ɂȂ�A�V�����ŔM�C�ցB
�@�M�C�ł͎v���������~�̉ԉ��y���݂܂����B�ƁA�����Ă����Ԃ̋C���͂Q�T�x�ɂ��B����Ƃ�����ȓ��ł������B�h�̉��ォ�猩��ԉ͖ڂ̑O���y��Ƃ�������Ȃ��̂ł����B
�@�����͖[�������A�^�ߖ����珉���A�����Ĉɓ��̑哇�܂Ō�����Ƃ��������B�H�R����A�쑺������A�x���K��Y����A�X�r�����ƁA����A���{�̑��������B�쑺���u���F�鍳�v�S�҂�ǂƌ����A�u�ł��A���{�͎����̔��e�ɂ͊���̕n�����͒ނ荇��Ȃ��ƍl�����̂�����ߗ�����Ȃ���v�Ɛ����B�ꓯ�A��x�����������̂́A�悭�l������u���F�鍳�v�͂��{�ł͂Ȃ��āA����̔ߗ��̕���ł����B�����̐l�͒j�̔ߗ��ɂ���Ȃɂ�������Ȃ��ƁA�[���B
�@�[���A�����ɖ߂��Ė�����w�̂P�R�K�̋i��������[��������ł䂭�Ƃ���߂܂����B�O���̃X�g�[���������݂����ɁA�����m���݂͂��Ȃ�L���͈͂ʼn����������悤�ŁA�O��R��̌������ɕx�m�R����������ƌ����A���̐��ɂ͒�������ԏ�̎R�X�A����ɂ͒}�g�R�܂ł��V���G�b�g�ɂȂ��Ă��܂����B�ꎞ�Ԃ��炢�����Ē���ōs���[���ƁA�z�������Ƃ̈��F�̋A�Q�F�ɕς���čs���̂߂Ă��܂����B����Ȃ��炵���[�Ă��́A��N�̂����ɂ������x�����߂�����̂ł͂Ȃ��ł��傤�B
�@�]�ˎ���̐l�͑傫�Ȋ֓�������͂ގR�X�����F�̋���o�b�N�ɍ����V���G�b�g�ɂȂ�i�F�����X���߂Ă����ɂ���������܂���B���̃X�P�[���̑傫����z�����邾���ŁA���ߑ����o�܂��B���E�͂��̍��Ɠ����悤�ɖL���Ȃ̂ɁA�قƂ�ǂ̐l�͂��̖L���Ȑ��E�����悤�Ƃ����Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���H
�@���ł́A���̏o�����̓�����������Ƃ��Ȃ��Ƃ������w�����A�����ɂ͂��Ȃ肢��̂ł��B���Ƃ������ȗ[�Ă����L�����Ă��Ă��A�r���̒J�Ԃɂ͂���ƋC�t�����ɖZ���������Ă����l���吨�������Ƃł��傤�B���ꂪ�܂点�Ă݂���ƌ����������l�����A�������N�����߂����Ƃ��Ȃ��Ƃ����l�����邩������܂���B
�W�H���@�쓇�f�w
2004�N12��03���i���j
�@�K�c���̔ӔN�̐��M�W�Ɂu����v������܂��B���{�̎R����A��������Ȃǂ����ĕ��������M�ł��B�ǂ����Ă���Ȃɂ��u����v���������̂�����Ȃ�����ǂ��A������������i�F���Ə����Ă��܂����B
�@���̋C������������Ƃ����킩��悤�ɂȂ����̂́A�ǂ����g�̂̒��Ɂu����v���N���Ă���̂ł��傤���H�u���̒��g���낤��v�Ƃ����Ђ����Ȑ�����������悤�ȋC�����܂��B�F�{����A���ĒW�H���ɍs���܂����B�d���̗��ł������A�ǂ����Ėk�W���̖쓇�f�w�������������̂ŁA��������o�����܂����B�쓇�f�w�͂��̍�_��k�Ђ������N�������f�w�ł��B
�@�����ւP�E�Q���[�g�����ꂽ�f�w���n�\�Ɍ��ꂽ�������������H����ĕۑ�����Ă��܂��B���ł͊ό��R�[�X�̈ꕔ�ɂȂ��Ă��܂����A��͂�ʐ^�ł݂�̂Ƃ͂܂������Ⴂ���͂ł����B��n�͗h�邪�ʂ��̂̏ے��Ƃ���邱�Ƃ������̂ł����A���̑�n���܂��������̂悤�ɓ��铮�������Ă���؋��������v�������܂��B����ȏ�ɃV���b�N�������̂́A�n���ɉt�����w�����邱�Ƃ������g�����`�ł����B
�@�܂�A���̉��̒n�ʂ��h���̑̐ς������̂悤�ȏ�ԂɓˑR�Ȃ�Ƃ������Ƃ����̃g�����`�̒n�w�͌����Ă��܂����B���k�͎��Ԃɂ���ƂP�O�b�قǂ��Ƃ������Ƃł����B
���C���h�ȐH��
2004�N12��01���i���j
�@�X�^�b�t���[���ɗV�тɂ���Ƃ̂���̗F�l����ƂĂ����C���h�ȐH���̂��b���܂����B�ȉ��R�s�[�ł��B
�u�d�����Ԃ̑�H����ŁA����D���ȕ������܂����B
���N�܂��A�R�Ō����ė�������̎������g�����ē��o�[�e�B�ɏ����ꂽ�̂ł����A�܂���Ɩт��t�����܂܂Ł@�����H���Ă�������@��Ő���Ȃ���@�Ă��ĐH�ׂ����Ă����������̂ɂ͎Q��܂����B
�l�Ԃ́A�{���A����H�ׂ鐶�����ł͂Ȃ��̂�������܂���B
������r�[�������݂Ȃ���|�����ɐH�ׂ銴�o�͂�����ƁA�ǂ����B�B�B�v
�@�~�͎�D���ɂ͂��܂�Ȃ��G�߂Ȃ�ł��ˁB�����~�����w���Ŏ������Ă����X�g�����ɓ��������Ƃ�����܂����A�u�ǂ����H�ׂ����̂��H�v�Ǝ��₳��Ă��������Ȃ��̂ŁA�������h�C�c�ꂾ�����̂ŁA�u�F���H�ׂĂ���ꏊ�v�Ɠ��������Ƃ�����܂����B����ƃh�C�c�l�̋��d�͊�Ȋ�����āA�u�F���H�ׂĂ���̂͂������v�ƓX�̏����w�����܂����B�u�ꏊ�v�Ƃ����P�ꂵ�������Ȃ������̂ł����A�{���́u���ʁv�ƌ���Ȃ�������Ȃ������݂����ł��B�����̉��邮����Ȃ��炠�Ԃ��Ă��܂����B�܂��A���������ւ�ȋq�͖��������̓X�ɂ͒������Ȃ��݂����ŁA���Ƃ͂悫�͌v����Ă���܂����B
�@�тƔ炪���Ă����˂��B����͗E�C������ł��傤�B�u���R�ɍg�t���ݕ����Ȃ����̂������������H�͂��Ȃ����v�ł͂Ȃ��āu�������������A���܂������ȁv�Ȃ�Đl������̂ł��傤�B�������������g�ł��ۂɂ��낪�����~������Ǝ|�������ȂƎv���ق��ł��B�{��l�����邩������Ȃ����ǁB
�Ȃ܂Ȃ܂�������
2004�N11��29���i���j
�@�ɓ���C������Ƙb���Ă���ƁA�ޏ������Ɍ��t���Ȃ܂Ȃ܂����������邱�Ƃ������āA��������o���Ă��܂��܂��B
�u���́A�Ȃ����A�R�`�ŐH�ׂ����t�����X�I����͂������������v
�u�ɓ�����A���t�����X����Ȃ��ă��E�t�����X�v
�@����ȉ�b�����Ĉȗ��A�X��Ń��E�t�����X�����邽�тɁA�m�����u���t�����X�A���t�����X�v�Ə����Ă���悤�Ɍ����Ďd��������܂���B
�@���x���u�������A�����͑��v�����ǏĂ�����ς��肵���b�����_���Ȃ́v�Ƃ����̂ŁA�Ȃ����u�W���E�j�N�v�Ƃ����������ǂ�����Ǝ��̒��Ɏc��܂����B
�@�|�g�t�̂��˓����u�W���E�j�N�A�W���E�j�N�A�P���m�m�j�N�_���v�ƌ����Ȃ���ς��Ă���悤�ŁA�܂������Ă��A�Ƃ̎q�ǂ������ɂ͋C����������̂Ō����܂���B����͑䏊�̔閧�B�ł��A�ǂ����Ă���ȂɁA�����̂��������Ȃ܂Ȃ܂����������ł���̂��낤�H
������肵�����j��
2004�N11��28���i���j
�@�Ƃ͊������H�����ɂ���̂ł����A���j���͉Ƃ̎��͂��畷�����Ă�����̉����̂�т肵�Ă���悤�ł��B���ꂩ��L���b�`�{�[��������l�̐��Ȃǂ��������Ă��܂��B
�@�l�b�g���X�Łu�������ƃg�����y�b�g�v�̗\�͂��܂��Ă���̂͂�����ƁA�ǂ��ǂ��B�Ȃɂ�����j���i�Q�U���j�̖�ɂ͂܂��V���Ђ̒S���҂Ɠ�l�ōčZ���Ă��܂����B���A����A�����Ɨ\���ǂ���̔������ɂ͖{�ɂȂ��Ă��܂��B���̂͂��B���v�B
�@�����u�������A�䂪�Ƃ̎��ӂ������ȍg�t���I��肩���Ă��܂��B���N�͂��܂ł��C���������̂ŁA�g�t�͊��҂ł��Ȃ��Ȃ��Ǝv���Ă����̂ł����A�}���Ɋ��������������肵�ė�N���������Ȃ��炢�ł��B
�@���̂��˓��̑傫�ȉ�ɓ������̂ŁA����͂�������Ƃ��Ǝςă|�g�t�ɂ��邱�Ƃɂ��܂����B�ύ��ݗ������Ēg�[�����邿����ƑO�ɋG�߂ɂ́A�Ƃ�g�߂���ʂ������āA���傤�ǂ�����ł��B
������
2004�N11��27���i�y�j
�@���{������X�����ɂȂ��Ă���悤�ŁA�F�{�ɂ��ߑO�Q���܂ŊJ���Ă���X�[�p�[������܂����B�����ł݂����̂́u������v�ł��B�͂āA����͂Ȃ낤�ƕr�l�߂����l�߂Ă��܂��܂����B
�@�ݖ��̎��Ƃ���������������܂��B���̂��Ƃ����������炵���̂ł����A�u������v�͍�����������������Ȃߖ��X�ł��B�ݖ��̎�����u������v�Ƃ������t���ł��Ă���̂ł��傤���H
�@��B�̊Â����ݖ������߂Č��ɂ������ɂ́A�ݖ����Â��Ȃ�Đ�ɋ����Ȃ��Ɗ������̂ł����A����ɂȂ�Ă݂�Ɣ��g�̂����̎h�g�Ȃǂ́A�֓��̐��ݖ������|�������邭�炢�ł��B�^�钆�̃X�[�p�[�ɍs�����̂͂��̊Â��ݖ����~�����������߂ł��B
�@�Â��Ƃ�����B�Ŏg�������X���Ɠ��̊Â��������Ă��܂��B���������������̊Â��͍������M�d����������̖��c����������悤�ł��B�܂����ł͂��܂�[����H�ׂȂ��ƌ����܂����A�Ȃ����F�{�̐l�͔[�����D���ȗl�q�ŁA���l�Ȕ[���������ɂ͕���ł��܂����B�Ƃ��납���Εi�ς��Ƃ��������͍��ł������Ă���悤�ł��B�u������v����r�����Ă��܂����B�������Â����ݖ�����ɂ���Ă��܂����B
���
2004�N11��24���i���j
�@�F�{�Ō�������ڂ̕s�v�c�Ȃ��̂͊�⡂ł��B���Ԃ�A���������̂��Ɠǂ�ł����̂��Ǝv���܂����A�r�j�[���̑܂ɂ́u��⡁v�̕���������܂����B�����ǂ���A�����̂��̊����ł��B
�@�O����s�v�c�Ɏv���Ă���̂͋������������̂́u�Ђ��́v�ŋ��ȊO�͍��z�̂悤�ȊC�̂��̂ł��A���Z�̂悤�ȎR�̂��̂ł��u����Ԃv�ɂȂ�̂͂ǂ����ĂȂ̂ł��傤�B������A�ق�Ƃ��͂����̂��̊����ƌ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł����A�����̂����L�����J���J���Ɋ������l�q�́u�����v�Ƃ������t���҂�����ł��B
�@��ӁA���ɒЂ��Ė߂��Ă���A�u�ߕ��Ȃǂɂ���Ɨǂ��炵���B���̂Ƃ���܂��䏊�ɕ���o���Ă����Ē����͂�����݂Ă��܂���B�ł��A�����̂��̊���������Ƃ������Ƃ́A���ꂾ����������̂����̂������n�ł���Ƃ������Ƃł��傤�B�����Ƃ����̂��̋G�߂ɌF�{�ɍs������A���S������̓X��ɂ͂��������Ȃ����̂�������ł��邱�Ƃł��傤�B
���m��w���t�y�������̈�コ�炲�ē������������܂���
2004�N11��23���i�j
�@���m��w���t�y�������̈�コ�������t��̂��ē������������܂����B
���m��w���t�y�������@��S�Q�������t��̂��ē�
���������P�Q���Q�T���i�y�j�J��P�U�F�R�O�@�J���P�V�F�O�O
���ꏊ������s���������Z���^�[�k�h�k�h�`���C���z�[��
���Ȗځ��T���@�r�U���`���̃��U�C�N��i�e.�`�F�U���[�j�j��
�@�@�@�@�U���@�o���G�g�ȁu����݊���l�`�v���i�o.�h.�`���C�R�t�X�L�[�j
�@�@�@�@�@�@�@�����ȑ�T�ԓ�Z����S�y�́i�c.�V���X�^�R�[���B�b�`�j
�@�@�@�@�V���@�X�e�[�W�}�[�`���O�V���E�u���m���`The Way of the SAMURAI�`�v
�@���ꗿ�T�O�O�~�i���w���ȉ������j
�N���̂��Z�������G���Ƃ͑����܂����A�����ꓯ�A�F���܂ɂ���ł��邱�Ƃ��y���݂ɂ��Ă���܂��B
���`�P�b�g�ɂ��܂��Ă͓��������z�[���y�[�W���̂��u���t��̂��m�点�v�̃y�[�W�ɃA�N�Z�X���Ă��������܂����炱���炩�炨���肢�����܂��B
�z�[���y�[�Whttp://toyowindband.hp.infoseek.co.jp
���O�̃y�[�W / �����̃y�[�W
|