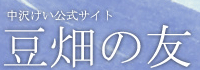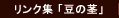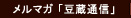|
|
 |
 |
| |
|
| |
北区浮間の火事
2005年02月11日(金)
昨日の夕方、東京北区浮間の温泉掘削現場で火事がおきました。天然ガスに何かの火が引火したみたいです。簡単に言えばガスバーナーに火はついた状態だと思えばいいようです。今朝になってもまだ鎮火していません。
夕方のニュースが流れた時、ベランダへ出てみました。浮間までは少し距離があるので、さすがに火は見えないのですが、一緒にいた息子が「お母さん、ヘリコプターがいっぱい飛んでいるよ」と、雲のかかる夜空を指差しました。赤く点滅するヘリコプターの明かりが、雲よりも低いところを接近して飛んでいました。
今朝の新聞をみますと南関東の地下には大きなガス田があるのだそうです。知らなかった。
100歳を越えるドライバー5人
2005年02月10日(木)
日本には100歳を超える運転免許保持者が5人いるそうです。実際に運転をしているわけではないかもしれません。が、60歳以上のドライバーがかなりな数に登っているのは確かです。高齢化社会は道路上も例外ではないのです。
いったい幾つまで運転をしてもいいのか?時々、考え込みます。個人差が大きいだけに、法令で規定してしまうのも、少しやりすぎの気がします。ですから個人的に自分の判断で運転をやめなければいけないのでしょうけれども。多くの人はどう考えているのでしょうか?
運転をするのと、しないのとでは、大げさに言えば人生設計が変わってくるところがあるので、こういうことはいろんな人の意見を聞いてみたいところです。
60代になった私の叔母は、ナビ付きの自動車で気ままな旅行をしてみたいと言っていました。60代はまだまだ大丈夫。いや、大丈夫であるためには努力がいるというところでしょうか?さすがに100歳は・・・
私は運動神経が鈍いから65歳が限界かもしれません。でも年齢って、下から見ているとすごく年寄りに見えるのですが、なってみるとそうでもないということがあります。小学校一年生の時の6年生は「おっさん」と
「おばさん」でしたら、自分がなってみたら、そうでもなかったというあの感じです。運転免許書についてはこれが曲者かもしれません。
替え歌の歌詞
2005年02月08日(火)
加茂靖子さんからビビデバビデブーの別の歌詞を紹介していただきました。こちらもなかなかです。
「私が幼少のころ(1980年代の千葉県内)は、
こんな歌詞でうたわれていました。
やめてよして
さわらないで
垢がつくから
あんたなんか嫌いよ
顔も見たくない ぷん!
誰が誰に対して歌っていたのか・・・
今から思うと、ひどい歌詞ですね。」
なるほど、東京から千葉に伝ってパワーアップしたのですね。この歌詞はリズムをとりやすい感じだし、歌いやすくなっています。「ぷん」っていうところがすごくいい。ほかにも何かご存知の方がいたら教えてください。
正調替え歌ビビデバビデブ
2005年02月07日(月)
トピックスに掲げた「うさぎとトランペットに使用した音楽」ですが、ビビデバビデブの替え歌には正調の歌詞があったようです。
スタッフ・ルームで管理人のながしろばんりさんが正調のビビデバビデブの歌詞を教えてくれました。
「面白いことに気がつきました。ビビデバビデブーの替え歌、小生が幼少のみぎりも(笑)あったのですが
さわらないで
ちかよらないで
垢がつくから
あんたなんか嫌いよ
顔も見たくない
だったように記憶しています。進化するのかしらん」
津島さんや伊藤さんの歌っていたのにも「垢がつくから」というのがあったので、たぶんこのほうが正しい(!)のではないでしょうか?私の聞いたのは進化したというよりも退化したやつだったみたいです。だって「垢がつく」ほうが強烈だもの。
あんまり好きじゃない単語
2005年02月06日(日)
「うさぎとトランペット」にも「楽隊のうさぎ」にも宣伝文句は「成長」という言葉を使っています。本の宣伝は出版社におまかせしています。それに私はどうも解りやすい言葉というのが苦手なので、わかりやすくなくちゃいけない宣伝文句はおまかせしたほうがいいと考えています。
で、「成長」なのですが、この単語があんまり好きじゃありません。単語を差別しちゃあいけないのかもしれませんが、子どもの頃「成長したな」って言われると妙に腹が立って仕方がなかった。植物じゃああるまいし、成長なんかするもんかと思っていました。「都合良くなってくれたね」って言われているような気がしたのです。早く大人になりたいとは思っていました。なにしろもう充分一人前で、「大人」という資格さえ授与されれば充分と考えていたからです。
「成長」のかわりに「一人前」という言葉は好きです。赤ちゃんでも「一人前」3歳でも「一人前」であるのに、45歳でも「半人前」になっちゃったりするところが大好きです。一直線な感じがする成長よりもぐるぐる回ってくねくねしているので。5歳くらいの男の子なんて「おうおう、いっちょうまえに、やっておるわい」という感じで、公園の木に蹴りを入れたりしていることがよくあります。あれは「一人前」と「半人前」の間くらいかな。
関が原の雪
2005年02月05日(土)
ああ、もう2月も5日ですね。2月は去ると言いますが、ほんとうに月末が少し短いだけであわただしい感じがします。
ここのところ、新幹線に乗る用事がある日というと何かしら奇妙なお天気に遭遇します。今度は大阪の大寒波でした。2月の寒波は当たり前ですが、高速道路で路面が凍結して、通行止めがでるとか、玉突き事故がおきるというような寒波の最中の大阪に行ってきました。
黒門市場でてっちりをごちそうになりました。それから白子の塩焼き。これは素焼きの蓋付きの入れ物に白子がぎっしり入って、蒸し焼きになってました。こんな塩焼きを食べたのは初めてです。それにしても寒い晩でした。空気の中の水分が凍っているような硬い感じの冷え方でした。
帰りは京都がうっすら雪化粧。瓦屋根の凹凸が、雪に覆われるとはっきり見えてなかなかきれいでした。関が原は猛吹雪で、新幹線は徐行運転。東京到着は一時間送れでしたが、急ぐ旅ではなかったので、雪景色が見物できてちょっと得した気分でした。
「ごちそう」を「どちそう」と打ち間違えていたら、スタッフ・ルームで管理人のながしろばんりさんが大笑いしていました。(6日追記)
杜甫草堂のジャン卓
2005年02月01日(火)
マージャンはいつ頃、日本に入ってきたのでしょう?三島由紀夫の「豊饒の海」第一部「春の雪」に宮家に嫁ぐことが決まった総子がマージャンを習う場面があります。これはフィクションですが、大正の末頃には実際に家族でマージャンを楽しむ宮家もあったようです。
文化大革命時代の中国ではマージャンをする人の姿などみかけることはなかったそうですが、今はまた街の中、いたるこころでマージャンをする人の姿を見かけるようになりました。商店の店先などで、お客をそっちのけにしてマージャンをしている商売人もいます。
杜甫が住んだという草堂が成都にあります。この杜甫草堂のある公園の中に気持ちの良い茶房がありました。茶房は中庭を囲むような建物で、庭のテーブルとお茶を飲んでいると、中庭を挟んだ向かい側の棟で、四人の女性が熱心にジャン卓を囲んでいました。いや、正確には5人と二人の子どもです。
子どものひとりはまだ這い這いもできないような赤ちゃんで、白い髪をおかっぱ型に切りそろえたお婆さんに抱っこされていました。このお婆さんは、気が向くとジャン卓の女性と交代でマージャンに加わっていました。おばあさんに変わって赤ちゃんを抱っこしていた女性がどうやら、この赤ん坊のお母さんのようでした。
もう一人はかわいらしい女の子で、この子はジャン卓の周りを回って、それぞれの手の内を見比べていました。年のころは7歳か8歳くらいです。もうマージャンのルールがわかっている様子で、それぞれの手のうちが解っても、顔色もかえずに眺めていました。
女性たちは冬の短い午後をマージャンに興じて過ごすのが日課のような様子でした。これが私が見たなかでいちばん穏やかなマージャンの様子です。しかし、あの静けさは、案外、真剣な勝負であったかもしれません。
雨の夜に
2005年01月30日(日)
どうして早稲田の裏町を歩いていたのか解りませんが、その晩、私は二人の男友達と雨の中を歩いていたのです。「こんな雨の湿っぽい夜はジャン荘にでもしけこむのがいいなあ」なんて話を二人の男ともだちはしていました。その頃に早稲田の裏町にはいたるところに小さなジャン荘がありました。
ジャン荘にしけこむと言われても私はマージャンを知りません。それに人数は3人です。だから、マージャンは無理です。が、そのとき、白く振る雨の向こうから黒っぽい傘を差した男がこちらに向かって歩いてきました。傘の下をみれば、同じ年頃の学生風の顔でした。
「君、我々とマージャンをしませんか」
やにわに男ともだちの一人が、黒っぽい雨傘に声をかけたのです。傘が少し揺れて、傘の主が笑っているのが解りました。
「いや、心配しなくてもいいです。この子はまったくの初心者で、この子にマージャンの手ほどきをするのを手伝ってもらいたいだけなんです」
「えっ」と思いましたが、交渉はすでに始まっていてともだちに恥をかかせたくなかったので、「うんうん」と頷いていました。ほんとうにあたりは暗くて静かな晩でした。
「ジャン荘なら、僕、知っているところがありますよ。そんなに高くないし」
交渉はあまりにも簡単に成立してしまいました。早稲田の学生だという黒っぽい雨傘氏が連れて行ってくれたのは食料品店の二階でおばあさんとその娘(おばあさんからみれば、幾つになっても娘は娘という感じのおばさん)がやっているジャン荘でした。客は私たち四人だけ。昆布茶をおばあさんが出してくれました。
パイの読み方も知らない私がマージャンをやったのはこのとき、一度だけでした。まあ、足手まといみたいな存在で、2時間ほどマージャンをやっていました。最初から2時間の約束だったのです。あとで聞いたら、この黒っぽい雨傘氏はけっこうな腕前の持ち主で、超初心者の私がいたので、「僕らは助かったのさ」ということでしたが、ほんとうでしょうか?
出久根達郎さんからエッセイ集「まかふしぎ 猫の犬」(河出書房新社)をいただきました。そのなかに戦争未亡人の温泉団体旅行の話があって、このジャン荘の一夜を思い出しました。なせかじゃん荘の主は戦争未亡人みたいな気がしたのです。根拠は何もありません。学生相手のジャン荘を娘と経営している老婦人が、戦争未亡人だったというのが、珍しくはなかった時代の終わり頃のことです。
学生街からなくなったもの
2005年01月29日(土)
喫茶店、ジャン荘 玉突き屋(ビリヤード)個人経営の定食屋、古本屋などなど、学生街からなくなったものです。喫茶店はチェーン店のスターバックスなどに代わりました。ジャン荘と玉突き屋はゲームセンターとテレビゲームなどのソフト販売店(こういう店を何というのか疎くなっている)になりました。それから携帯電話屋(こんな言い方があるのかな?)古本屋はブックオフなどの新古書店とレンタルビデオ屋になりました。が、最近では若い店主のいる古本屋さんが少し増えだしています。
喫茶店やジャン荘をのぞくと友だちがいたのですが、今は携帯電話で呼び出すようです。ずいぶん変わったともいえるのですが、対応関係があるところがおもしろいなあと思います。偶然の出会いが少なくなったような気もしますが、ネットの中には昔では考えられないような偶然の出会いもあります。
大学も卒業式は三月ですが、これから入学試験が始まるので、実質的な登校は一月の学年末試験が終わった時で最後になるという四年生も多いでしょう。ですからこの季節、ひっそりと昔を思い出したりします。
文章の書き方 ダイエット 禁煙
2005年01月26日(水)
しばらく前のことになりますが、アマゾン・コムからダイレクトメールが送られてきました。
「文章の書き方 ダイエット 禁煙」の三つに関連した書籍のおすすめでした。正直言って「ありゃま」です。なんでこの三つの組み合わせになったのだろう?
ダイレクトメールはこれまで購入した本のデータをもとに送られてくるのだそうですが、なぜ、太っていて煙草を吸って、時々、文章の書き方に悩んでいるなんてことがわかってしまうのでしょう?これは今年最初の謎。
↑前のページ / ↓次のページ
|
| |
|
|
|
|
| |
|
| |
|