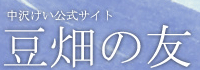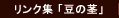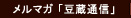グリーンカード
2005年03月20日(日)
グリーンカードって言ってもアメリカの居住権のことではありません。日本で1980年代前半に非課税預貯金の限度管理のために導入しようとした制度です。その頃はマル優って言ってました。政府は貯蓄奨励だったので、一人300万円を限度として、預金金利が非課税になっていました。その限度額を管理しようとしてグリーン・カードの導入が検討されました。結局、この制度は個人情報を国が過度に管理することになると言うこと理由の反対が強くて、導入されませんでした。
なぜマル優があったかと言えば、貯蓄を奨励して、資金を集め、道路、港、鉄道、ダム、空港などの公共施設を建設して行くためでした。マル優を利用していた頃の私たちはそんなことは、少しも考えずに質素倹約こそ美徳だと、貯蓄は道徳的に正しいことを教えられ、信じてました。
今になって、ああ、なるほど、マル優の限度管理が考えられた頃から、国全体の資金の動きを公共投資中心から民間投資中心へと変換させたかったのだなあと気付くくらいです。お金があればたいていのことができるのですが、その次に重要になってくるのはそのお金を誰が持っているかということです。
道路や港などの公共財は国がお金を持っていればできますが、アニメーションやゲームソフト、音楽、絵画などは、国がお金を持っていても作れないものです。おもしろいものを作って、大勢の人に楽しんでもらって、利益も上げようという性格のもの、あるいは服飾やおいしい料理など、それぞれの人によって好みが分かれるもの、などなど、国がお金を持っていたって、ぜんぜん無意味です。民間に資金が回るようにしなければなりません。民間に資金を回すための公平校正な方法を作らなければいけないのです。
政府がグリーン・カードの導入に失敗したあと、消費税が出てきました。これは税金の取り方の構造を変える税制でした。それからリクルート事件がおきます。政治家と政治資金の問題としてさかんに報道されましたが、今から考えると株式市場を公正公平にするための第一歩の事件だったように見えます。その頃はまだメディアという言葉はなくて、マスコミと言っていましたが、マスコミの思い込み報道がひどかった時期でもあります。
今回のライブドアとフジテレビの株争奪戦もここまで来るとフジテレビ側に初期の段階で敵対的買収という思い込みが強すぎたのではないかと疑問を感じるようになってきました。なんのための買収かをよく確認しないうちに敵対的買収に対する防護作を打って、フジテレビはかえって立場を悪くしているのではないでしょうか?どうもそんな気がしてなりません。
よく日本人が幼くなった、幼稚になったという話を耳にしますし、実感もあります。文学が衰退した原因もそのあたりにあるのですが、いや、文化そのものが衰退しているもとは、人の気持ちにあると言ってもいいのですが、そういう現象が起きたのは豊かな社会のためという説明に私は首をひねってきました。なぜなら豊かな社会は、必ず文化的豊饒を生み出してきたからです。
日本人が幼稚になったとか、幼くなったという現象がおきたほんとうに理由は「資本」への無関心だったのではないでしょうか。「会社は社員のもの」という言葉の中で「社員」を「動労者」に入れかければ、社会主義あるいは、共産主義の考え方に限りなく近づきますが、「労働者」という単語を使えば、対抗概念としての「資本家」が登場します。しかし「社員」だと対抗概念が消えてしまうのです。「資本」に無関心というのは、例えて言えば、子どもが親の収入に無関心なのと同じような心理を生み出したのでしょう。まして、日本は会社や企業を家族に見立てる風土ですから、なおさらなのではないでしょう。
グリーン・カード導入は強い反対にあって失敗しましたが、90年代に入ってからの構造改革の中でマル優そのものが縮小廃止されました。また、政府系の金融機関の代表である郵便貯金、簡易保険を含む郵政が民営化されようとしています。
グリーンカード導入の頃から国全体の資金の動きを構造的に変えようとしてきたことを思うと、子どもっぽい投資家が出てきて、許認可事業である放送局を買収しようとするのはなかなかアイロニーに満ちた現象です。デキンズやバルザックが生きていたらきっとおもしろい小説を書いたでしょう。
ここのところ、同じ話題に終始しているようで恐縮ですが、ライブドアとフジテレビの株争奪戦を見物していると、自分が生きてきた時代の「形」(フォルム)の生成過程が見えるようで、どうしても興味が尽きないところがあります。
外国人の団体旅行
2005年03月19日(土)
八重桜が高瀬川の縁を飾っている京都を歩いたのは去年の春です。フランス人は個人主義的な態度をとるから団体旅行などしないと聞いていたのですが、ホテルはフランス人の団体旅行客でいっぱい。フロントはフランス語の洪水に大混乱でした。
3月のはじめに初めて広島の平和記念公園を歩いてきました。紅毛碧眼の外国人団体旅行客の姿。はてさて何人だろうとボランティアガイドの人の言葉に耳を傾けたらドイツ語でした。ドイツ人の団体旅行です。
数年前の夏、こんなに暑くては観光客も少ないだろうと奈良・東大寺の大仏殿に久しぶりにお金を払って入りました。だってうっかり季節を考えずに入ると恐ろしいくらいの中学生や小学生の大群が出現しますから。これは広島でも同じかもしれません。大仏殿の中では、中国人団体旅行客と家族連れの韓国人旅行者が大仏を見上げていました。
日本を旅行しているとあっちこっちで外国人旅行者と出会うようになりました。欧米人は団体旅行をしないと私たちが耳がたこになるくらい聞かせられた話は嘘だったんだなと思います。階級の感覚が根強く残っているヨーロッパでは、言葉の通じない国を旅行するのはそれなにのインテリだけだったようです。階級とか身分という感覚が少ないアメリカ人はもっと前から団体旅行をしていました。
お伊勢参りなどで江戸時代から団体旅行をしていた日本は団体旅行先進国だったのかもしれません。でも、団体旅行って、帰ってきてから考えると、何も覚えていないってことがよくあります。あれは人を頼っているから頭を使わずにすんじゃうでしょう。一番、怖いのは外国旅行の途中で団体から離れる時です。頭の切り替えがうまく行かなくって、自分の身を守る行動に出られなくなっていて、どきりとする場面を何回か経験しています。
今朝の日経新聞は内閣府が近くまとめる「日本21世紀ビジョン」案で訪日旅行者数を現在の年間600万人から2030年には、4000万人に増加させるという目標を報じています。これは団体旅行抜きに達成できない数字でしょう。一度、団体旅行で来て事情がわかれば二度目は個人でという人もいるはずです。政府が思い描いたとおりになるとは限らないのですが。
黒パン見っけた
2005年03月18日(金)
池袋のデパートを歩いていたら、プリチェルを見つけました。細長くしたパン生地のわっかにして両端は「¥」みたいな感じに中央でねじったパンです。ドイツではあっちこっちのパン屋さんで売っています。ブッシュ大統領の大好物で、これをかじりながらテレビを見ていた大統領が、喉にプリチェルを詰まらせ、気絶しているところを夫人が発見したという騒ぎもありました。このときは、イラク戦争開戦前で、世界中からプリチェルを贈られたホワイト・ハウスが悲鳴を上げてました。
このパンについている四角い粒の結晶は一見、ザラメに見えます。が、ほんとうは塩なのです。街角で自転車の荷台にパンを積んで売っているパン屋さんで、これを買って食べた時には予想に反して塩辛い味だったのでびっくりしました。
プリチェルがあるならライ麦のパンもあるだろうと見てみるとありした。ありました。ライ麦90パーセントから20パーセントまで。パーセント表示をしているところが日本のパン屋さんです。
さっそく、すっぱくて苦いライ麦のパンを買って、家で紅茶を飲みながらネットを覗いていると「ホリエモンは和をもって尊しとなすの聖徳太子の一万円札じゃなくて、学ばざれば愚者となるの(学問のすすめ)の福沢諭吉の一万円札で育ったのがまずかった」という投書を見て、思わず「うまい!座布団一枚」と言ってしまいました。「アメリカはフセイン大統領の口の中で何を探しているのか?もちろん大量破壊兵器さ」以来のヒットでした。
ロンドンの金融街
2005年03月17日(木)
1985年の3月末、私はロンドンの金融街シティを歩いていました。ちょっと間抜けなのは、でかけたのが日曜日なので、あたりはがらんと静まり返っていたことでした。なんで、そんな場所を歩いていたのかというと小説のゆりかごを見ておこうと思ったのです。見てどうなるというものでもないのですが。
小説は19世紀の市民社会を背景に生まれた文学のひとつのジャンルです。教科書風に言えばそういうことになります。今でこそ、文学という言葉を小説作品と同じ意味に使う人も大勢いますが、小説というジャンルが登場するまえは、文学の主流は詩歌でした。印刷という技術がなければ小説は登場しなかったでしょう。また印刷された本を読むことができる読者がいなかければ、小説というジャンルが文学の主流になることもなかったでしょう。
市民社会を生み出したのはイギリスの産業革命とフランスの重商主義です。良識のボン・サンスはフランス語であるのに対してコモン・センスは常識と訳すことが多いのですが、最近良く耳にする市民感覚もたぶんもとはコモン・センスでしょう。ボン・サンスも個人の良識というよりは、市民に共通のよき感覚に近い言葉だと思います。
ええと、それで、イギリスの産業革命ですが、これは大きな資本を必要としたために、様々は金融の仕組みを生み出しました。と、ここまでは学校で習ったことですが、そうなると、ロンドンの金融街が小説のゆりかごのひとつであったことになるでしょう。風が吹けば桶屋が儲かるよりも、もう少し確実な事実だと思います。ま、そんなことをぼんやり考えながらとぼとぼ歩いてしました。旅行に行くと曜日の感覚をなくしてしまうので、日曜日だったのはまずかったなあと後悔。三島由紀夫の「絹と明察」とか高橋和己の「我が心は石にあらず」それにトーマス・マンの「ブッテンブローグ家の人々」なんて作品を思い浮かべていました。あと、イギリスの作家、デケンズの「クリスマルキャロル」とか「二都物語」なども浮かんできました。85年よりあとのことになりますが、安達裕美主演の「家なき子」といテレビドラマがはやった時、大江健三郎さんとドラマの話をしたら「あれはデケンズだよ」と言っていたのが印象に残っています。「同情するなら金をおくれ」のセリフが小学生に大流行でした。
シティはロンドンでも古い街で、日曜日でも日本風に言えば下町の感じが色濃く漂っていました。イギリスにしては珍しくいろいろなお魚を山積みにして売っている魚屋さんも近くにありました。その陳列の方法がまるで果物でも盛るように彩りよく魚を盛り上げて、なぜかそこにはうさぎもいて(食肉として売られているのです)色彩的なアクセントを付けるために、真っ赤なオマール海老がちらしてありました。
イースターが近づいていたために、お菓子屋さんは卵型のチョコレートでいっぱいでした。ものすごく豊富な種類の卵型チョコレートがありました。シティの近くのお菓子屋さんと魚屋さんで撮影した店先の様子は、今でも我が家の風呂場の脱衣場を飾る写真になっています。
その頃、もう、イギリスは「ウィンブルドン効果」と呼ばれる金融市場の外国への開放政策をとっていたのかどうか、調べてみたかったのですが、適当な資料が手元にありませんでした。「ウィンブルドン効果」というのはテニスのウィンブルドンのは世界中の選手が集まってくるように、金融市場を外国に開放して世界中の金融機関に集まってもらおうとする政策です。1985年はまたプラザ合意の年でもあって、そこから日本のバブル景気が始まるのです。今、振り返ってみると、現在、私たちが経験している変化はその時期から始まったものでした。パソコンならぬ自分で組み立てるコンピュター、「マイコン」が東京のデパートの売り場に出ていたころでした。
そんな変化の始まりとはつゆ知らず、うさぎと魚をいっしょに売っているのを私は珍しげに眺めていました。日本の兜町や証券取引所のほうがロンドンをまねたのでしょうけれども、似たような下町にあるのもちょっと意外な感じがしました。
ホリエモンの国盗り物語
2005年03月16日(水)
ニッポン放送の塚越孝アナウサーに、プロミスエッセイ大賞の選考会でお目にかかったときに
「野球の時はおもしろかったんだけど、今度はちょっとなあ」
と、ライブドアによる株式買収について、そういう感想をおしゃってました。朝、目が覚めたらほかの会社に自分の会社が買収されていたというのは、おもしろい話ではないでしょう。
民主党の岡田代表はTVのインタビューで「堀江氏に対する生理的嫌悪感があるんです」と政治家一般の反応について語っていました。これまでの価値観を破壊したり軽んじたりする相手に対して、人は生理的嫌悪感を感じます。とくに価値観を軽蔑されたり、軽く扱われたりする時には激しく生理的嫌悪感を覚えます。小泉首相に対してもそうした嫌悪感を示す人がいます。
昨日の朝日新聞「天声人語」はニッポン放送の対抗策である焦土作戦が「はたして社員によって有利なものかどうか」と書いていました。フジサンケイグループに残りたいという社員の望みをかなえるために、焦土作戦をとって相手と同じ土俵に乗ってしまうと、結果として会社は社員のものだという考え方感じ方が脅かされのでしょう。
よく日本はほんとうは社会主義国なんだという悪口を90年代に耳にしましたが、「会社は社員のもの」という感じかたをすごく図式的に言ってしまえば、企業は小さな社会主義国のような状態を作り出して、年功序列、終身雇用を守ってきたのでしょう。企業という小社会主義国の集まりを、合衆国のように集めて、国は資本主義の立場と取るというような構造に戦後の日本はなっていたのではないでしょうか?
それよりもっと遡る「会社は創業者一族のもの」という考え方感じ方は企業を家族に見立てることで、経営者は主人、雇用者は使用人というみもふたもない上下関係を穏やかなものにしてきました。家族に見立てられた会社員が、「会社は社員のもの」という感じ方や考え方
に基づいた仕組みを手に入れると社会主義国に似た構造が出来上がるというモデルを考えてみました。それはかなり公平な富の分配をする結果を生み出しました。みんなで豊かになろうという共通の目標があった時には、うまく機能した仕組みでした。
が、良いことばかりではないのです。豊かさの内容が問われる時代がくると、その仕組みは悪い部分を露呈させてきました。「日本は社会主義国だ」という悪口はその露呈した悪い部分を象徴しているものです。
そこへ「会社は株主のものだろう」という盗賊が現れました。というお話にしてみたのです。現れたのが、正統な救世主ではなくて盗賊だったので、なんだか複雑な気分です。プロ野球問題の時には盗賊に見えた人は少数で、どちらかといえば風変わりな救世主に見えていた人が多かったでしょう。今度は盗賊に見えているという人もかなりいるはずです。盗賊は「だから上から下まで資本主義の筋を通せばいいじゃない」と言っています。筋が通れば、行くべき道も見えてくるというわけです。
ライブドアのにニッポン放送買収は違法ではないといわれていますから、盗賊のたとえは適当ではないでしょう。が、この強引さ、これまでの価値観に基づく秩序の無視はやはり盗賊の例えが相応しいのです。盗賊にも鼠小僧次郎吉も入れば、アリババも物語の世界にはいますし、そもそも「国盗り物語」は戦国の武将斉藤道三を描いた司馬遼太郎の小説のタイトルです。さて、このホリエモンという盗賊はボン・サンスという愛人に気に入られることができるでしょうか?そこが勝敗の分かれ目かもしれません。盗賊が領主になろうとしているこの物語はこれからが、かなりおもしろなんて言っては、渦中の人から大目玉を喰らいそうですが。
ボン・サンス
2005年03月14日(月)
「金貸しの日本史」(新潮新書 水上宏明著)というおもしろい本を読みました。それによると金貸しのもとは神社で、種籾を貸して、秋の収穫のときには、ちゃんと利子をつけてお米を返してもらうというものだったそうです。今の企業の資金集めもこれに似たようなもので、原理的には変わっていないのでしょう。
田んぼにまけば芽が出る種籾と違って、銭は芽を出しません。しかし、人間は銭に芽を出させる方法を考え出したのです。それが賭博です。天武天皇は銭を普及させもしましたが、同時に賭博にも夢中になってしまったらしいです。で、賭博を最初に禁止したのが天武天皇の皇后だった持統天皇でした。天の香具山に白い衣が干されているのを眺めながら、ああ賭け事だけ止めさせなければと思ってのかどうか解りません。
マネーゲームなのか、つまり賭博みたいなものなのか、それとも、まともな投資、田んぼに種籾をまくようなものなのか、どちらだろうと人の興味をそそるライブドアのかげに隠れて、西武鉄道の株式虚偽記載事件はネットの掲示板などでもあまり関心を集めてはいないようです。関心が向かない理由のひとつに一般の人は会社の資金集めの方法などを知らないということがあるでしょう。さらに言えば、何か悪いことには違いないけれどもオーナー経営者が逮捕されなければならないほど何が悪いのかはっきりしないということも、関心が薄い理由になるでしょう。会社は社員のものだと考える日本的経営のもとでは、会社の出資者に興味を持つ必要がなかったという点がこうした関心のなさの根にあります。
ライブドアが「ホリエモンの国盗り物語」なら西武鉄道のほうは「西武処分」とでも名づけたくなるような権力による強制的な企業の解体の様相をみせています。西武鉄道の場合は、会社は社員のものという感覚よりももうひとつ古くて、会社は創業一族のものという考えに根ざしたまま運営されて来ていたのでしょう。企業というものに対する考え方の50年から100年くらいの歴史を、去年の秋からの半年あまりで、西武とライブドアという会社をモデルに復習させてもらうような気持ちでここのところのニュースを見ています。
西武鉄道のような考え方のもとでは、株式会社という仕組みは大きな資金集めの仕組みであると同時に、その裏には「大きな事業は株式公開によって公的性格を帯びなければならない」という良識(ボン・サンス)は幾ら説明して理解されないでしょう。では、ライブドアの買収の対象になったニッポン放送や、それに関係するフジテレビの「会社は社員のもの」という感じ方は、ボン・サンスに近づいているのでしょうか?フジサンケイグループにもかつて創業者一族との確執がありました。それを考えると、ボン・サンスに近づいているように見えるのですが、やっかいなことに「会社は社員のもの」という考え方感じ方は資本に対する興味を失わせてしまうという欠点を持っていると言えます。
社員は自分がもらう給料には興味を持ちますが、会社の資本にはそれほど興味を持たないのは当然のことです。創業者やその一族は資本に興味を持つ存在です。株主もまた興味を持つのは社員の給料ではなく、会社が上げた利益に興味を持ちます。この違いが重要な意味を持っているのだなあと、新聞やらテレビを眺めています。それにしても、新聞もテレビも資本を集める仕組みを支える哲学を承知している取材者は少ないようです。興味をもたなければ、資本に対するボン・サンスも育たないということになります。
このごろ、ボン・サンス(良識)というのは、それだけ独立して存在するのではなくて、みもふたもない現実主義、例えば資金調達とか、マネーゲームと言われるような投機など、簡単に言えば「お金が欲しい」と叫びたくなるような心境などに現れる現実主義と、恋人どうしなのだと思うようになりました。恋人というよりもボン・サンス(良識)は現実主義のミステリアスな愛人と言ったほうがいいでしょう。
お金で買えないもの
2005年03月11日(金)
どの新聞だったか忘れましたが、お金では買えないものもある、例えば「ホリエモン」というあだ名と書いていたコラムがありました。確かにあだ名というのはお金では買えません。
これもいつ聞いたインタビューなのか忘れてしまいましたが、タイガー・ウッズのインタビューを聞いていたら「競争に勝った者は社会に奉仕する義務がある」というセリフが出てきました。タイガー・ウッズの独創的な考えではなくてごく常識を言っている感じでした。ああ、競争社会の裏にはそういう勝者の義務が存在していたのかと納得したものでした。こうした常識というより良識はお金では簡単に作れないものでしょう。
同じくお金で買えないものにひとつに野球やサッカーのファンを上げたいと思います。プロに限らなくてもいいのですが、強いチームならお金を積んでつくることができます。国家的に事業として強いチームを作ることもできます。しかし、良いファン、優れた観戦者はお金だけで作ることはできません。去年の秋、中国でサッカーの試合のあとに騒乱が起きた時そう感じました。
株式会社というものは株式によって資本を集めます。株式というのは会社が事業を行うための資金を集める仕組みであると同時に、その裏には大きな事業は個人や個人の所属する家族に独占されるべきものではなくて、誰にでも参加できる公的なものにならなければいけないという良識が存在しているようです。
株式は資金調達の仕組みだということは理解されているかもしれませんが、同じ仕組みが事業を公的なものにするという良識に沿っていることはどのくらい一般的な理解が得られているのでしょうか?資金集めのシステムは作れても、システムを維持するための良識は、簡単に形成されないのです。
ホリエモンの国盗り物語となずけたくなるようなライブドアによるニッポン放送買収騒動は、東京地裁がニッポン放送の新株予約権を差し止めの仮処分を出したことで、新たな展開を迎えています。ここまで、この騒動を野次馬的に見物してきた感想を言うと、会社は株主のものと考えるホリエモンと会社は社員のものと考えるニッポン放送とフジテレビノの戦いという性格がはっきりしてきました。
会社は社員のものなのでしょうか?株主のものなのでしょうか?資本主義の理屈から言えば後者が筋が通っています。が、前者の考えは戦後の日本の比較的平等な社会を作るうえで、大きな役割を果たして来たことも事実に思えます。はたして、現実の日本社会のボン・サンスはどちらに傾くべきなのでしょうか?
海のニュース 陸の予報
2005年03月11日(金)
青森でテレビの天気予報を見ていたら、「路面情報」というコーナーがありました。道路が凍結しているのか、シャーベット状なのか、雪解け水で完遂しているのかなどを地域ことに放送してしました。
BRCの地方懇談会が広島で開かれた帰りに久しぶりで尾道に回りました。大学時代の友人と夕食を食べていた小料理屋さんではラジオがかかっていました。そこで「明日の航路情報」というのが流れていました。明日、どこそこを通過する大型船は何隻、何々丸は何時何時に通過というふうに、細かく海路の情報が流れていました。会話を止めてラジオを珍しがって聴いていると、
「だって、大型船の通る時の波はすごいもんだぜ」
ともだちが言うのでした。小料理屋の女将さんも
「交通量がおおいですからねえ」
と当たり前の顔で言っていました。
ところが変われば、天気予報で伝えられる情報も変わるものです。瀬戸内海はもう春の様相で水も温んでいました。
暖気してきた
2005年03月10日(木)
青森の「めだかの学校」事務局からおたよりをいただきました。今年の青森は記録的な豪雪でした。以下、青森の「めだかの学校」事務局からいただいたお便りの一部です。
「こちら青森は、ニュースでご存知かもしれませんが観測史上4番目という大雪の冬になってしまいました。
<昨日どこそこの誰かが屋根雪をおろしていて屋根から滑り落ち、んヶ月の怪我をした>、<どこそこの店舗が1メートル50センチの屋根雪に耐え切れず倒壊した>等々、雪被害の記事が地元新聞に掲載されない日がないような状況になっています。
ですが、春の来ない冬はない、と言いますように、二、三日前あたりから雪国特有の重く暗い空に晴れ間の占める割合が多くなってきたような感じがしています。
こちらでは「暖気してきた」と言いますが、寒気に締め固められた道路の雪が融けはじめ、やわらかくなった雪の上を行き交うクルマがまるで波乗りしているみたいに揺さぶられる状態になってきました。 春の近いことが実感できるきょうこの頃です。」
青森では春の訪れのことを「暖気してきた」というのですね。まず空気や空の感じから長い冬の終わりをいち早く感じる実感のこもった言葉です。
しかしやわらかくなった雪も車にとってはかなり曲者です。どうぞ皆さん、交通安全をこころがけて下さい。春はもうすぐそこまで来ています。
お釜の引退式
2005年03月03日(木)
本日2005年3月3日をもって我が家の電気釜に引退してもらうことにしました。思えばこのお釜は我が家の二人の子どものご飯を炊いてきた偉いお釜です。お釜さん、い、お釜様と呼ばなければいけないかもしれません。なんでご飯を食べないんだろうと不安になって保育園時代から、なんでこんなに食べられるのだろうと呆れた中学生時代、さらにさらに、せっかくご飯を炊いたのに帰ってこないじゃないか!の大学まで、せっせっとよくご飯を炊いてくれたお釜さまでした。
最近は寄る年波には勝てず、保温状態にしておくと中のご飯は黄色くかりかりぼろぼろになるという状態が続いておりました。
お釜様には本日、最後の仕事としてひな祭りのすしご飯を炊いていただきました。
ひな祭りのおすしはなぜかお野菜だけで作るものとおそわっています。かんぴょう、きぬさや、はす、しいたけ、にんじん。例外は金糸卵です。なまぐさは入れないのがひな祭りのおすし。
お釜様はこのお野菜のおすしのためのご飯を無事炊き上げてくれました。パチパチパチ。拍手です。
お釜様、長い間どうもご苦労さまでした。おかげで我が家のチビどもも立派な大人(いささか疑問もあるが、お釜様の担当部門の体格の点では疑問なし)になりました。どうもありがとう。
↑前のページ / ↓次のページ
|