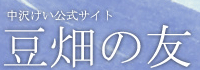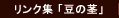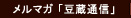|
|
 |
 |
| |
|
| |
「源氏物語」白石加代子朗読会
2005年04月29日(金)
浜町の明治座で開かれた白石加代子の「源氏物語」朗読会に行ってきました。連休初日。とても風の気持ちの良い日でした。明治座はいっぱいのお客さん。朗読は途中休憩を挟みますが、四時間以上。舞台は白石加代子のほかは、黒子がひとりいるだけ。
「源氏物語」の中から須磨、明石の章に末摘花の章とその末摘花との再開を描く「関屋」などで構成された朗読です。源氏物語がどのような物語であるかを大きく骨格からつかめるうまい構成でした。景色や拝見などは色とりどりの扇で表現されていて、物語の進行にしたがって黒子が次々と舞台上の位置を変えてゆきます。またこの扇がまるで落語家の扇子のような様々は小道具の役割を果たします。
朗読というよりもかなり一人芝居に近い感じでしたが、やはり白石加代子はすごい迫力です。とくに怨霊の声などは女性の声なのに低音の白石さんの声がぴったりでした。で、ここまでは最近の流行語で言うと想定の範囲内。予想外だったのは、外見のみすぼらしさにはまったく無頓着な末摘花のかわいらしい声を出す時のなんともいえない優雅さでした。高い声というだけではく、なんというか、その無頓着で、飢え死にするか凍死するかにもおかまいなしというお姫様のそらおそろしいほどのかわいさが声に出ているのです。
最後に黒子さんが女性の俳優さんであることがカーテンコールの時にわかり、以外な楽しさを添えていました。連休はDVDを見て過ごします。太平洋プロジェクトさんから教えてもらったフラソワ・オゾンの「8人の女たち」をまず見るつもりです。こちらは白石加代子にも負けない大迫力のフランスの女優さん勢ぞろいという映画です・
スタッフ・ルーム開放
2005年04月29日(金)
ゴールデンウィークが始まりました。と言ってもまだ真夜中ですが。
本日から5月5日までスタッフ・ルームをパスワードとIDなしで入室できるようにします。皆様の書き込みをお待ちしています。
それにしても28日は暖かでしたね。緑色の葉が出た桜の木の下を歩いていると、とても愉快でした。
訃報
2005年04月28日(木)
パック・イン・ジャーナルの総合プロデゥサー神山啓二さんが23日(土)にお亡くなりになったというご連絡をいただきました。突然のことに驚いています。
パック・イン・ジャーナルは生放送の番組で4月9日に出演したときも神山さんにお目にかかっています。ご病気とは想像できないお元気なご様子でした。土曜日といえばパック・イン・ジャーナルの放送日です。23日は御加減が悪いとのことで、神山さんはお休みだったそうです。なくなられたのはその晩ということでした。
この番組は放送終了後の雑談がおもしろ時があって、その時に神山さんの見方や感じ方を伺うのお楽しみでした。神山さんにお目にかかるのが楽しみで、苦手な午前中の放送に出かけるというようなこともあったので、たいへん残念です。まだ実感が湧かず、ご冥福をお祈りすると言う気持ちにもなれていません。
代々幡斎場のお葬式に伺いました。ご冥福をお祈りします。(4月29日記)
I GO TO金沢八景
2005年04月27日(水)
叔母や叔父はいまでも京浜急行の金沢八景周辺に住んでいます。京浜富岡と金沢文庫の叔母を誘って、母の(叔母たちから見れば姉)お墓参りに行ってきました。が、連休前で大渋滞。都内の環八が混雑するのは毎度のことで驚きませんが、なんと東名も横浜町田のインター手前から渋滞。そのさきの保土ヶ谷パイパスはまったく動かず、自宅を出てから京浜富岡まで5時間もかかってしまいました。夜なら一時間に道です。27日のことです。
さらに間抜けなことに富岡の叔母の家を探すのに一時間近くも費やす始末。子どもの時から何度も尋ねている叔母の家ですが、その頃はまだ住宅造成されたばかりで今とは少し景色が違います。三島由紀夫の「午後の曳航」の最後に出てくる富岡の場面は、ちょうど叔母の家が富岡にできた頃を描いています。山が切り崩され、更地が階段状に並んでいる住宅地です。
山を造成してできた住宅地も40年近くの年月が過ぎると再び樹木が大きく育ち、生い茂り、家々を取り囲むようになっています。生きているものの力はすごいなあと思うのですが、住宅造成地はまた山に戻り始めているのです。もちろん家は新しく建てられたり改築されたりしていますが、それ以上に自然は修復力を発揮しているようです。叔母の家の庭には3匹のヒキガエル、それも巨大なやつが住んでいたり、ハトの雛を3羽も飲み込むほどの大きな蛇がすんでいるという話でした。住宅造成のためにいなくなってしまったと思われた動物や植物がいつのまにか戻ってきてきるようです。
そんなわけで、子どもの時に見慣れていたはずの景色がすっかりかわり、車で出かけた私は大慌て。叔母は叔母で、私の車が階段状の造成地を上へ行ったり下へ出たりしながら、なかなか家の前にたどりつかないのを、はらはらしながら眺めていたそうです。
久里浜からフリーで房総の金谷へ。金谷からはできたばかりの東関東自動車道館山線であっと言うまにお寺のある館山まで飛ぶような速さでした。新しくと言ってももう開通して数年になりますが、まだ造成のあとが残る高速道路を走るたびにサルになってような気分がします。だって、そのあたりはサルが木の枝から枝に飛びうつりながら移動する以外に、通るものがいなかった場所ですから。
I COME FROM 横須賀
2005年04月25日(月)
スタッフ・ルームでキャンデーズと山口百恵が話題になっています。もとはと言えばカラオケでどうしても京浜急行の歌としか思い出せないという山口百恵の歌があるという話題を出したのです。
それが「I COME FROM 横須賀」です。とのくんの友人さんによると「生まれ育った土地を思い出すという理由で自分の歌った歌の中で一番好きな歌だ」と山口百恵自身がテレビで言っていたそうです。
I COME FROM 横須賀
横須賀から汐入、追浜、金沢八景
金沢文庫
汐風の中 走ってゆくの
赤い電車は白い線
駅の名前をソラで言えるの
横須賀マンボ・Tシャツね
I COME FROM 横須賀
あなたに会いに来た
I COME FROM 横須賀
あなたに会いに来た
文庫をすぎて上大岡、井土ヶ谷
日の出町 横浜まで
窓を開ければ 緑が飛ぶの
快速特急 音たてる
扉の近くに陣取りながら
呪文のようにつぶやくの
I COME FROM 横須賀
あなたに会いに来た
I COME FROM 横須賀
あなたに会いに来た
横浜から鶴見、川崎、品川
ここまでの道
小さな屋根が 集まっている
歴史のあとも あるけれど
あいにく私は 詳しくないの
心は走る線路なの
I COME FROM 横須賀
あなたに会いに来た
I COME FROM 横須賀
あなたに会いに来た
この歌はずっと横須賀恵のペンネームを使った山口百恵自身の作詞だと思い込んでいたのですが、調べてみると阿木洋子作詞宇崎竜童作曲でした。すごくべたなメロディであんまりはやらなかったのですが、私は金沢八景の生まれなので「ああ、きっと文庫で特快に乗り換えたんだなあ」なんて思いながら聞いていました。
と言うわけで4月29日から5月5日までスタッフ・ルームにパスワードとIDなしで入れるようにします。どうぞお遊びに来て下さい。
靖国神社参拝と郵政民営化
2005年04月24日(日)
小泉政権のアキレス腱は、外交政策にあるようですが、ここまではなんとか切り抜けてきました。これまで郵政民営化と靖国神社参拝を結びつけて考えたことはなかったのですが、ここへ来て「ああ、なるほど」と思うようになりました。
郵政民営化をするために、どうしても国内の保守派の心情を掴んでおく必要があったのでしょう。その象徴が小泉首相の靖国参拝であったというふうに見えてきました。新聞では郵政民営化は骨抜き法案だと書かれていますし、先週、東京新聞の政治部の記者とお話した時も、ともかく反対したというジェスチャーをとる必要が議員にはあるんだという話でした。裏を返せば本気で反対する気はないということになります。
しかし、どうもそういう政治部記者の見方にうなずけないところもあるのです。確かに民営化法案は骨抜きですが、骨なんかなくたって、直截に言えば郵政縮小解体法案です。二年前の公社化が民営化で、今度は縮小解体の法案だということは、郵政関係の職場で働いている人には直感的に理解できているのではないでしょうか?だとすればけっこう本気で反対する可能性もまったくないわけではないでしょう。
私自身は郵政縮小解体は止む終えないと考えています。大きなお金の流れを公共投資型から民間投資型に変えなければ、日本はやってゆけないところまで発展してきたからです。ここの理屈がどのくらいの国民的コンセンサスを得ているのか、新聞やテレビ報道だけではよく解らないところがありますが、しだいしだいに理解はされてきているのではないでしょうか?
バンドンの日中の首脳会談は対話の再開と促進という結論で終わりました。どちらの首脳も相手を追い詰めなずに振り出しに戻るという形に収まったというところです。いずれの国も国内に解決しなければならない事柄が進行形で存在していることをひしひしと感じさせる会談だったのではないでしょうか。
三色スミレ冬を越える
2005年04月23日(土)
12月になると三色スミレ、とくに花の小さなタイプの苗が出回ります。春の花を先取りするように花をつけた苗が売られているのですが、なんとなくヘンな感じがしてあまり買う気になれなかったのです。が、花屋さんに聞いてみると冬の間に苗を植えておくと、根ががっちり張るのだそうです。そういう冬を越えた株は、春になるとどんどんと大きくなって、夏の初めまで花を付けるということでした。
なるほど。なるほど。なるほど。
物は試しといいますから、試してみました。
冬を越えた三色スミレは今、伸び盛りでどんどん育っています。蝶々のような花も次々に咲きます。人間の経済活動や芸術の分野もおんなじようなところがあるのかなと妙なことを考えました。親しいよもだちと日本映画の話をしていて、このごろ見ていてすごく楽しい映画が出てきたという話題でおおいに盛り上がりました。「だめだ、だめだ」って言われていた時期は、きっと映画も根を張っていたに違いありません。
ホリエモン勝ったか負けたか
2005年04月20日(水)
フジテレビとライブドアが和解しました。ホリエモンが勝ったか負けたかで、テレビは賑やかですが、わりに安い買い物をホリエモンはしたのではないでしょうか?
この騒動の勝敗という点ではフジテレビとライブドアの業務提携を話し合う委員会が機能するか否かで結果が変わって行くでしょう。株の買い取り合戦のような派手なことは起きないでしょうから、あまり大きく報道されることはないかもしれません。しかし、ほんとうの激しい変化は、そうした地道な作業が進むことで起きるのです。いつのまにか、気がつかないうちに、ガラリと変わっていたということになるのです。
テレビを中心としたメディアのあり方はおそらくこれを境に急激に変化して行くことは間違いありません。
何が変わるかと言えば、もっとも大きく変化する可能性があるのはコマーシャルの料金でしょう。スポンサーのあり方にも大きな変化が出るに違いありません。付随して視聴率というものの考え方調べ方にも変化が出てくるでしょう。なぜ、そう思うのかと言えば、それはネットの性質がこれまでのメディアと異なるからです。
ネットは高い検索機能を持っています。また個別の対応を得意とします。さらに、双方向性を持っています。いずれもテレビが苦手として機能です。メディアの中では一番古い活字の世界も、書籍、雑誌の流通が激変期を迎えることになるでしょう。ネットとテレビの結びつきは、視聴者や読者に目に見える形の変化を呼ぶというよりも、その収益を出すシステムの変更を迫るのではないかという予想を私は持っています。
賑やかな仁王様
2005年04月19日(火)

韓国の仏石寺に行った時の写真です。日本風に言えば山門にたっていた仁王様ですが、このお寺の仁王様は左右に二人づつ、四人もいました。しかも極彩色。白髪のこの仁王様はなぜか琵琶を弾いて歌を歌っているみたい。ええと、「豆蔵通信」の主の豆蔵君に似ているような似てないような、そんな感じです。
水田三喜男の生家
2005年04月18日(月)
房総に行ってきました。鴨川市の山へ入ったところにある水田三喜男の生家を見てきました。水田三喜男は1960年代に佐藤内閣の大蔵大臣などを勤めた政治家です。高度成長期の通産、大蔵大臣で、高度成長政策の中心的な人物の一人です。その生家は安政年間に建てられたものだそうです。浦賀沖に黒船が現れたころですが、きっと家を建てている最中には幕府がなくなるとは思っていなかったでしょう。
房総はもともと酪農が盛んな土地ですが、水田家は日本で最初にホルスタイン種の牛を飼育した家だそうです。ホルスタイン種の牛を飼ったのが水田三喜男のお父さんでした。そのあたりは曾呂村というのですが、江戸時代には毎年5月に「馬捕り」で賑わったといいます。さて「馬捕り」とはなんでしょう?どうも文脈から判断すると馬の市のような気がしますが・・・。
大きな長屋門の左右には牛のための部屋(牛小屋)がありました。水に乏しい場所で、飲み水は遠くの湧き水を汲み、そのほかの水は母屋の裏にあるため水を使っていた様子です。水をためる四角い池のそばに水神様がまつってありました。なかなか暮らして行くのが容易でない土地です。それほど裕福な家にはみえませんでした。長屋門は客間を持つ家にしては質素なくらいです。しかし、この家は西洋種のホルスタインを飼育する決断をした時にある程度の経済的な基盤を築くことに成功したのでしょう。日本の酪農発祥地と言われる嶺岡牧場のすぐ近くで、嶺岡牧場にもかかわりがあったかもしれません。黒船が来なかったら、水田三喜男も寂しい山里の牛飼い馬飼いの三男坊で生涯を終わったかもしれないと考えてみると、歴史の巡り方は不思議なものだと思いました。
以前、ここに紹介した仁衛門島の仁衛門屋敷が海の交通を担った人々の元締めのような存在であったとすれば、水田家のほうは、陸の交通に大切な牛や馬などを生産していた人々の元締めみたいな家だったのでしょう。
房総では田のしろかきが始まっていました。しろかきを終えて新鮮な水が流れ込んだ田では、もう田植えを始めているところもありました。
↑前のページ / ↓次のページ
|
| |
|
|
|
|
| |
|
| |
|