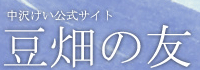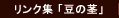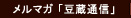|
|
 |
 |
| |
|
| |
街路樹の値段
2005年05月24日(火)
2005年1月22日の東奥日報に以下のような記事がありました。
「街路樹2本切り倒される/青森」
「青森市浜館二丁目の市道に植えられた街路樹二本が、何者かによって根元からバッサリと切り倒されているのが二十一日までに見つかった。青森署が器物損壊事件として捜査している。
切り倒されたのは、はまだて公園西側にある浜館通り線(通称アオギリ通り)に植えられた高さ六メートル、直径十五センチの街路樹「アオギリ」(市価一本一万八千円程度)。切断面の八割程度にノコギリの歯の跡がついていた。二十日午後一時ごろ、市民が発見し、青森市に通報。市が二十一日午後、青森署に被害届を出した。」
今年の青森は記録的な豪雪でした。雪の中でのこぎりを使って高さ六メートルの木を切り倒すのは容易な作業ではないでしょう。なぜ切り倒したのか?それはこの記事だけではわかりません。雪で道が狭くなったので、腹立ち紛れに切り倒したのでしょうか?
私がこの記事を保存してあったのは、市価一本18000円というところに注目したからです。街路樹ってどのくらいの値段がするものなのかしらとかねがね思っていました。荒っぽい伐採で、枯らしてしまった街路樹の値段が知りたかったのです。樹木の種類や大きさにもよるかもしれませんが、ひどい伐採で枯らしてしまった場合にはそれだけの損失をこうむっているということになります。ひどい切り方だと嘆くと情緒的な事柄だとないがしろにされるのですが、街路樹にもちゃんと値段があって、故意に伐採すれば器物損壊の罪に問われるのです。
電動鋸でいい加減なきり方をした木に痛々しさに比べれば、雪の中で苦労して自分の手で鋸を使って切り倒したこの事件の犯人がなぜか「偉く」見えてしまいます。
これがえごの木です。
2005年05月23日(月)

満開になったえごの木はほろりほろりと星型の白い花を散らせます。崖の上から崖下の道に滝のようにしだれているえごの木の下を歩いて出かけるのがほんとうに楽しみです。桜はみんなで大騒ぎするのにこんなに見事に咲いている花が頭の上にあるのにも気付かずに急いでいる人を見るとおかしいやら、さびしいやら、へんな気がします。
インド料理屋
2005年05月22日(日)
たいていの人はカレーが好きですが、日本人が好んで食べているカレーは、インドからイギリスに伝わってシチュー風に変化したものを、今度は日本で洋食の一種にアレンジしたものだそうです。カレーってほぼ地球を一周してしまったお料理なんですね。
が、本格的なインド料理の評判をいまひとつ。デリーに中華料理屋はできても、北京にインド料理屋はできないなんて言う人もいます。確かにカルカッタにもデリーにも中華料理屋さんはたくさんありました。で、カレー味にあきたら中華料理屋さんに行けばいいというインド旅行のコツを教えられました。
最近、銀座でインド料理の店を二軒も見つけてしまいました。一軒は銀座一丁目です。で、入ってみました。一人で。インド人?らしきコックさんがガラスの向こうでナンを焼き、タンドリーチキンを焼いていました。暑い国で、いかにお腹をこわさないか、いかに消化の良いものを食べるか、そして食欲を刺激するかという工夫をしたお料理です。たまに食べたくなるのです。おいしかったのですが、なんだか洗練されすぎているような気がしました。
最後にマンゴウジュースというメニューを見つけて「甘いのですか?」と質問すると「ええ、とても甘いジュースです」という答えが返ってきたので、注文するのをやめました。カルカッタで飲んだ塩辛いマンゴウジュースが飲みたかったのです。そんなものって、誰もそのおいしさを認めてくれないのですが・・・。かわりにマサラ茶を飲みました。店の奥ではインド人らしき身奇麗いなグループでおいしそうに食事をしてました。
インド料理屋の裏に回るとなぜかチャンドラ・ボースビルというビルがありました。チャンドラ・ボースというのはインドの偉い人だったような気がするのですが、どうしてもどんな人か思い出せません。どなたかご存知でしたら、教えて下さい。なぜ銀座一丁目にチャンドラ・ボースビルがあるのかも解らないのですが、もっと不可解なものを目にしました。
そのビルには「海女」というキャバレーが入っているのです。たぶん「あま」と読ませるのでしょう。で歌やダンスなどのショーを見せる本格的な実演(おお、おっそろしく古式ゆかしい言葉だ、今はライブって言わなくちゃね)を見せるキャバレーのようです。海辺の町の歌手兼踊り子がひとりしかいないような寂しいキャバレーなら「海女」でも解るのですが、いったいどういうセンスで命名したのだろうとしばし「?」でした。「海女」とチャンドラ・ボースの組み合わせになるとますます奇妙でした。
赤く咲くのは芥子の花
2005年05月21日(土)
赤く咲くのは芥子の花って昔、藤圭子が歌ってました。歌田ヒカルのお母さんって言ったほうがいいんでしょうか。で歌は「どう咲きゃいいの この私」って続くのですが、それはさて置いていて、今年の路傍でずいぶん芥子の花を見かけます。ここの管理人豆蔵ことながしろばんりさんのホームページでのそれに触れていました。ながしろさんのホームページの芥子の写真があります。
芥子は麻薬の原料となるので栽培が禁止されています。藤圭子が芥子の花の歌を歌っていた頃はまだそういう法律がなくて、私が小学生の頃に栽培が禁止されました。昭和40年代前半です。で、芥子にもいろんな種類があって、駐在所の掲示板に芥子の種類を解説したポスターが張ってありました。植物図鑑みたいできれいなポスターで、指名手配や行方不明のポスターといっしょにならんでいると絶大な違和感がありました。
私の家の庭にも大きな芥子の株があったのですが、その法律ができたので、根こそぎ引き抜いたのを覚えています。最近、街で見かける芥子は小型のひなげしの類いですが、これも確か麻薬の原料になったような覚えがあります。園芸種のポピーなどは麻薬の原料にはならないのですが・・・。それにしてもどうしてこんなに芥子の花があっちこっちに咲いてしまったのでしょうか?
どんな花なのか見たい方は、リンクページからながしろばんりさんのホームページにどうぞ。
ながしろさんは芥子の栽培が禁止されてからこの世に生まれ出てきたので、芥子の花をみたことがなかったようです。
えごの木花盛り
2005年05月19日(木)
「うのはな」というのは、特定の花をさすのではなくて、5月から6月にかけて咲く白い花の総称だと聞いたことがあります。「うつぎ」という白い花を咲かせる木が「うのはな」だという人もいます。
どちらがほんとうなのか解らないのですが、いずれにしても5月から6月にかけては白い花の木が目立ちます。水木は小さな傘のような花を咲かせていますし、えごの木は鈴がたくさん付いたような花をいっぱい開いています。家の近くの斜面に大きく育ったえごの木があります。えごの木は往来のほうへ枝を張り出しています。昨日の風が強くて、しろい花がほろりほろりと散っていました。
江戸時代には所沢がこうした「うのはな」の名所だったのだそうです。水田の少ない台地で、雑木林が多かったのでしょう。桜ばかり見ていたわけではなかったようです。
交渉人 真下正義
2005年05月18日(水)
「踊る大走査線」シリーズのから出た「交渉人 真下正義」を見てきました。月曜日の新宿コマ劇場、最終上映。やっぱりアベック(ふるいことばだ)が多いです。客席は七割り程度の入り。
映画はずばり言ってこのシリーズの中ではいちばんおもしろかったです。国村隼や寺島進と言った映画俳優といえる俳優さんが加えて見ごたえがありました。爆発物処理班の松重豊もよかったし、小泉孝太郎もなんだか大人っぽくなっていました。それから群集シーンがお金がのかかった映画だなあと思うくらい迫力がありました。あと空撮もいいなあっていうシーンがたくさんありました。そういう役者の出てこないシーンで、東京の暮らしも悪くないと、いや、もっと積極的に東京をいとおしいと思わせておいて、だから地下鉄や都市を犯罪から守ろうとする登場人物の気持ちに厚みがでるという構成でした。
個人的には小泉孝太郎がちょっと好きになったかな。これまでは「あ、出てる」くらいの印象しかなかったのですが。それから、寺島進がボレロを演奏している最中のシンバルの奏者を後ろから羽交い絞めにするシーンでは思いっきり笑ってしまいました。表情がいいんで。
歌舞伎町に足を踏み入れたのは久しぶりでした。
今夜は異様に重い
2005年05月15日(日)
はて、さて、どうしたことか。今夜は異様なくらいにページを開くのが重いのです。管理人さん、何かしている?って聞いてもダメか。回線が込み合っているのでしょうかねえ?
「豆の葉」も、もうすぐ200回。一年で200回というのは多いのか少ないのか?わかりません。200回記念にひとりでケーキを食べようかな!銀座のダロワイヨのtokyou-parisがいいなあとか考えちゃってます。
以前はネットって言ってもなかなか繋がんないときがあったのがうそみたいにこの頃は軽々と接続できるようになりました。
怒りは貴重な感情
2005年05月14日(土)
小川国夫さんが藤枝から東京におこしになっていると言うので、少し夜遅かったのですが、お目にかかってきました。で、あれこれととりとめもなくお話するうちに以前、岩波文庫で「ゲーテ箴言集」というのが出ていたという話になりました。岩波文庫の箴言集は何種類かがあったように記憶しています。
「ゲーテ箴言集」の中に「怒りは貴重な感情だ。だから節約して使わなければならない」というのがあると小川さんから教えてもらいました。少し前のことですが、家の息子が「おかあさん、犬の無駄吠えって知っているだろう。それとおんなじで無駄怒りを止めてもらえないかな」って言っていたのを思い出しました。もちろんゲーテの震源のほうが、怒っている人を尊重している点で立派です。
「ううん、その貴重な感情を惜しげもなく使っているのが解らんのかって言っても通じないかな?」と小川さんに言うと、例の小川さん独特のゆっくりした口調で「通じません」と笑っていました。
今朝、息子にゲーテの震源を受け売りすると、彼はさっそく前段を忘れて、後段の「節約するように」ばかりをさかんに連発していました。
こらっ!貴重な感情なんだぞ、大切にせんかい
おでかけ三種の神器
2005年05月13日(金)
財布と鍵と携帯電話。これが近頃のおでかけ三種の神器です。どれを忘れても困ってしまうのですが、おとといは携帯は置き忘れるは、鍵は家に置きっぱなしのまま出てしまうはで、さんざんでした。どうも家に人がいるときが危ない。とくに鍵を持たずに出てしまうのは決まって家に誰かいるときです。
出かける時は息子が家にいたのですが、帰ってみると家は誰もいません。で、かなり夜中近い時刻になっても息子も娘も帰ってきません。どうかするとそのまま家に帰らない日もあるので、日付が変わらないうちにどこかホテルに泊まるというような決断をしなくちゃならないかなと考え込みながら、駅前のコンビニで時間をつぶしていました。いつのまにか、公衆電話の数が激減したので、電話のあるコンビニで時間をつぶしていたのです。
そこへリュックサックを背負った娘がふらふらと入ってきました。思わず、リュック・サックをむんずと掴んでしまいました。聞けば、一度、家に帰ってこれからともだちの家にでかけるところだということでした。どうも私が公衆電話から家に電話をかけたのは、彼女が家に戻る寸前と、家を出てからだったみたいです。やれやれ。彼女がともだちの家での飲み会へ持ってゆくおつまみを買おうとしなければ、危うく一晩家から閉め出されるところでした。結局、息子のほうは帰ってこなかったのですから。
で、息子曰く「携帯を忘れちゃだめだよ」
お前さんが帰ってこなかったのがそもそも、まずいのだろう。ぷんぷん。どこをほっつき歩いていたんだ。
線を愛好する
2005年05月12日(木)
連休中、和辻哲郎の「古寺巡礼」を読み返していました。3月に奈良に旅行したときに思い出したです。で、その中に日本画に発展する「線」に対する愛好という話が出てきます。「面」ではなくて「線」で絵を描くという好みが天平の頃にすでに生まれていて、それがやがて繊細な「線」に対する感覚を生み、絵画の「線」を愛好するようになるという考察です。
で、そういえば漫画もかつての日本画が持っていたような「線」にたいする好みの感覚が働いているなあというようなことを思い当たりました。現在の漫画についてはほとんど知らないのですが、30年前に竹宮恵子などが出てきた時、それまでの少女漫画とはまったく違う「線」を持った絵が魅力的でした。今、思うと、その頃に次々と出てきた漫画というのは、手塚治虫の漫画の「線」とはまったく違う、そして多様な「線」を持った作家が登場してきたのだなあと、今までとは違う角度からその頃の漫画のことを考えてみました。
「サザエさん」も初期の頃、昭和20年代は「線」ではなくて色を塗りつぶすかたちの絵で描かれているのです。それがしだいに単純化された「線」になって行きました。前々からどうしてそういう変化をしたのか不思議に思っていたのです。(私は小学生の時、バス通学をしていて、毎日、駅前の松田屋書店で「サザエさん」を立ち読みで一巻ずつ読んで、とうとう全巻、読み終えてしまいました)で、あれは「線」に対する読者の好みに作家が答えた結果だったのかと、何かがわかったような気がしました。
日本画のほうは朦朧派なんて悪口まで出るような感じで「線」ではなく「面」で描くという方法が近代になって出てきましたが、もっと大勢の人の目に触れる部分で、例えば漫画のようなジャンルで、古くから根を張ってきた美意識の好みが出てくるというのは、おもしろ現象です。漫画というのは、従来の大人文化と一線を画す若者文化として論じられることが多かったのですが、表現の基礎的な部分でかなり時代を遡ったものと繋がっているのを発見したような気分です。
↑前のページ / ↓次のページ
|
| |
|
|
|
|
| |
|
| |
|