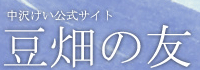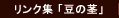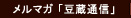原稿用紙5
2005年06月06日(月)
仙台文学館で公演してきました。その帰りに山形の上山にある斎藤茂吉記念会に寄ってきました。仙台文学館では与謝野晶子展が開かれています。与謝野晶子展でも斎藤茂吉記念館でも気になるのは原稿用紙!
与謝野晶子も斎藤茂吉も現在と同じ型の20×20の原稿用紙を使っていました。明治40年代にはこうした形式の原稿用紙が使われるようになっているようです。
「超漢字原稿プロセッサ」の開発段階では20×20の字つめで縦書きができるというのは基本的な条件でした。20×20だと、分量の目安を掴みやすいからです。しかし、その時は桝目にはそれほど感心を払ってはいませんでした。ワープロで桝目のあるものが使いにくかったので、桝目はいらないという考えもありました。私もどちらかと言えば、桝目はいらないのではないかと思っていました。
ところが、その後、桝目にも意味があるんだということに気付かされる事件がおきたのです。某大学の卒業制作の字数を20×20の原稿用紙何枚というふうに数えずに、純粋に字数でカウントするというウワサが流れて、詩の製作を考えていた学生がまっさおな顔で相談に来ました。詩は空白も表現のひとつです。いや、詩だけではなく散文でも、どこで一行アキを入れるか、カギカッコの下を空白であけるか、それともそのまま文章をつなげて書くか、これも表現の一部分です。
ワープロやパソコンがなければ、提出された卒業制作を純粋に字数で数えてみようなんてことも考え出さなかったでしょう。で、その話が伝わってきた時、遅まきながら原稿用紙の空白も表現の一部だと気付いたのです。
つまり桝目にも意味があるのです。
原稿用紙の桝目が必要かどうか侃々諤々の議論の結果、どちらも選べるという方式に落ち着きました。が、その時の議論を思い出すとぶんに感覚的で、欲しいか、欲しくないか、好きか嫌いかに終始して、原稿用紙の桝目の意味などには及んでいませんでした。
物書きの手近にある紙は原稿用紙ですから、斎藤茂吉も原稿用紙に手紙を書いています。気楽な手紙の用紙として原稿用紙を使うときは、斎藤茂吉も桝目を無視して使っています。書簡の時の書き方(正書法)をしているのです。これまでなんどもいろんな文学館を訪れることはありましたが、こんな興味で展示を眺めたのは初めてでした。資料というものは、何かひとつの目的だけで、見られるとは限られないのですね。
原稿用紙4
2005年06月04日(土)
ふだん、原稿を大量に書いている人でも、たとえば学者や研究者のような人でも、原稿用紙が正書法を支えてきたのだということをあまり意識していないことに最近、気付きました。むしろパソコンやワープロの便利さのほうが目を引くのは当然のことです。
ところで、ある時期まで、大学でレポート提出について説明するすると、必ず「手書きですかワープロでもいいですか」という質問がありました。その次は「縦書きですか、横書きですか?」という質問が出ました。レポートは手書きの縦書きのみしか受け付けないという先生が文学系の授業には、かなりいたようです。
最近はレポートは「ワード」で製作したものしか受け付けないというふうにアプリケーションまで指定する先生もいます。レポートの内容にもよるでしょうけれども、アプリケーションまで指定してしまうのは、あまり感心しないなという気がします。ここ数年で、手書き縦書きのみという指定から急速にアプリケーションの指定まで変化してきているのです。世の中全体で原稿用紙を使っていた経験が急速に薄らいできているのです。
正書法の混乱とか乱れという問題が生じてくるのは、原稿用紙を使った経験が乏しくなってからでしょう。もともと活版印刷導入といっしょに自然発生的に出来たものだから、使う道具の変化とともに変化してもいいと考えるか、ここで正書法を整備して、無闇な変化を防ぐほうがいいと考えるか議論の分かれるところでしょう。
原稿用紙3
2005年06月03日(金)
丸谷才一さんの話を書いたら、その丸谷さんから新著を頂戴しました。「綾とりで天の川」(文芸春秋刊)です。また烏帽子大紋のお礼状をで大騒ぎなんてことはないのですが、偶然の符合が「うふふ」でした。
書簡体も明治の頃から比べればずいぶん変化しています。夏目漱石の「それから」で大助が兄嫁に口語文の手紙を書いたらどうですかと勧めていますが、その頃はまだ手紙は候文で書くのが当たり前だったのでしょう。
手紙の文章やその書き方の決まり(正書法)も活字化を前提にした原稿用紙の書き方にしだいに影響を受けて現在のような形に変化してきました。ただ、多くの人は自分の書いた文章が活字になることなどはないので、あまり原稿用紙の書き方などは意識しません。さらに言えば手紙の書き方がだんだんに、筆で書く文語文の正書法から鉛筆や万年筆で書く原稿用紙の正書法へ変化したことなどまったく見落としているのです。
手紙は苦手だなあと感じている人はたくさんいて、電話が出てくると、かなりの用事が電話で済むようになってしまいました。そこにファックスが出てきて、さらに電子メールが登場して、追いかけるように個人のホームページやブロクが登場してきました。で、原稿用紙は過去の産物ということになるのかもしれませんが、原稿用紙が作った日本語の正書法はどうなるのでしょうか?
ワープロが出てきてから、文章の段落の頭を一文字分空白にするという決まりが相当に無視されるようになりました。名前の知られた大出版社の発行する雑誌でもそうした様子が見られます。また、この文章のそうですが、段落ごとに一行の空白を作るのは、電子メールが出てきてからの習慣です。まだ決まりというほどではないのですが、かなりの人がこうした書き方を用いています。さらに文頭の一文字を大きくするレイアウトも、以前は雑誌や本などの紙面のデザインであって、正書法とは関係のない事柄でしたが、パソコン画面に直接にそうした修飾を入れることができるとなると、これも正書法のひとつに数えられる時が来るかもしれません。
原稿用紙2
2005年06月02日(木)
なにやら、昨夜はぐらぐらとそんなに大きくない地震が続きました。東京湾が震源とか。大丈夫かな?と不安になります。
「地震で発見。送る。」というお葉書を丸谷才一さんからいただいたことがあります。なんという簡潔さ。服装に例えれば、海水パンツ一丁という感じです。確かにやや大きめな地震のあったあとでした。でも何を発見したのか?送るというのだからそのうち送られてくるだろうと待つこと、一日。金子武蔵「ヘーゲルの国家観」が送られてきました。昭和19年発行の本です。
そう言えば、さるパーティで丸谷さんにお目にかかったとき、その本を探しているというお話をしたのです。
「僕のうちにあるはずなんだけど」と丸谷さん。地震で本の山が崩れて発見したというわけです。発見したので進呈しましょうというお葉書でした。
さて、問題はここから始まります。御先方が海水パンツ一丁の潔さと言え、こちらが「届いた。あんがと」では済みません。なにしろその頃、私は明治大学の学生だったので、服装で言えば烏帽子大紋(忠臣蔵で浅野の殿様が着ているやつ)くらいの礼状を書かなくちゃとものすごく緊張。ううん、困った。困った。手紙ってすごく億劫なものでした。とくに形式を踏まなくてはいけない手紙はもっともっと億劫で、どんどん日が過ぎて行きます。
それはこれまで、事項の挨拶などの形式と候文の血統を引いているような手紙独特の文体のためだと考えていました。どうも、そこに江戸時代から引き継がれている手書きの正書法も混じっていると考え出したのはこのごろです。烏帽子大紋という比喩が似つかわしいのも、そうしたことを考えているからです。
そもそもふだん原稿用紙に書いているのとは違う正書法を用いているとは、考えてもみなかったのですが、例えば段落を分けるなどということも手紙ではあいまいに住みます。段落の文頭を一字空けるのも、桝目がないのですから、とくに考える必要はありません。そのかわりに行分けや、文字の位置に気を配る必要が出てきます。原稿用紙が出来てからも、手紙では、それより古い正書法が脈々と生き残っていたということになります。
丸谷さんへのお礼以上は困ったあげくに「手紙の書き方」という実用本の文例そのままと書き写したものを差し上げたというふうに記憶しています。
原稿用紙1
2005年05月31日(火)
江戸時代の本を見ると木版刷りで、草書のつづき文字が刷ってあります。現在の私たちが目にする本とはまったく異なった正書法を用いています。正書法が大きく変化するのは明治期になって活版印刷が盛んになってからです。現在の正書法は活版印刷とともに整えられてきたのです。
活版印刷が生み出した正書法を支えてきたのは原稿用紙です。原稿プロセッサ開発の時に20×20の原稿用紙にこだわる必要があるのかという議論をした時、吉目木晴彦さんが「印刷のほうの人に聞いたら、20×20は経験的にもっとも安定した字面になる組み合わせだと言っていた」と発言したのが、じゃあ、その方向でというひとつの決め手になりました。
今、考えてみるとあの吉目木さんの発言はその場で考えられていた以上に重要な発言だったと思います。というのは、ワープロやパソコンで文章を書くようになってまた日本語の正書法が大きく変化する可能性が出てきたからです。原稿用紙にこだわる必要があるのかどうかを議論した時にはそこまで大きな事柄とは、私も考えていませんでした。
これは最近、考えはじめたことなので、いささか混乱しているところもありますが、少しづつ書いて行くことにします。
まず最初にワープロを使ったときに困惑したのは原稿というものと、印刷された紙面の区別がぐちゃぐちゃだったことです。文章を書くことを仕事にしているとこれは画然と区別されているものなのですが、ワープロでは区別されてませんでした。よく考えてみると手書きで手紙など書くときは文章を書くという仕事と文章の書かれた紙面を作るという仕事は同じ仕事になっています。だからワープロでもそこがひとつになっているのは不思議なことではないということになります。
ところで、話は変わりますが、明治期の国語教育では作文教育は書簡体と作文体のふたつの分野に分かれていました。作文体では原稿用紙を使ったのかどうか、調べてみるとおもしろいかもしれません。
書簡体の教育が独立してあったのは、私が高校の教育を受ける頃まではまだ続いていました。この話を持ち出したのは正書法と手書きと印刷を考える手がかりがそこにありそうだからです。作文体と呼ばれる文章の正書法は、活字の印刷の発達と結びついて出来上がってきたものだという視点は、まだあまり共通認識にはなっていません。だからあまり注意を払われないのです。が、一方で書簡体というかたちで、手書きの正書法も長く残っていたとい側面があるのでしょう。手紙を書くときには原稿用紙を使いません。だから、なんとなく原稿用紙の持っている意味が等閑視されたのではないでしょうか。
インジゲーター
2005年05月30日(月)
「超漢字原稿プロセッサ2」で様子を見たかったのはインジゲーターなんです。目標の原稿の分量を設定して、どのくらい書き進んだのかを、視覚的にあらわすインジゲーターが欲しいと開発の初期の段階で言ってたのは私です。
原稿は20字×20行の400字原稿用紙で書いてきたのですが、そんなに長くない原稿なら指定枚数を聞いておおよそどんなことが書けるか見当がつきます。で、書いてみるとだいたいぴったりに収まるのです。ただ長い原稿になるとそうは行かなくて、全体の構成を原稿用紙の枚数(実際には紙の厚み)で図っています。で、ワープロだとこの身体的情報がなくなってしまうのです。
だから、せめて視覚的なインジゲーターが欲しかったのです。この望みは雑誌のライターの人にもそう考えている人が多くて、その話をすると興味をしめしてくれました。「超漢字原稿プロセッサ1」ではパーセント表示でしたが「超漢字原稿プロセッサ2」では棒グラフのインジゲーターになっています。
今「ベンちゃんの『誰も知らない』」という短編小説を書いていて(そのタイトルは反則だと言われそうですが)それでインジゲーターの様子を見ています。
ところでここで身体的情報を与えてくれていた原稿用紙ですが「原稿プロセッサ」の開発の段階から20×20の桝目にこだわる必要があるのか否かが問題になってました。で、それが意外なほど重要なのではないかと最近考えるようになりました。このことは続きで書きます。
「超漢字原稿プロセッサ2」では桝目の色と桝目の地の色を組み合わせられるのがうれしいです。最近、文房具屋さんに行っても原稿用紙の種類が少なくなって選ぶ楽しみを奪われていたので、よけいにうれしくなってしまいました。
インストール
2005年05月29日(日)
インストール。なんとなく厄介な仕事だなあと思い込んでしまったのはパソコンを使い始めた頃に何度もこれでエライ目にあっているからです。仕事で使っている機械はあまりいじりたくないのが本音です。で、いつもインストールとなるとぐずぐずしてしまいます。
万年筆だって、今でも「控え」があるくらいなのです。毎日、使っているものが一番良いのですが。もし万が一にも壊れたり紛失した場合のためにセカンドの万年筆を用意してあって、日記とか個人的な書類はセコンドの方で書いています。そうすると仕事用の万年筆に何かあった場合も、すぐにセカンドが使えるからです。
じゃあ、パソコンもセコンドを用意するかということになって昨年、ノートブックパソコンを一台購入したのですが、結局、これはまだセコンドというほどにはなっていません。さあ、今日はインストールするぞ!なにが起きても驚かないぞって一大決心がいるんです。
でもたった3分でできちゃいました。「超漢字原稿プロセッサ2」のインストール。まさか坂村先生の神通力?なんてことはないか。「超漢字原稿プロセッサ1」よりもずっときれいにな画面に大感激。「超漢字原稿プロセッサ2」でバージョンアップされた機能のなかにどうしても確かめておきたいものがあったのです。
パーソナルメディアの皆さんお騒がせしました。ご配慮ありがとうございました。自力で(というかすごく簡単に)インストールできました。これから、「超漢字原稿プロセッサ2」の感想お送りします。今、来月(8月号)の新潮(編集長がうんと言えばですが)の短編小説「べんちゃんの『誰も知らない』」を書いています。ベンちゃんってあの「楽隊のうさぎ」のベンちゃんです。今回は推敲機能もうんと使ってみようと思います。(実はこれまでは推敲は紙に打ち出して赤鉛筆でやってました)
坂村 健
2005年05月28日(土)
久しぶりに坂村健さんにお目にかかりました。一年ぶりくらいかな。お元気です。いつもお会いするたびにすごいエネルギーだと、なんだか圧倒されてしまいます。
来月創刊される「表現者」で、「道具と仕事と眼」という連載を始めます。創刊号は陶芸家の角りわ子さんにお話を伺いました。道具を作る人にお話を伺って行こうという連載です。コンピュターは「道具」ということで第二回目は坂村さんのお話を伺いました。お話の内容は「表現者」のほうでご覧下さい。と言ってもまだ昨夜の今日で、原稿は書いていないのですが。
で、その原稿では書けない話。坂村先生、パーソナルメディアの皆さんや、トロンに関係した皆さんがそう呼んでいて、その発音がほんとに親しみがこもるので、なんとなく私もそれに習うようになってしまいました。その坂村先生は食べることも飲むこともお好きで、ワインがお好きで、食べながらお話することがお好きで、なんだか地球が3倍の広さになるような気がしてくるから不思議です。よくネットによって世界は狭くなったという話を聞きますが。坂村先生とお話をしていると、コンピュターは世界を広くするという感じがします。
最後はコンピュターを愛しているんだというお話になりました。だから、コンピュターの悪口を言われるとつい頭にきちゃうということで、その気持ちはコンピュターの苦手な私にもよく解ります。たぶん、この「愛している」というのが、世界を広くしているいちばんのミナモトなのではないでしょうか。「愛している」というのは単なる感情ではなくて精神(スピリッツ)の核心にある燃える火みたいのものとか、なぜか坂村先生とお話をしているとぼんぼんいろんな比喩が私の頭の中に飛び交うのです。自分の頭が良いというだけの人は世の中にたくさんいますが、話すだけで人の頭まで良くしてしまう人はそんなにたくさんいません。
悪意を感じる
2005年05月27日(金)
練馬区におすまいのNさんからお手紙をもらいました。昨年、読売新聞に書いた「樹木受難」という随筆の感想です。半年以上前の記事にお手紙をもらうというのは珍しいことです。が、この随筆は時々、お手紙をいただくということがもう半年も続いています。
街路樹や庭木の伐採については眉をひそめている人が大勢いるけれども黙っていることが多いのだなあと思います。読売新聞の随筆では内容について担当者と打ち合わせをしています。その時、「あの切り方は悪意や憎悪を感じさせる。樹木というものは、時間が積もったことを示すものでもあるけれども、そうした時間の堆積に対しての憎悪のようなものを感じてならない。枝や葉がうっとしいというよりも、時間が積もったことや時が過ぎてしまうことが我慢ならないのかもしれない」というようなことを話しました。
そこまで書いては少し文学的過ぎるかもしれないということで、そういう記述は抑えたのですが、やっぱり、私は樹木が象徴している「時間」というものへの悪意を感じざるおえないのです。
なんてことだ!
2005年05月25日(水)

西武池袋線江古田駅南口のすずかけの木です。この木は改札口の真向かいにあって、出かけて行く人には「いってらっしゃい」帰ってくる人には「お帰りなさい」と声をかけいるような木でした。日大芸術学部の卒業生の皆さん、M君、K君、M2君と卒業式の日にこの木のしたでお別れをしました。「それじゃあ皆さん、お元気で」とご挨拶した時、この木にはちゃんと枝がありました。
いったい何の目的でこんなきり方をしたのでしょう。邪魔なら切り倒してしまったほうがましなくらいです。いたぶって痛めつけるという切り方です。撮影日は5月23日です。ほんとうなら青々とした葉が風にそよいでいていい季節なのに、痛ましい限りです。
↑前のページ / ↓次のページ
|