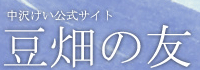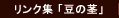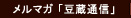|
|
 |
 |
| |
|
| |
朗読会のハプニング
2005年06月18日(土)
どのくらいの大勢の人の前で朗読をしたことがありますか?という質問に谷川俊太郎さんは
「僕、20000人」
と答えました。こういう答えをする時の谷川俊太郎さんは、黒っぽい骸骨がかくかく答えるような感じがします。近代文学館の朗読会の時のことです。
「20000人!」
いったいどんな場所でそんなに人を集めたのだろうと想像も付かないで驚いていると
「辻仁成のライブでね」
種明かしをしてくれました。
近代文学館の自作朗読会は詩人や作家の映像資料を残しておくという目的で開かれています。私が出た時は谷川俊太郎さんと安岡章太郎さんが一緒でした。
で、この朗読会でちょっとしたハプニングがありました。朗読が終わってから会場の観客とのやりとりがあったのですが、ひとりのご婦人が谷川さんに詩を読んでもらいたいと差出したノートがありました。
ノートにはベントレーに寄りかかった谷川さんの写真に添えて一編の詩が書き写されていました。
「あ、これ、僕の詩じゃないよ」
一読、谷川さんがそう言い出したので会場は緊張してしまいました。
「確かに写真は僕だけど、詩は僕の詩じゃないよ。しかし、これはひどい詩ですね」
こうしてますます緊張は広がって行きます。ステージにいた私もどうしたらいいのだろうとどきどきしてました。
谷川さんは声を少し大きくして、その詩を読みます。
「あの娘をペットにしたくて」
小林旭が歌っていた自動車唱歌だと谷川さんが読み進むうちに気がつきました。でも、「「いやあ、これはひどい」と言いながら、谷川さんが読み進んで行くので言い出すことができません。結局、谷川さんはその詩を全部、読んでしまったのです。朗読っていう感じではありませんでしたが、まあ、終わってみると結果として朗読になってました。それにしても30年も谷川俊太郎の写真といっしょに自動車唱歌を谷川俊太郎の詩だと信じていた人がいるんですね。
このときの朗読会の様子はあとでビデオにして家に届けてもらいました。このビデオを見たうちの子どもたちが、その時は、中学生くらいだったのですが「ええっ、谷川俊太郎って生きているんだあ」をおおいに驚いていました。教科書に載っていたのでもう死んじゃっているんだと思い込んでいたみたいです。人気のある詩人というのは、間違われたり、死んだことにされたり、いろいろとたいへんだなという話でした。
インドの朗読会
2005年06月17日(金)
朗読会って詩人はよくやる人もいるけれども、作家はあまりやりません。ただ、例外的に外国の作家のシンポジウムを開いたりする時は、お互いの作品の音の感触を確かめるために自作を読みあったりします。その場合、あらかじめ読む部分の翻訳を相手に渡してあります。
インドのカルカッタで松浦理英子さんが自作朗読をした時は、英語の翻訳を読んでました。日本語の自作朗読だと、とてもじゃなくけれども、顔から火がでちゃうくらい恥ずかしいっていうことで、英語の翻訳のほうは選んだということでした。で、ただ英語の翻訳を読むだけじゃ寂しいので、小熊英二さんが「音」を付けることになりました。
小熊さんは歴史学者ですが、ミュージシャンでもあるとのこと。で、急遽、音を付けるのにどうしかたというと会場のあるものを片っ端から叩いていました。カバンとかソファーとか鉄の柱とか、ともかくいろいろ叩いてみて、松浦さんの作品の内容に即した音がでそうなものを探して、朗読とあわせて行きました。会場はカルカッタ市内の出版社が経営している本屋さんでした。
このリハーサルの様子がすごくおもしろかったのを覚えています。おもしろいから日本でもやってみたらどうかというと、松浦理英子さんは「絶対やだあ!」という返事でした。その気持ち、解ります。
カルカッタは石を投げれば詩人に当たると言われる町で、自作の詩を読む朗読会は野外で、時には20000人くらいの人を集めて開かれることもあるそうです。
ううん、20000人はすごいなあ。詩人の谷川俊太郎さんも20000人の前で朗読をしたことがあるそうです。こちらは後楽園ドーム。それもすごい。
なりまさる
2005年06月15日(水)
大学の研究室の扉を開けたまま、夜の授業が始まる前に、生協で買ってきたパンを食べてました。すると廊下ととことこと横切ったスーツ姿の男性がいました。「誰かのところに来たお客さんだなあ」と見送りながら、ずいぶん立派なスーツの着方をしているなと感心してました。扉の前を通り過ぎたかと思うと、すぐにその男性がとことこと引き返してきました。
数年前に卒業したK君でした。確か高校の先生をしているはずです。大学にいたときよりもずっと自信の重みみたいなものが感じられる顔をしてました。にっこりしたK君の顔を見て
「まあ、ずいぶん立派になって」
なぜか私はパンを食べながらなのも忘れて、そう言ってしまいました。こんなにスーツが似合うようになるとは想像もしてませんでした。
N君はなにを思ったか5月の末からずっとスーツを着て学校に登校しています。就職活動かなと思ったのですが、本人はまったく就職する気はないでそうです。実際、就職活動もしてません。でも、なんだかスーツの気分なのだそうです。イメチチェン。そう言っています。スーツの方向にイメチェンするような自信が付いたみたいです。
M君は相変わらずのんびりやってますって言うのですが、なんとなく影のようなものが横顔に浮かぶようになりました。それが、詰まらない自信家の曇りない表情よりもよっぽど人としてのぬくもりを感じさせるところがあります。何があったのか、聞き出したいような気がするのですが、まあ、そう無闇に話したりはしないでしょう。秘密が出来た人の顔です。
古典語に「なりまさる」というのがあります。源氏物語などにはよく出てくるのです。成長して立派になったと現代語に訳すしと、とっても詰まらないのです。M君の影や、N君の本人にしか根拠がわからない自信や、K君の昔と変わらない微笑がその「なりまさる」という言葉の意味をよく体現しているようです。
それにしてもみんな大学をを卒業するとどんどん「なりまさ」って世の中の真ん中のほうに押し出して行く勇気がついてゆくようです。
伊藤比呂美さんから
2005年06月14日(火)
この間、丸谷才一さんの話を書いたら「綾とりで天の川」(文芸春秋刊)を送っていただいて「うふふ」だったのですが、今度はご本人の許可なく豆畑の朗読会2回目は伊藤比呂美さんをお迎えしますって言ったら、その伊藤比呂美さんから御著書が送られてきました。
ああ、びっくり。びっくり。聞こえてたのかな。
「レッツ・すぴーく・Englsh」
岩波書店刊
です。装丁は岩波書店というよりも学習研究社風。
それって、どんなんじゃと言われそうだけど、岩波書店の装丁をイメージして書店で探したら絶対みつかりません。「ア、アイム ファイン」って言っている女の子の漫画が載っている黄色い表紙です。
内容は一言で言えばブロークンイングシッリュの本。やあ、これは便利だ。外国からのお客様の時に、通訳がどこかに行ちゃって、二人でとり残されても、この本を読んでいれば大丈夫。非英語圏からのお客様でも大丈夫。正しい英語は通じなくても、ブロークンはなぜか非英語圏のお客様には通じるのです(これは経験済み)
伊藤比呂美さん、すごく、すごく役にたつ本を送ってくださってどうもありがとう。もし見ていたらスタッフ・ルームに書き込みを下さい。朗読会大好評でした。次の朗読会には絶対に出て下さい。
豆蔵師匠 さつまあげを持って現る
2005年06月13日(月)
豆蔵さんと朗読会の反省会をひっそりやりました。というよりもおもしろかったから、懲りずにまたやろうってな話でした。例によって江古田の「尾志鳥」で生中で乾杯。で、さつまあげを頂戴しました。
ちゃんと保冷在が入っていたところをみると、これは豆蔵さんのお母さんのご配慮でしょうか。さつまあげ、おしかったです。桜海老とねぎの入っているやつをさっそくいただきました。
愉快でした。
2005年06月12日(日)
豆畑の朗読会にご出演の皆さん、ご参加の皆さん、おかげさまでたいへん愉快な朗読会を開くことができました。どうもありがとうございます。
朗読会の様子はマニエニストQさんに書いてもらうことになっています。トピックス欄に掲載します。しばしお待ち下さい。
ここではその準備や周辺のことを少し書きます。私は午前中、朝日ニュースターの「パック・イン・ジャーナル」に出演して(生放送ですから)それから神田小川町に回りました。小川町画廊では、もう出演者の皆さんがそろって準備が進んでいました。集英社のYさんが会社に行く途中だと言って覗いてくれたのですが、いつもは真っ白な画廊にパイプ椅子が並んで、すっかりライブの会場になっているので「まあ!」と驚いていました。
狭すぎず、広すぎずちょうど良い感じでした。「え、こんなところなの、なんかもっと喫茶店みたいな感じなのかと思ってました」というのはあやこさんです。三々五々に皆さんお集まり。さて、もうすぐ五時というところで、突然、♪夕焼け小焼けで 日が暮れて♪とチャイムが鳴り出して、あまりのタイミングに皆さん大笑い。
5時になると千代田区の流すチャイムが響いてくるのを、私も含めて、みんな知らなかったのです。ちょうど良い開始の合図になりました。夏至が近いので5時と言ってもまだ街は明るく、遊びほうけている子どものためのチャイムで始まった朗読会でした。さて、朗読会が始まると道を行く人がおや、これはなんだろうという顔をした画廊の中を覗きこんでいました。なにしろ、ふだんは静かな画廊に人がいっぱいなんですから、さぞや不思議な眺めだったことだろうと思います。
こうして愉快な朗読会の時間はまたたくまに進んで行きました。その様子はトピックス欄で改めてご紹介します。
本日小川町画廊で朗読会開催
2005年06月11日(土)
本日、図書新聞小川町画廊で朗読会を開きます。予約はしてないけれど、行きたい。急に閑ができた。気が変わったなどなど、そういった方にもぜひぜひお越しいただきたいです。
ご出演のみなさん、準備はよろしいでしょうか?
それでは午後に、図書新聞小川町画廊でお会いしましょう。
明日は朗読会です。
2005年06月10日(金)
原稿プロセッサのインジゲーターに助けられました。1100字の原稿をどういうわけだか800字と勘違いしたのです。短い原稿をふつかに分けて書くと、時々こうした錯誤を起こします。紙の原稿用紙の時にはやらなかった間違いです。で、ふっとインジゲーターの棒グラフを見て、目標値までの空白が四分の一ほど残っているの気付きました。
「あれ!」と思わなければ今頃、原稿の書き直しに大騒ぎになっているところでした。で、いよいよ、明日の土曜日6月11日は朗読会です。豆蔵さん、準備は進んでいるでしょうか?魚子(ななこ)さんとまだ絡み合っている最中ですか?私のほうは準備万全どころか、まだ何もしてません。明日、午後に図書新聞小川町画廊に行きます。それから、なんとかします。はい。相変わらずどたどたです。すみません。
朗読会は近代文学館で、谷川俊太郎、安岡章太郎のお二人とご一緒させたいただい以来のことです。うまく行くかしら?
瀧と油揚げ
2005年06月09日(木)


なんだか妙な組み合わせですが、ま、油揚げがおいしかったのでお許しいただくことにしましょう。瀧はホウメイノタキと言ってました。岩山の間をくぐって流れる広瀬川です。何段もの瀧が続いています。雪解けの水と梅雨の雨水で数量が増してしました。どうどうと轟く瀧の音の響きが、豊かな山の緑の中に消えて行くのは気持ちの良い眺めでした。
定義如来の油揚げ
2005年06月08日(水)
作並温泉は仙台の奥座敷なんていわれる温泉です。2年ほど前の冬、韓国の作家の伊大寧氏を作並温泉に案内したことがありました。もちろん、その時は冬景色。今度は新緑の作並温泉に行ってきました。
作並温泉の近くにある定義如来は、近郷近在の信仰を集めているお寺です。おみやげに変わったものをふたつみつけました。ひとつは飴。古事記風に言えば「成り成りて成り余れるところ」と「成り成りて成り足らざるところ」をかたどった飴です。子宝祈願と安産祈願のお寺の縁起物のようでした。そうふざけたものではなくて、真面目に良い子が授かりますようにという願いがこめられているのでしょう。陰陽石のことは耳にしたことがありますが、飴は初めて見ました。
それから油揚げ。油揚げを入れた袋に「三角定義」としゃれていましたからそんなに古くからの名物ではないのかもしれません。ふつうの油揚げよりも厚いのです。しかし、厚揚げのように中がしっとりしているのではなく、さくさくしています。少し凍らせてから、揚げているのかもしれません。中がスポンジ状になっているところが、凍り豆腐と似ていました。子ども連れ家族連れの参詣者がたくさんいる境内では、この油揚げを焼いて、少々のねぎを載せたものを売っていました。
これがなかなかおいしい。あぶったくらいで食べるのです。それに、握りこぶしのような大きな丸いおにぎりに味噌を塗ってあぶったものも、人気がありました。素朴で単純ですが、味噌もお米もおいしいのです。地元の人々がお参りしている定義如来でした。
↑前のページ / ↓次のページ
|
| |
|
|
|
|
| |
|
| |
|