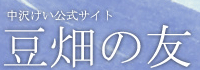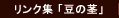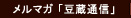頭の話
2005年07月21日(木)
森鴎外は奥さんに「なんでこんなに本を買うのか?読みきれないほど買ってもしょうがないじゃない」と言われて「馬鹿!俺の頭だけじゃ足りないから本を買うんだ」と答えたそうです。
聖ロカ病院の精神科医の大平健さんは「病理学ってのは個人の頭だけを調べるけど、だからわかんないことがおおくなるんです。人間は他人の頭も利用して生きている生き物だからね。何か忘れた時に、ほかの人に尋ねたりして思い出すかわりにするでしょ。あんなふうに一人の頭だけじゃなくて、他人の頭も使って生きているんです」とおしゃっていました。
パーソナルメディア社のHさんは「携帯電話っておもしろいですね。これって、誰も電話番号を覚えようとしないでしょ。マシーンに記憶させてあるから。なんだか頭の中身を携帯電話のほうに出して使ってみるみたいですね」とおしゃっていました。
人間の頭ってのはもともとネットみたいになっているんですねえ。なるほど、なるほど。そう考えてみると時にはみんなの頭が悪くなっちゃうコンピュターウィルスみたいな人間どうしの悪いコミニュケーションもあれば昔から「三人寄れば文殊の知恵」というくらいに、頭を二倍にも三倍にみ使えるようになるコミニュケーションもあるんですねえ。
ひとりの時間
2005年07月20日(水)
ここのところ、ほかの人と一緒に仕事をする時間がふえています。すると、不思議なことがおきました。ひとりになると頭の中がからっぽになっているのです。何も考えていないというと、無念無想などを連想していいことのように思う人もいるかもしれませんが、そうじゃなくて「からっぽ」とか「あほ」とか「ばっかみたい」の類いです。
会社に勤めている人が、社内のうさわばなしや人事の話が好きな理由が解るような気がしてきました。なんであんなに人事がらみの話がすきなんだろうって、不思議に思っていたのですが「からっぽ」とか「あほ」とか「ばっかみたい」の状態の頭に浮かぶのは、たいてい直近の過去に体験したことばかりで、人と共同で仕事をしていると、自然に一緒に仕事をしている人の顔や態度が浮かんでくるんです。なろほど、こんな心理状態だったのかと改めて納得してます。
そうしてみると、ひとりの時間ってのは、頭を良くする時間なのかもしれません。うまく言えないのですが、ひとりの時間は頭のご飯の時間で、ほかの人と共同で仕事をする時間は頭の体操の時間みたいなイメージです。
頭のご飯の時間をちゃんととらなくっちゃ、カロリー不足になってしまうのでしょう。きっと、そんな感じですい。
連休が終わってさて夏休み
2005年07月19日(火)
連休が終わったら夏休みという学校も多いでしょう。今年の夏休みは東京の美術館や博物館を歩いてみようかなと思っています。できたらという話ですが・・・。
夏休みになったらなんとかしますと約束した仕事の山を考えるとそれどころではないのですが。いや、でも夏休みに何をしようかなって考えるのはすごく楽しいので、その楽しみくらいは味わってもいいかなって(で、仕事の山はどうなるのだ?)
外国の都市に行くとせっせと名所旧跡博物館美術館と周り歩くのに、東京では行ったことがない美術館や博物館がたくさんあります。(仕事の山だけじゃなくて、この間、申京淑さんに、夏休みになったら、生活韓服を買いにソウルに遊びに行くって約束しなかったけ?)で、まるでよそから来た人みたいにぶらぶら歩いたら楽しいだろうなあと空想(空想はいいのですが、夏休みになったら飲もうとかなんとか約束した人が幾人いる?)
夏休みが無限にあるような気がしてくるのは、毎年7月20日前の恒例なんですが・・・。(それにしても気が多いとしかいいようがない)
忘れてない?イラクの自衛隊のこと
2005年07月18日(月)
ロンドンでのテロ事件に続き、昨日はイラクで大規模なテロ事件がありました。テロ事件があるたびに「テロには屈しない」という言辞がひとり歩きしてしまいます。そうこうするうちに、イラクから自衛隊を引き上げるタイミングを逸してしまうのではないでしょうか?
「テロには屈しない」といわざる終えない状況があるのですから、サマワの自衛隊を引き上げる期限をきちんと決めるべきなのです。一時、12月には引き上げという説がかなり信憑性の高いものとして流れていましたがこの頃、消えてしまいました。
テロ事件のたびに、テロの原因をなくすことも必要だとして「貧困撲滅」などが上げられていますが、どもうこちらの意見もピンと来ないのです。ほんとうに問題は「貧困」にあるのでしょうか?ロンドンでもニューヨークでも狙われたのは金融街でした。「金融」に対する憎悪と「貧困撲滅」が一直線には繋がらない感じがします。
7月14日のパリ祭にフランス各地で起こった騒乱といい、断片的な情報は日本の新聞も伝えているのですが、そうした事件の裏で動いている思想的哲学的変容はほとんど伝わってきていません。物を考える手がかりが伝えられていないのです。
伝わってくるのはアメリカ政府高官の談話ばかり。派遣する時には賛否両論であんなに大騒ぎしたイラクの自衛隊も、どうかすると引き上げが難しくなりかねないのに、引き上げ時期の明示するように政府に迫ることはないというのも、ちぐはぐな状況に思えます。これも物を考える手がかりを失っているためでしょうか?
危険?なパフェ
2005年07月17日(日)
光が丘公園でお祭りをやってました。で、雑踏の中で変わったものを見つけました。豆電球に水あめが巻きつけてあるのです。闇にぴかぴか光る水あめ。けっこう人気で、小さい子から高校生くらいまで、あっちでもこっちでもぴかぴか光るあめをなめていました。
誰がこんなしかけのあめを考えだしたのでしょう。豆電球は点滅されることまでできるのです。すごい!
小さな女の子がそのあめを、お父さんに買ってもらってました。そして、お父さんは心配そうに「ねえ、熱くないかい?熱くないの?」と聞いていました。
それで思い出したのが危険な?パフェのこと。子どもたちが小さいときに、あるファミリーレストランに食事に行き、ドライ・アイスの煙がもうもうと出ているパフェを注文したのです。ガラスの入れ物が二重になっていて、外側に赤い色をした水が入っていました。水の中でドライ・アイスが煙を出しているのです。で、ガラスの器がもうひとつあり、そこにパフェが盛り付けられていました。
煙がもくもく出てくるパフェを大喜びで食べていた子どもたちですが、盛り付けられたクリームやお菓子を食べ終わった頃には、煙のすっかり消えました。で、ガラスの器をはずして、中の液体を眺めていた子どもたちは
「お母さん、これ、飲んでもいいの?」
と聞いたのです。ドライ・アイスの入っていた液体を飲むことなど想像してなかった私はただただ絶句。
とても飲みたそうにしているので「まて、まて、まて」と押しとどめて、自分でちょっと赤い液体をなめてみました。甘いのです。口に入れていけないものなら甘い味付けはしないでしょう。でも、まだ、不安。で店員さんに尋ねました。「これは飲めますか」と。「はい、飲めます」と聞いても半信半疑。子どもたちはもう赤い液体を飲み始めてました。
ううん。よく怖くないなあと半ば呆れながらも私はかなり不安な気持ちでいました。ドライ・アイスって毒じゃないのは解っていても、なんだか魔女のおばあさんに騙されているような気分でした。
いったいヨーロッパでは何が
2005年07月16日(土)
いったいヨーロッパでは何が起きているのでしょう。以下のようなニュースをネットで見つけました。時事通信が伝えたものです。
「14日のフランス革命記念日(パリ祭)は大荒れとなった。ロンドン同時テロの直後でもあり、警備に多くの治安要員が動員されたが、パリと周辺地域を中心に騒ぎが多発し、約200台の車が焼かれ、数十人が検挙された。若者たちと警官隊との衝突も発生した。」
この記事によると警察は肩掛け式の手投げ弾発射機まで用意したということですから、尋常な騒ぎではありません。200台の車が焼かれたのです。いったいこの騒ぎはどのような不満から引き起こされているのでしょう?パリ北部郊外ではシナゴーグに火炎瓶が投げつけられたそうです。
ヨーロッパではいったい何が起きているのでしょうか?宗教対立なのか?それともEUの統合への不満なのか?事件を伝えるだけのべた記事では不可解なことが多いのですが、去年の夏あたりから、こうした警官と一般の人々の衝突の記事を時々見かけるようになりました。
小さなお屋敷
2005年07月15日(金)
マンションって2DKでも3DKでも小さなお屋敷だなって思うことがります。隣家との距離がとっても遠い小さなお屋敷で、家の中で何もかにも用事を足らしてしまおうと思ったら、たいていの用事が済んでしまうという、そういう小さなお屋敷です。
で、このお屋敷はあんまり小さいものですから、片付けるのにはたいそう手間がかかります。一日放りだしておくとそれだけもう雑然としてしまいます。こまごまこまごまと片付けておかないと、とたんに何がなんだかわからない乱雑さが出現します。
やれやれ小さなお屋敷を保っておくのも容易じゃありません。ここのところ宴会続きだったのです。ですからお屋敷は荒れ放題。八重葎のかわりに新聞紙になりかけた新聞が散らばり、蓬のかわりに、ファックス用紙が散乱しています。
クーーール・ミズ
2005年07月13日(水)
電車の中で見かけた豊島園のポスターです。「クール・ビズ」ではなくて「クーーール・ミズ」の文字の下は青く輝くプールの水。来週には梅雨明けしそうな様子です。このポスターの隣りには、バスタブの中で浮き輪を使っている小さな女の子。「イメージ・トレーニング」の文字。うちでも子どもたちが小さいときは風呂場でイメージ・トレーニングをやってました。浮き輪だけじゃなくて、水中眼鏡までかけてました。
東京新聞で、政治部記者と話そうという連載をやっています。一ヶ月に一回くらい、政治部の記者の高田さんをお話しています。で、今回は「クール・ビズ」が話題になるのかな?と思っていたら、「党議拘束と政治家個人の政治信条」でした。記事は来週でるはずです。
で、これはたぶん記事にならないかもしれない雑談なのですが、政治家の発言よりはどんな襟のシャツが似合うかで、政治信条が一目瞭然になりそうという話になりました。例えば、開襟襟が似合いすぎるあの人とか、ボタンダウンのシャツを着たとたんに学生時代のお金持ちお坊ちゃまの素顔を見えてしまうあの人とか、なぜかマオカラーが似合いそうな怪人とか、ここには具体的な名前が入っていたのですが、それはご想像にお任せします。
ちょっと前に「豆畑の友」のスタッフ・ルームでもクール・ビズが話題になっていました。
申京淑さんにお目にかかって来ました
2005年07月12日(火)
日曜日(10日)法政大学のスカイホールで行われたシンポジウムで久しぶりに申京淑さんにお目にかかってきました。今回はご主人も同行されていました。背の高い詩人であり、評論家であり、大学でも文学を教えているというご主人でした。どちらも静かな方です。
ときどき作家というのはなんと物覚えがいいんだ!と驚かれることがありますが、申京淑さんについて言えば、私も驚嘆するほどの記憶力を持っています。2000年に青森で開催したシンポジウムの時に履いていたスカートをご記憶でした。豆畑の朗読会の時にも履いていたスカートです。ベージュのロングスカートですが、胸元に紐がついていて、紐を縛って着るようになっています。KENZOのもので、朝鮮のチマ(チマチョゴリのスカート部分)からヒントを得たデザインだったのを、おもしろがって着ていたのです。
申京淑さんは「懐かしい」お人柄で、別段、お話することはなにもなくてもそばにいるとほんわりと和んでいられる感じの人です。
街路樹多難
2005年07月10日(日)
お知らせが遅くなりましたが、以前「豆の葉」にかいた街路樹の剪定に関連して、以下のようなお手紙をいただきました。
「7月7日付けの日本経済新聞夕刊に、街路樹の強剪定についての記事が掲載されておりましたが、ご覧になりましたか。
緑を増やそうと街路樹を植樹したにもかかわらず、予算不足で丁寧な管理ができないためにバッサリと枝を落とさざるを得ないという事情が報告されています。
葉っぱが一枚もない街路樹では、なんのための緑地化なのでしょうか。自治体の無計画な管理のために、日本中の街路樹が悲鳴を上げているかと思うといたたまれません。
これからの季節、炎天下の街中でも、木漏れ日の下で足を止めれば、ほっと一息つけるような、立派な枝ぶりの街路樹を守っていかないといけませんね。」
今日になってようやく日経の記事をみつけて読むことができました。7月7日夕刊17面の「樹木多難」という記事です。その記事によると東京都の場合は、街路樹の管理のための予算のピークは1996年で、現在はその当時の半分の22億円ほどの予算になっているそうです。にもかかわらず、都が管理する樹木は96年当時の13万本から16万本に増えているとのことでした。
チェーンソーでいきなり幹を切ってしまうような剪定を強剪定というのだということも、この記事でしりました。また競争入札が影響しているとの指摘もありました。それにしても、街路樹そのものをからしてしまうような剪定は乏しい予算の二重の無駄遣いに見えます。
↑前のページ / ↓次のページ
|