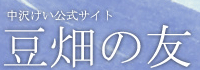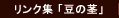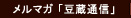|
|
 |
 |
| |
|
| |
ながしろばんりさんの朗読会
2004年08月31日(火)
9月5日にながしろばんりさんが朗読会を開くようです。ご興味のある方はスタッフルームのほうをお尋ねください。メールをいただければキーワードをお知らせします。
ながしろばんりさんはこのホームページの管理人さんです。
世界最速のブラスバンド
2004年08月29日(日)
世界最速のブラスバンドと言われるルーマニアの
「ファンファーレ・チォカリーア」
の演奏を隅田トリフォニーフォールで聞いてきました。すごくエネルギッシュな演奏で、トランペットなどはこれでもかこれでもかという高音の連発。ずっとリズムを打っていたホルンは、途中で歌も歌えば、悪踊りも踊るという体力。
パイプオルガンが備えつけてある音楽ホールで聞くよりも、遠くのほうからやって来る音楽をわくわくしながら聴きたいなあという吹奏楽でした。子どもが夢中になって楽隊のあとを付いて行き神隠しにあうようなそんな感じです。
ホールでの演奏が終了したあとで、ロビーに突然、現れた彼らが、即興演奏をしてくれました。この即興の音がとても素敵でした。肺活量も凄いけれども、ウェストサイズもすごいおじさんたちのノリノリの演奏です。音楽とは関係ないけれども、こういう人たちの
シャツの着方ってとても素敵です。なんの変哲もない白いYシャツなんですが。
気力減退
2004年08月26日(木)
夏ばてで気力減退。でもなぜか歩くのはとても楽しくて、仕事を放り出して歩いています。近所の公園は元は米軍の高級将校の住宅地だった場所です。その頃の樹木をそのまま公園の木にしました。
米軍の将校住宅だった時は植木もアメリカ風に刈り込まれていました。沖縄でも米軍基地はアメリカ風に刈り込まれています。どんなのがアメリカ風かと言えば樹木の容姿に関係なく同じ形に切りそろえるのです。米軍から返還されたそろそろ30年になる家の近くの公園の樹木はこの30年で、すっかり日本の樹に戻りました。でも、横に枝を張り出したマテバシイの樹だけは、背の伸びる時期を過ぎていたのでしょう。今でも太い幹から枝が横に張り出して、マテバシイらしからぬ姿をしています。
気力は減退しているのだけれども体力は回復しているので、公園の樹木を見て歩いています。
「誰も知らない」見てきました
2004年08月08日(日)
カンヌで主演男優賞を受賞した「誰も知らない」を見てきました。初日です。午後四時からの回を見たのですが、舞台挨拶があったためか40分遅れの開演でした。午前中に7時の最終回までの切符が売り切れてしまったようです。観客は若い女性が多いように見受けました。予告や広告は全部カットでいきなり本編の上映でした。
1987年に戸籍のない四人の子どもたちが暮らしていたことが解った事件は、私も興味を持っていました。一番小さな子が死んでしまったことから、この子どもたちの存在が解ったのです。家の中を探せばその当時の新聞の切り抜きがあると思います。
映画では焦点は一番上の男の子に当てられています。上映後、「厳粛」と言ってもいいようなしいんとした空気が客席に流れてしました。言葉では説明しにくいので、見てもらうのが一番だと思います。
12、3歳くらいの男の子の成長っていうのはすごいなあとため息が出るくらいのものです。映像がすごくリアルなのですが。同時にピュアで透明で、美しいので、リアリズムのあり方とはなんだろうと考えてしました。
ところで実際の事件では、私は母親がどうやって子どもを生んだのかに興味を持っていました。出生届けを出さずに子どもを四人も生むのはなみたいていではありません。行政サービスを受けることができないのですから、出産後をどのように乗り切ったのかの気になります。都市の中に棲家を変えた山姥みたいな話だなと思ったものです。昔話に出てくる山姥は金太郎のお母さんです。そのあたりは映画では省略されていあますし、また映画の主題でもありません。
母親役のYUOはたいへん評判がいいということでした。なんとなく許せてしまう。あるいは置き去りにされた子どもたちが母親を思うような気持ちと同じ気持ちにさせてしまうところがYUOの演技にはあって、一番上のお兄ちゃんの柳楽優弥と良いコンビでした。
銭洗弁天
2004年08月07日(土)
夏の鎌倉を散歩してきました。鶴岡八幡宮の源平池では、紅白のハスが今を盛りに咲いていました。いつのまにか白いハスが増えてしまったみたいです。
鶴岡八幡宮から佐助のトンネルを通って銭洗弁天へ。佐助はそのあたりの地名でもあるのですが、これはもとは人の名前なのでしょうか?いつも不思議に思っているのですが、あとで調べようと思うだけで、すぐに忘れてしまします。
銭洗弁天は佐助を山のほうに入った不便なところにあるので、初めて行きました。弁天様が祭られている岩穴の清水でお金を洗うと、お金がたくさんに増えると言われています。小さなお社で、もしお金を洗うなどという習慣がなかったらとっくに忘れられてしまった神社かもしれません。
お金はざるに入れて洗います。一万円札を洗う人もいるそうです。五百円玉を洗ってみました。お金がきれいになったような感じがしました。となりでお金を洗っていた男の人が「マネーロンダリングだな」とつぶやいていたのには、思わず笑ってしまいました。奉納された絵馬を見ていたら「宝くじが当たりますように」というお願いがあって、なんとなく「なるほど」とうなずいてしましました。境内には「洗われたお金は有意義なことにお使いください」という張り紙がありました。有意義って人によって感じ方が違うのだろうなあとしばしせみ時雨の声を聞きながら考え込んでしいました。
湿った山道に開いたトンネルの向こうにある銭洗弁天は、沖縄の「ウタキ」に似ていました。周囲を山に囲まれ、洞窟には清水が湧き出しているので、きっとここは大昔に人は住んでいた場所にちがいないと思いました。清水が湧き出している涼やかさが、夏の午後にはとても清涼に感じられて、隠れ家か何かに忍び込んだような気がしました。こういう場所を人が暮らしていた時はまだお金なんて必要ない時代だったのでしょう。いったい一番最初にざるにお金を入れた洗ったのは誰だったんでしょうか?
銭洗弁天からひさしぶりに大仏さんの顔を拝んでついてに長谷の観音様にもお目にかかってきました。子どものころ、親に連れてきてもらったことのある神様や仏様というのは、なんだかちょっと親戚のうちに顔を出したような感じがするものです。懐かしい人に会った時の感じに似ています。
厄日かな?
2004年08月02日(月)
机の上にあったインク瓶に手を伸ばした時、あ、倒れそうだなと思った瞬間、インク瓶は横倒しになっていました。これが昨日の午前中の出来事。机の上はブルーブラックのインクの海。
晩御飯のあと、ひと眠りしていると息子が「水槽のポンプが逆流しちゃってさ」と言ってきました。最初は寝ぼけまなこで聞いていたのだけれども、そのうち彼の部屋は水浸しということに気づいてあわてました。なぜ水槽のポンプが逆流してのかを、息子は説明するのですが、どうも要領を得ません。たぶん言いにくいことが、ひとつか二つあるのです。
水槽にはエビユキーズという名前の海老が三匹すんでいるのですが(三匹でエビユキーズです)海老たちも畳の上をぴちぴちはねていました。
マンションの8階なのに床上浸水状態。なんだか憮然としてしまいました。彼の部屋はとても寝られる状態ではないので居間に寝るということになりました。それで、彼が居間に掃除機をかけていると今度は電源が落ちてしました。ますます憮然。なにしろパソコンは起動していたので。憮然としていると、なぜかピアノの上にあった弟の結婚式の写真が、かたりとピアノの裏に落ちました。ああ、今日は厄日みたい。という昨日でした。
ミャンマー人と間違えられる
2004年07月31日(土)
先週の土曜日のことでした。ともだちが入院している東京医科大学病院にお見舞いに行きました。ロビーで女の人から声をかけられたのですが、なんだか解らない言葉で話しかけてきます。「何語だろう?」と首をしばらくかしげてました。それで、とりあえず日本語で「今日は暑いですね」と言ってみました。
「日本語が上手ですね」といわれたので、ははんこれは何か間違っているなあと思いました。
「ネイティブですから」と言って笑ったら、とたんにその女性は困った顔になってしまいました。ちょっとあわてています。
「いえ、ミャンマーの人だと思ってのです。ごめんなさい。」
「じゃあ、今のはミャンマー語ですか?ミャンマー語の勉強をしているのですか?」
「少しだけミャンマーにいたことがありまして」
たいへん恐縮した様子でそう言っていました。ミャンマー人に間違えられてたのは初めてでした。なんだかちょっと気まずいので、その人にミャンマーのことを少しだけ教えてもらいました。
そういえば、韓国の出かける前に銀座の鳩居堂へお土産を選びに行ったら、そばにいた人から英語で話しかけられたので、片言の英語で答えておきましたが、きっとあの人もどこか別の国の人と私のことを思い込んでいたふしがありました。この時はなんだかだましたようで、その人が売り場から居なくなるまでに日本語を使わずに済ませました。でも何人だと思ってのかな。聞いてみたら意外な答えが帰ってくるかもしれないなあと思いました。
桔梗と赤いかさと黄色い長靴
2004年07月26日(月)
中学生の時の夏休みの宿題にスケッチをしてくることというのがありました。家の庭先に桔梗がたくさん咲いていたので、それをスケッチしました。琳派風というと大げさですが、背景を水色に、桔梗の花を紫で、花芯を黄色に塗ろうと考えていました。
めずらしくこのスケッチが美術の先生に褒めてもらえてうれしかったのですが。そのあとがいけません。ここに黄色の長靴と赤いかさを描くともっとよくなるよと、画面にかさと長靴が加わってしましいました。水色の大空が急に小さくなった感じで、この絵をどう仕上げたていいのかさっぱり解らなくなってしまいました。
今でも、そのときの感じが残っていて、創作クラスの人の原稿に手を入れるのは嫌だなあと億劫になることがあります。ううん。教えるほうに回ると黄色の長靴と赤いかさを描いた先生の気持ちもわかるのですが。
トラジ、トラジ、トラジ
2004年07月25日(日)
韓国の市場ではトラジをよく見かけます。トラジは桔梗のことです。食べるのはどうやら根っこの部分みたいです。桔梗は日本でもよく見かける夏の花ですが、どういうわけか食べるというは話はあまり聞きません。
慶州はここのところ雨降り続きだったと言います。新潟や福井に豪雨をもたらした梅雨前線の延長が朝鮮半島にもかかっていたのです。韓国では梅雨をチャンマ(長雨)と呼びます。私が慶州に行った時は幸い久しぶりのお天気となりました。(晴れ女は誰だ?)
晴れれば暑いのですが、川の土手にはオミナエシがたくさん黄色く群れていました。また、あちらこちらに桔梗の花が、白と紫で入り混じりながらさいていました。昔「トラジ、トラジ」と繰り返しのある歌を聴いたことがあるのですが、いったいどんな歌だったかそれ以上は覚えていません。でも、故郷の桔梗の花を懐かしむ内容だったと思います。
紫の花だけでなく、白い花も混じると、とたんに華やかな感じがする桔梗でした。この桔梗、東京近辺では平将門の愛妾の名前が「桔梗」で、将門はその桔梗に裏切られて敗戦に追い込まれたそうです。それで将門塚には桔梗が生えないという伝説を聞いたことがあります。
生活韓服
2004年07月24日(土)
大急ぎで韓国を旅行してきました。
日本で着物のことを洋服に対して和服といいますが韓国でも、洋服に対して、チマ・チョゴリやパジ・チョゴリのことを韓服といいます。韓服は結婚式などのお祝いの時やお葬式に着ることが多いのですが、日常的に着られるようにデザインを工夫した生活韓服が数年前から流行しています。
夏の生活韓服は蝉の羽のように薄くすけるように織った麻などの生地がとても涼しそうに使われています。今度はたった2泊3日でソウルから慶州、またソウルに戻るという大急ぎの旅でしたが、生活韓服を着た若い旅行者をよく見かけました。男性用もあります。染めや織りに伝統的技法をつかったり、天然染料を使っているので優しく見えます。
この夏用の生活韓服が一着欲しかったのですが、残念ながら選んで買う閑がありませんでした。来年の夏はぜひソウルに夏用の生活韓服を買いにいかなくちゃ。
↑前のページ / ↓次のページ
|
| |
|
|
|
|
| |
|
| |
|