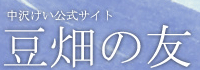|
|
 |
 |
| |
|
| |
水田三喜男の生家
2005年04月18日(月)
房総に行ってきました。鴨川市の山へ入ったところにある水田三喜男の生家を見てきました。水田三喜男は1960年代に佐藤内閣の大蔵大臣などを勤めた政治家です。高度成長期の通産、大蔵大臣で、高度成長政策の中心的な人物の一人です。その生家は安政年間に建てられたものだそうです。浦賀沖に黒船が現れたころですが、きっと家を建てている最中には幕府がなくなるとは思っていなかったでしょう。
房総はもともと酪農が盛んな土地ですが、水田家は日本で最初にホルスタイン種の牛を飼育した家だそうです。ホルスタイン種の牛を飼ったのが水田三喜男のお父さんでした。そのあたりは曾呂村というのですが、江戸時代には毎年5月に「馬捕り」で賑わったといいます。さて「馬捕り」とはなんでしょう?どうも文脈から判断すると馬の市のような気がしますが・・・。
大きな長屋門の左右には牛のための部屋(牛小屋)がありました。水に乏しい場所で、飲み水は遠くの湧き水を汲み、そのほかの水は母屋の裏にあるため水を使っていた様子です。水をためる四角い池のそばに水神様がまつってありました。なかなか暮らして行くのが容易でない土地です。それほど裕福な家にはみえませんでした。長屋門は客間を持つ家にしては質素なくらいです。しかし、この家は西洋種のホルスタインを飼育する決断をした時にある程度の経済的な基盤を築くことに成功したのでしょう。日本の酪農発祥地と言われる嶺岡牧場のすぐ近くで、嶺岡牧場にもかかわりがあったかもしれません。黒船が来なかったら、水田三喜男も寂しい山里の牛飼い馬飼いの三男坊で生涯を終わったかもしれないと考えてみると、歴史の巡り方は不思議なものだと思いました。
以前、ここに紹介した仁衛門島の仁衛門屋敷が海の交通を担った人々の元締めのような存在であったとすれば、水田家のほうは、陸の交通に大切な牛や馬などを生産していた人々の元締めみたいな家だったのでしょう。
房総では田のしろかきが始まっていました。しろかきを終えて新鮮な水が流れ込んだ田では、もう田植えを始めているところもありました。
↓前の日記
/ 次の日記↑
|
| |
|
|
|
|
| |
|
| |
|